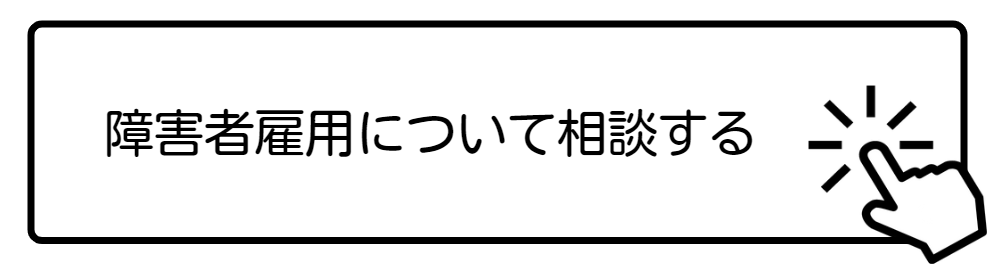Q&A「新型コロナ、緊急事態宣言などで精神的に不調になりがちな社員への対応方法」
新型コロナウイルスの感染拡大、再びの緊急事態宣言など、企業担当者様におかれましては、ご対応にご苦労されている方々も多くいらっしゃるかとお察しします。精神・発達障害の社員の方をマネジメントしている管理スタッフ・上司の方々からは、長期にわたる在宅勤務や、社会情勢などにより不安が強くなり、メンタル不調になるメンバーの対応に苦慮されている旨のご相談を、多くお受けしております。
ネットなどの情報を読むと不安になってしまう
具体的な事例として最も多いのは「ネットなどの情報を読むことで不安が強くなるようです。ネットの閲覧やニュースを見たりすることを制限させたほうが良いのしょうか?」という内容です。
ネット閲覧を制限することはあまりお勧めしません。実際問題として、「あまりネット情報などを見ないように」とアドバイスしたとして、行動を制限できるものではありませんので、多くの場合は我慢できずネットを見てしまうでしょう。また、仮に見るのを我慢できたとしても、それが更にストレスとなったり、情報が足りないことでより不安を強くしてしまうこともあるでしょう。
このため周囲として支援できることを2つご提案します。
情報取得が心理的に良い方向に向かうよう、情報の取り方を具体的にアドバイスする
行動を制限することが、問題解決になるとは限りません。「どうしても見てしまう」という衝動を理解・受容したうえで、上手にポジティブな行動に置き換えたり、意味付けをリフレーミングすることが効果的です。
偏った情報ではなくバランスよく幅広い情報をとるようにアドバイスしましょう。SNSや掲示板などの情報ソースが不確かな情報だけではなく、大手メディアのニュースや公的機関のウェブサイトもバランスよく閲覧するとで、不要な不安を掻き立てられることが少なくなることが期待できます。
もう一つは「検索の仕方」をアドバイスすることです。「コロナ 不安解消」や「在宅勤務 メンタル管理」など具体的に検索ワードを挙げながら、ポジティブにネット情報を使うことができるよう具体的なレクチャーすることが有効です。
社内だけで抱え込まずに公的な相談窓口を上手に活用する
不安な気持ちや焦燥感を一人で解消するのはとても困難です。信頼できる人と会話することで気の持ちようを切り替えていくことが重要ですが、そのコミュニケーション機会を社内だけでサポートすることは、多くの企業様では難しいことかと存じます。
不安が強く、頻度高くコミュニケーションをとる必要があるメンバーは、地域の支援機関などにも定期的に相談するように伝え、サポートの負担を分散していただければと思います。また、厚生労働省や自治体などが、新型コロナウイルス感染症関連の心の相談窓口を開設しています。
サポートする側が、サポート疲れしてしまっては元も子もありません。会社内だけで抱え込まず、公的機関の相談窓口を上手に活用し、この状況を乗り越えていきましょう。
心の悩みにおける相談窓口一覧pdf(厚生労働省)
Kaienでは、人事ご担当者様に向けて人材活用や障害者雇用を取り巻く情勢など、日頃の採用活動に役立つ最新情報をメールでご案内しています。
人事担当者向け 無料セミナー(約1時間)
| 日時 | 場所 | イベント | 申込 |
|---|---|---|---|
| 2024/5/20(月) 15:30 | オンライン | 障害者雇用における面接のキホンをレクチャー「精神・発達障害者の採用面接 初心者講習」 | リンク |
| 2024/5/21(火) 14:00 | オンライン | 新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー<業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |
| 2024/5/27(月) 14:00 | オンライン | 「合理的配慮」議論を始めていますか? | リンク |
| 2024/5/27(月) 15:30 | オンライン | 経産省推進事業「ニューロダイバーシティ人材活用」 導入支援プラン 人事ご担当者様向け説明会 | リンク |
| 2024/6/12(水) 13:30 | 東京・秋葉原 | 【就労移行支援の見学あり】新任の障害者雇用ご担当者向けセミナー <業務切り出し・採用・定着の基礎知識から、最新の民間サービスのトレンドまで> | リンク |
| オンデマンド配信 | ー | サテライトオフィス大阪弁天町 法人向けサービス説明会 | リンク |
| オンデマンド配信 | ー | ゼロからはじめる障害者雇用「小売業編」 ~業種別の障害者雇用事例シリーズ 第1回~ | リンク |
| オンデマンド配信 | ー | はじめて発達障害の部下を持つ上司のための「基礎知識・初期対応・マネジメント講習」 | リンク |
| オンデマンド配信 | ー | 助成金を活用した障害者雇用の採用と定着のための取組み事例 | リンク |