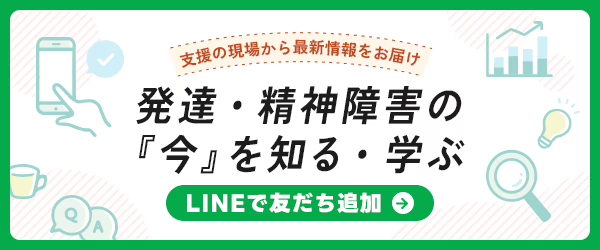「自分や家族が障害者雇用を利用したいと考えている」という人も多いかと思います。障害者雇用の利用を検討している人は、制度の概要や対象者、メリット・デメリットなどを把握しておきましょう。
この記事では、障害者雇用について詳しく解説します。対象者や一般雇用との違い、メリットや注意点、特例子会社の障害者雇用の特徴、活用できる支援機関などを紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
障害者雇用とは
障害者雇用とは、一般雇用とは別に障害を持つ人を対象とする雇用枠を用意することです。従業員数が一定数を超える企業や自治体は、一定割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。また、障害を持つ人が働きやすいように、環境の整備や合理的配慮、差別の禁止なども求められます。
障害者雇用の対象者と目的、一般雇用との違いについて詳しく見ていきましょう。
障害者雇用の対象者
障害者雇用は、原則として障害者手帳を持っている人が対象となります。具体的には、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを取得している人です。
従業員数が一定数以上の企業では、一定割合以上の障害者を雇用することが定められています。このとき人数としてカウントできるのは「週所定労働時間が20時間以上」という条件を満たしている人です。しかし、障害の特性などによって週20時間以上の就労が困難で、障害者雇用枠の利用が難しい人も多いという問題がありました。
そこで制度変更が行われ、2024年4月1日以降は週10時間以上の労働者についても障害者雇用の人数としてカウントできるようになっています。具体的なカウント方法は、以下の通りです。
| 週所定労働時間 | 10時間以上20時間未満 | 20時間以上30時間未満 | 30時間以上 |
| 身体障害者 | – | 0.5 | 1 |
| 重度身体障害者 | 0.5 | 1 | 2 |
| 知的障害者 | – | 0.5 | 1 |
| 重度知的障害者 | 0.5 | 1 | 2 |
| 精神障害者 | 0.5 | 0.5 | 1 |
このように、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者については、労働時間が週20時間に満たなくても障害者雇用枠の採用人数として扱えます。また、これは従来の制度ですが、重度身体障害者と重度知的障害者については1人の採用で2人としてカウントできるようになっているのも特徴です。
障害者雇用の目的
障害者雇用の目的は、誰もが希望や能力に合った仕事に就いて活躍できる社会を作ることです。障害者雇用を通して、障害の有無に関係なく誰もが社会参加できる「共生社会」を目指しています。
また、障害者雇用は企業にとって労働力の確保や生産性の向上が目指せるという側面もあります。それぞれの特性を活かせる職場環境を整備して活躍の場を提供することで、企業は貴重な労働力を確保できます。
障害者雇用と一般雇用の違い
障害を持つ人は、一般雇用と障害者雇用の両方を利用できます。
一般雇用は、企業が提示する条件を満たす人なら誰でも応募できる採用枠です。さまざまな職種の求人があり、求人数も多いため、就職の際の選択肢が幅広いというメリットがあります。一方、障害を持つ人の採用を前提としていないため、職場によっては十分な理解や配慮が得られない可能性があるのがデメリットです。
障害者雇用は、先述の通り障害者手帳を持つ人を対象とした雇用枠です。障害を持つ人の採用を前提としているため、理解や配慮を得やすいというメリットがあります。
一般雇用と障害者雇用では、就職後の定着率に差が出ているのが現状です。障害者職業総合センターの調査によると、障害を持つ人の1年後の定着率には以下のような差が出ました。
- 障害者雇用枠:70.4%
- 一般雇用枠(障害非開示):30.8%
障害者の採用を前提としている障害者雇用のほうが、一般雇用と比較して定着率が高いことがわかります。
障害者雇用と特例子会社で働くことの違い
特例子会社とは、親会社が設けた、障害者のための子会社のことです。厚生労働省の認定を受けることで、障害者の雇用数を本社の雇用人数と合算できる仕組みになっています。
この制度は、障害のある方の雇用拡大を目的に作られました。一般の企業では配慮が行き届かず、就職が難しい場合が多くあります。そこで、特例子会社においてサポート体制を手厚く整えることで、誰もが働きやすい職場を増やすことを目指しています。
そのため、特例子会社では、職場環境や業務内容が、障害の特性に合わせて配慮されている傾向があります。例えば、バリアフリーの設備や勤務時間の調整、相談員の配置などが、一般企業の障害者雇用より充実している点が特徴です。
一方で、単純作業を中心に行う職場が多く、スキルアップを望む人には物足りなく感じる場合があるでしょう。給与水準も全体的に低い傾向にあります。また、特例子会社の数自体が少ないため、希望に合った職場が見つからないケースも少なくありません。
障害者雇用に関する制度
障害者雇用に関連する制度には、以下のようなものがあります。
- 障害者雇用率制度
- 雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
- 障害者職業生活相談員の選任
- 障害者雇用納付金制度
それぞれの制度の概要について、以下で解説します。
障害者雇用率制度
障害者雇用率制度は、従業員数が一定数以上の企業は法定雇用率以上の割合で障害者を雇用しなければならないという制度です。具体的には、40.0人以上の従業員を雇用する企業が対象となります。
法定雇用率は、以下の通りです。(2024年4月時点)
- 民間企業:2.5%
- 独立行政法人等:2.8%
- 国、地方公共団体:2.8%
- 都道府県等の教育委員会:2.7%
例えば、従業員数が100人の民間企業なら、2.5人以上の障害者を雇用しなければなりません。カウント方法は「労働時間が週20時間以上30時間未満の身体障害者は0.5人」など、障害の種類や程度、週の労働時間によって細かく定められています。
また、2026年7月から民間企業の法定雇用率は2.7%へ引き上げられ、対象は37.5人以上の従業員を雇用する企業まで範囲拡大を予定しています。同様に地方公共団体や独立行政法人、教育委員会等の法定雇用率も同時期に引き上げが予定されており、今後さらに障害者雇用は進んでいくでしょう。
参考:
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
徳島県「とくしま障がい者雇用NAVI」
雇用の分野における障害者の差別禁止及び合理的配慮の提供義務
企業は、障害の有無によって機会の不平等が生じないようにしなければなりません。また、障害を持つことを理由にした賃金や福利厚生、その他の待遇における不当な差別は禁止されています。
また、障害の有無による機会の不平等などが生じないよう、募集や採用の際に障害の特性に応じた合理的配慮を行わなければなりません。具体的には、障害者からの申し出に基づく施設整備や援助者の配置などが挙げられます。
障害者職業生活相談員の選任
障害者生活相談員とは、障害を持つ人の職業生活全般について相談や指導を行う担当者のことです。常時5人以上の障害者を雇用する企業は、この障害者生活相談員を選任しなければなりません。
障害者生活相談員になれるのは、「障害者職業生活相談員認定講習を修了している」「大学卒業後に1年以上の障害者の職業生活に関する相談・指導の経験がある」など、一定の要件を満たす人です。
企業は障害者職業生活相談員を選任したら、所管のハローワークに速やかに届け出る必要があります。
障害者雇用納付金制度
障害者雇用納付金制度は、法定雇用率を達成している企業と未達成の企業の間での負担を公平化するための制度です。具体的な実施事項として、次の3つがあります。
- 法定雇用率が未達成かつ常用労働者が100人を超える企業から障害者雇用納付金を徴収する
- 上記の納付金から、法定雇用率を達成している企業に調整金・報奨金を支給する
- 障害者の雇用に際して環境整備などのために一時的に多額の費用が発生する場合、助成金を支給する
障害者雇用を実施している企業では、職場環境の整備や特別な雇用管理などを行うために、一定の経済的負担を負っています。これでは障害者雇用を積極的に進める企業ほど経済的負担が大きくなってしまうため、企業間の負担の公平を図るために障害者雇用納付金制度が設けられました。
障害者雇用で働いている人はどれくらいいる?
厚生労働省は、毎年6月1日時点の障害者雇用状況について調査を実施しています。令和5年の集計では民間企業における雇用障害者数が642,178人と、前年から28,220人増加しました。
障害の分類別の雇用者数は、以下の通りです。
| 分類 | 雇用者数 | 前年比 |
| 身体障害者 | 360,157.5人 | 0.7%増 |
| 知的障害者 | 151,722.5人 | 3.6%増 |
| 精神障害者 | 130,298.0人 | 18.7%増 |
全体の障害者雇用者数は過去最高の数値となっていて、特に精神障害者の雇用者数が大きく伸びていることがわかります。
障害者雇用の給料はどれくらい?
障害者雇用の給与の目安については、以下の厚生労働省の調査結果が参考になります。
| 区分 | 1ヶ月の平均賃金 | 週あたりの労働時間別の1ヶ月の平均賃金 | |||
| 30時間以上 | 20〜30時間未満 | 10〜20時間未満 | 10時間未満 | ||
| 身体障害者 | 23 万5,000円 | 26万8,000円 | 16万2,000円 | 10万7,000円 | 6万7,000円 |
| 知的障害者 | 13 万7,000円 | 15万7,000円 | 11万1,000円 | 7万9,000円 | 4万3,000円 |
| 精神障害者 | 14万9,000円 | 19万3,000円 | 12万1,000円 | 7万1,000円 | 1万6,000円 |
| 発達障害者 | 13万円 | 15万5,000円 | 10万7,000円 | 6万6,000円 | 2万1,000円 |
給与の目安をおおまかに知りたい場合は、1ヶ月の平均賃金をご覧ください。また、フルタイムで働く方や短時間労働で働く方など、労働時間ごとの目安を知りたい方は、週あたりの労働時間別の1ヶ月の平均賃金で確認できます。
障害者雇用の雇用期間に制限はある?
障害者雇用の雇用期間は一律に決まっておらず、企業ごとに異なります。
一般的には、正社員、契約社員、パートタイムなど雇用形態に応じて、雇用期間が設定されています。
一方、「障害者トライアルコース」を利用する場合は、原則として3ヶ月間の試行雇用となります。精神障害のある方については、さらに最大3ヶ月間の延長が可能です。この期間に適性があると判断された場合は本採用となりますが、必ずしも無期雇用に移行するとは限りません。
障害者雇用から一般雇用へは変更できない?
障害者雇用から一般雇用への切り替えは可能です。ただし、実際に変更できるかどうかは、企業の方針や制度によって異なります。
また、一般雇用へ移行した際に不都合が生じないかどうかも、事前に確認しておくことが大切です。例えば、障害への配慮の内容や、勤務時間・勤務形態に関する支援が変わる場合があります。
将来的に一般雇用を希望している場合は、応募の段階で、企業が一般雇用への変更に対応しているか、実績があるか、また労働条件がどのように変わるのかを確認しておきましょう。
障害者雇用で働くメリット
障害者雇用で働く代表的なメリットは、障害の特性に応じた配慮が受けられることです。障害者の採用を前提としていることから障害への理解がある職場が多く、勤務時間や通勤時間、業務内容や業務に使用するツールなど、さまざまな配慮が受けられるでしょう。
5人以上の障害者を雇用する企業には障害者職業生活相談員が選任されているので、困ったときに相談しやすいというメリットもあります。
障害者雇用で働く上での注意点
障害者雇用枠を利用できるのは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかの障害者手帳を取得している人です。障害者手帳を持っていない人は、まず手帳を取得しなければなりません。
障害者雇用は一般雇用と比較して求人数が限られる点にも注意が必要です。障害者雇用枠で就職したいと思っても、そもそも希望の条件に合う求人が見つからない可能性もあります。
障害者雇用を希望する人が利用できる支援機関やサービス
障害者雇用を希望する人は、以下の支援機関やサービスの利用がおすすめです。
- ハローワーク
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 障害者職業能力開発校
- 発達障害者支援センター
- 就労移行支援
- 自立訓練(生活訓練)
それぞれの支援機関・サービスの概要を以下で解説します。
ハローワーク
ハローワークは国が運営する機関で、仕事を探している人や人材を求めている企業に対してさまざまなサービスを無償で提供しています。全国のハローワークでは障害を持つ人のための専門窓口を設置していて、専門知識を持ったスタッフが担当となり丁寧に支援を行います。地域障害者職業センターなど各支援機関とも連携しながら、就職から職場への定着まで一貫した支援を受けられるのが特徴です。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、ハローワークと連携しながら障害を持つ人に対して専門的な職業リハビリテーションを提供する機関です。利用者一人ひとりの特性やニーズに応じて、職業能力の評価やセンター内での作業体験、コミュニケーション能力向上のためのサポートなど、さまざまな支援を実施しています。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害を持つ人の就業と生活を一体的に支援する機関です。利用者に対して就業支援担当者と生活支援担当者がそれぞれ付き、自立・安定した職業生活を実現できるよう支援を行います。就職だけでなく、生活習慣の形成や健康管理、金銭管理などについても相談できるのが特徴です。
障害者職業能力開発校
障害者職業能力開発校は、障害のある人が自立して働く力を身につけるために、職業訓練を行っている専門の学校です。国や都道府県が運営しており、費用の負担も少ないため、経済的にも利用しやすい制度となっています。
障害者職業能力開発校では、障害の特性に合わせた訓練を受けられます。内容は学校によって異なりますが、軽作業や清掃などの作業系のほか、事務補助やパソコンなどの事務系、さらにプログラムや機械設計などのIT・設計系の訓練などが用意されています。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害*のある方とその家族の暮らしを支えるために利用できる福祉サービスです。各都道府県や政令指定都市が直接運営している場合と、社会福祉法人やNPO法人などに委託している場合があります。
支援の対象は幅広く、生活や仕事、学びに関する悩みまで対応しています。必要に応じて、医療機関や福祉施設、教育機関などの関係機関へのつなぎ役も担います。仕事や学校生活で困りごとがある方や、診断を受けたばかりで今後の進め方に不安を感じている方などにとって、最初に相談する窓口としても適した支援機関です。
就労移行支援
就労移行支援は障害を持つ人が就労を希望する際に利用できる障害福祉サービスで、全国にある就労移行支援事業所に通って職業訓練や就活支援が受けられます。これまでの経験や障害特性に応じて一人ひとりに合った支援計画を作成し、一般企業への就職を目指します。
就労移行支援は、就職までの支援に加えて就職後の定着支援が受けられるのが特徴です。必要に応じて本人と就職先の仲介役となり、困りごとを解消して長く働けるようサポートを行います。
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)は、自律的な生活を送るために必要な生活習慣やスキルを身につけるための福祉サービスです。生活リズムの改善、感情や睡眠のコントロール、人間関係の築き方の練習など、日常生活に役立つ内容が中心です。また、金銭管理や片づけ、予定の立て方など、暮らしに密着した実践的な訓練も行われます。
このサービスは、すぐに働くことに不安がある人や、まずは生活を整えることから始めたい人におすすめです。例えば、就労移行支援や障害者職業能力開発校に進む前の準備として、自立訓練(生活訓練)を活用できます。
障害者雇用を検討中の方はKaienにご相談ください
障害者雇用は、障害を持つ人を対象とした雇用制度です。一定規模以上の企業は、法律で定められた割合以上の障害者を雇用するよう義務付けられています。障害者の雇用を前提としているため、障害者雇用枠で就職すると合理的配慮を受けやすいのがメリットです。
ハローワークの障害者関連窓口や、就労移行支援をはじめ就労に関する障害福祉サービスもあるため、障害者雇用を利用したい人はこれらの支援機関やサービスを活用しましょう。
障害者雇用を検討中の方は、ぜひKaienにご相談ください。特性を活かして働きたい人を応援するKaienでは、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)などを実施しています。ご利用説明会・見学会も開催しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修者コメント
障害者雇用における「合理的配慮」について、クリニック診療でも大きなテーマになってきたので、コメントしたいと思います。
合理的配慮とは、過度な負担にならない範囲で、本人が能力を発揮できるようにする職場上の工夫のことです。そして、合理的配慮の提供は、日本では「障害者差別解消法」および「障害者雇用促進法」に基づいて、事業主に提供が義務づけられています。ですので、労働者(被雇用者)は雇用者に合理的配慮を求める権利があります。
では、具体的にどのような配慮を求めれば良いでしょうか?まずは自分の強みと弱みを見返してみましょう。おそらく就労移行支援事業所やクリニックで何回か、そのようなフィードバックを受けたことがあるでしょう。
例えば、あなたは集中力に波があるため、静かな環境で働き、1日2回は10分ほどの休憩を取りたいという希望が出ることを考えます。ご自身で上司や人事に伝えることも可能ですが、ジョブコーチに頼んで合理的配慮の内容を交渉してもらうのも一手です。また、クリニックの主治医に医学的側面から合理的配慮を求めるのも良いでしょう。
また、いちど決めた合理的配慮の内容は、定期的に見直すことをお勧めします。仕事の内容が異動などで変化することがあるため、メンターやジョブコーチに都度、配慮の内容を話し合えるとより働きやすくなると思います。

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。