障害のある方の中には障害者雇用での就職、転職を考えている方もいるでしょう。しかし、障害者雇用の給料はどのくらいなのか、一般雇用で働くよりも低いのか、給料が少ない理由は何かなど、気になる点も多いはずです。
本記事では、障害者雇用の給与平均額や、障害者雇用の賃金が安いといわれる理由、収入を上げる方法、給料だけでは足りない際に活用できる制度などを詳しく解説します。また、障害者雇用を検討する際におすすめの支援機関も紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
目次
障害者雇用とは

障害者雇用とは、一定数の従業員を雇用する民間企業や自治体に定められた障害者を対象とする雇用枠のことです。障害の特性に応じた合理的配慮を得て、自身の希望や能力、適性を十分に活かして働き、活躍できる社会を目指す目的があります。
従業員数が40.0人以上の民間企業は障害者雇用率制度により、雇用する労働者の2.5%に当たる障害者の雇用が義務づけられています(2025年5月時点)。
厚生労働省が公表した「令和6年の障害者雇用状況」の集計結果によると、民間企業の雇用障害者数は約67.7万人、実雇用率は2.41%です。共に過去最高を更新しており、公的機関や独立行政法人においても対前年の障害者雇用率を上回る結果となっています。
一般雇用との違い
障害のある方が対象となる障害者雇用に対し、一般雇用は企業の募集条件を満たす人すべてを対象とします。障害のある方は障害者雇用に加え、募集条件を満たしていれば一般雇用にも応募可能です。
ただし、一般雇用は障害者の採用を前提としていないため、職場によっては合理的配慮を十分に受けにくい場合があります。一方、障害者雇用では、障害者雇用促進法により雇用環境を整えるための助成金や制度などが手厚い傾向にあるため働きやすく、就職後の定着率も一般雇用より高いとされています。
もちろん、一般雇用でも合理的配慮が求められますが、障害者雇用のような手厚い配慮は受けられない可能性もあるため、このような点も踏まえて雇用形態を決める必要があるでしょう。
特例子会社の雇用との違い
特例子会社とは障害者雇用の1つの形態であり、障害がある方の雇用機会を増やすことを目的につくられた会社です。障害の種類や程度に左右されずに幅広く利用でき、働きやすい環境や支援制度が整えられているケースが多くあります。
特例子会社では、多くが障害の特性に合わせた配慮を受けられ、柔軟な働き方が認められています。一般雇用では雇用が難しかった方や、より自分にとって無理のない環境での雇用を希望する方にとって、特例子会社は障害者雇用の1つの選択肢といえるでしょう。
障害者雇用のメリット・デメリット
障害者雇用の大きなメリットは、障害の特性に応じた配慮が受けられることです。障害者雇用では障害者の雇用を前提としているため、障害に理解のある環境や支援制度が整えられ、柔軟な働き方が叶います。
また、5人以上の障害者を雇用する企業には障害者職業生活相談員が選任されています。障害者職業生活相談員のいる企業で働く場合は、業務での困りごとが生じた際などに相談しやすいのもメリットでしょう。
ただしデメリットとして、障害者雇用はそもそも求人数が少なく、希望に合う職種が見つからなかったり、応募条件に合わなかったりするケースが多いです。加えて、業務の内容によっては一般雇用よりも給料が安いこともあるため、これまで一般雇用で働いていた方が障害を理由に障害者雇用で転職を希望する場合には、給料が減る可能性も考えられます。

障害種別ごとの障害者雇用の平均給料
厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、障害者雇用の給与の目安は以下のとおりです。労働時間に合わせて、参考にしてください。
| 区分 | 1ヶ月の平均賃金 | 週あたりの労働時間別の1ヶ月の平均賃金 | |||
| 30時間以上 | 20〜30時間未満 | 10〜20時間未満 | 10時間未満 | ||
| 身体障害者 | 23 万5,000円 | 26万8,000円 | 16万2,000円 | 10万7,000円 | 6万7,000円 |
| 知的障害者 | 13 万7,000円 | 15万7,000円 | 11万1,000円 | 7万9,000円 | 4万3,000円 |
| 精神障害者 | 14万9,000円 | 19万3,000円 | 12万1,000円 | 7万1,000円 | 1万6,000円 |
| 発達障害者 | 13万円 | 15万5,000円 | 10万7,000円 | 6万6,000円 | 2万1,000円 |
障害者雇用の職種別給与平均と相場
Kaienが運営する障害者雇用求人サイト「マイナーリーグ」に掲載された首都圏を中心とする求人を基に、障害者雇用の平均給与月額と相場を職種別に紹介します。
まず、平均給与月額が20万円以上の職種は以下の5つです。
- 一般事務:約21.7万円
- 専門事務:約26.4万円
- IT系:約26.0万円
- クリエイティブ系:約22.7万円
- その他専門職:約23.0万円
例えば上記の一般事務の場合、業種別の給与相場は以下のとおりです。
- 総務・庶務:20.3万円
- 一般事務:23.0万円
- 営業事務:23.2万円
- その他事務:20.3万円
次に、平均給与月額が15万円以上の職種は以下の2つです。
- 軽作業:約16.4万円
- 接客・販売など:約15.3万円
同じ障害者雇用でも約15~26万円と、職種によって平均給与月額には幅があります。
障害者雇用の給料が安い理由

障害があるからといって、他の社員より給料を低くすることは法律で禁じられています。
しかし、障害者雇用の方とそうでない方とでは、可能な業務内容や仕事の成果に違いが出るケースもあるでしょう。そのような場合に、給料を安く設定せざるを得ない理由が生じることは考えられます。具体的にどのような理由が挙げられるか見ていきましょう。
正社員の割合が少ない
障害者雇用の給料が安くなりがちな理由として、そもそも正社員雇用の割合が少ないことが挙げられます。障害者雇用は全体的に離職率が高い傾向があり、採用時から正社員として雇用する企業は多くありません。契約社員から3~5年の雇用期間を経て正社員に登用する企業が多いです。
さらに障害の特性に応じて雇用時間や出勤日数が調整され、こうした配慮により全体的な雇用時間が短くなったり、出勤日数が少なくなったりすることも、給料が安くなる原因と言われています。
実際のところ、正社員の比率はどれくらいなのでしょうか。厚生労働省「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」のデータを基にまとめたものが以下の表です。
| 無期契約の正社員 | 有期契約の正社員 | |
| 身体障害者 | 53.2% | 6.1% |
| 知的障害者 | 17.3% | 3.0% |
| 精神障害者 | 29.5% | 3.2% |
| 発達障害者 | 35.3% | 1.3% |
仕事内容に制限がある
障害者雇用の仕事内容は、主に「事務補助」「専門職」「軽作業」の3つに分けられます。3つのうち1つを行うケースもあれば、どれか2つ、3つの業務が組み合わされる場合もあります。
障害者雇用の場合、同じような業務をルーティンワークとして長期的に行うことを前提に、仕事内容が限定されていることが多いです。苦手な仕事を避けてもらえる配慮がなされていますが、一般雇用のような大きな昇給やキャリアアップは難しいかもしれません。
勤務時間が短い傾向にある
障害者雇用で働く方は、勤務時間が短い傾向があります。週あたりの労働時間別に雇用者数の割合をまとめたものが以下の表です。
| 区分 | 週所定労働時間別雇用者数の割合 | |||
| 30時間以上 | 20〜30時間未満 | 10〜20時間未満 | 10時間未満 | |
| 身体障害者 | 75.1% | 15.6% | 7.2% | 1.2% |
| 知的障害者 | 64.2% | 29.6% | 3.2% | 2.1% |
| 精神障害者 | 56.2% | 29.3% | 8.4% | 2.7% |
| 発達障害者 | 60.7% | 30.0% | 4.8% | 3.9% |
このように、障害者雇用ではフルタイム(30時間以上)以外の時短勤務を選ぶ方が一定数おり、特に精神障害者と発達障害者で割合が高い傾向があります。時短勤務は心身に負担が少ない点がメリットですが、フルタイムの方に比べると労働時間が減る分、給料が下がります。
障害者雇用の給料は今後上がっていく?
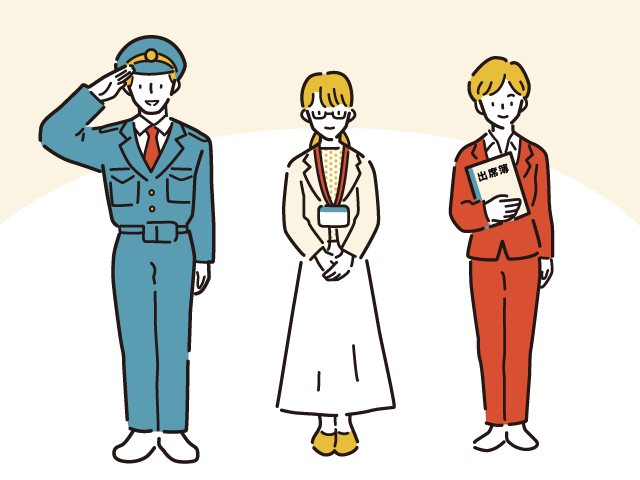
企業に義務づけられている障害者雇用率は、今後、段階的に引き上げられる見通しです。しかし、都市部ではすでに障害者を雇用したくても人材が見つからない企業が増えており、さらに雇用率が上がると「雇いたくても雇えない」という状況が広がる可能性があります。
このため、企業は法定雇用率を達成するために給与条件を改善するなど、雇用環境を整える動きが強まることが予想されます。これにより、障害者雇用の給料が上がる可能性が高まっているのです。
また、すでに障害者雇用で働いている方に対しても、離職を防ぐために、給料を引き上げる企業が増える可能性があります。
発達障害でも障害者雇用は可能?
障害者雇用の求人に応募するには、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)が必要です。発達障害*の方の場合、発達障害専用の手帳はありませんが、発達障害の診断を受けている方で知的に遅れのある方は療育手帳、知的に遅れのない方は精神障害者保健福祉手帳を取得できます。
ただし、発達障害の診断基準をすべて満たさず、発達障害と診断されていないグレーゾーンの方は障害者手帳の取得対象外となるため、障害者雇用には応募できません。
障害者雇用の給料だけで足りない場合はどうすればよい?
障害者雇用の給料だけでは生活が厳しい場合、障害のある方や生活が困難な方を支援する制度の活用を検討してみましょう。ここでは、働きながらでも利用できる障害者年金、生活保護、グループホームの3つの制度を紹介します。
障害者年金を受給する
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に支給される年金制度です。障害年金は現役世代でも受給でき、国民年金加入者向けの「障害基礎年金」と厚生年金加入者向けの「障害厚生年金」の2種類があります。
障害年金は、障害者雇用での賃金が低く生活が困難な場合に、生活を補完する収入源として活用できます。2025年度(令和7年度)の障害基礎年金の支給額は、以下のとおりです。
- 1級:年額103万9,625 円(月額 8万6,635 円)+ 子の加算
- 2級:年額83万1,700 円(月額 6万9,308 円)+ 子の加算
一方、障害厚生年金の支給額は、加入者の給料や加入期間によって変わりますが、障害基礎年金より多くなる傾向があります。
障害年金がもらえる3つの条件とは?受給金額や申請方法、支給までの流れを解説
生活保護を利用する
生活保護とは、生活に困窮している世帯に対して、国が最低限度の生活を保障する制度です。憲法で定められた権利であり、生活費や家賃、医療費など必要な費用が支給されます。
生活保護は、収入が最低生活費を下回る場合、その不足分を補う形で支給されます。そのため、就労している場合でも、収入が生活保護基準額を下回るときは、その差額が支給される仕組みです。
就労収入がある場合、その収入の一部が収入認定額として生活保護費から差し引かれるため、収入が増えるほど支給額は減少します。また、先述した障害者年金の受給額も収入として扱われる点に注意が必要です。
グループホームを活用する
グループホームとは、障害のある方が地域において少人数で共同生活を送る住まいです。主に、親元を離れて生活したい場合や、入所施設から地域生活に移行したい場合に利用されています。
グループホームは、生活費を抑えながら自立した生活を送りたい方にとって有力な選択肢です。家賃は地域によって異なりますが、一般の賃貸物件よりも安価に設定されていることが多く、国の「特定障害者特別給付」や市区町村の補助を受けることで、さらに負担を軽減できます。
また、食費や光熱費も入居者同士で分担する形となるため、一般的な一人暮らしと比べても生活費を抑えやすい仕組みです。
障害があっても給料をアップさせる方法
障害者雇用の給料は、障害の特性に応じた業務内容をはじめ、雇用時間や勤務日数の調整などがあることから、障害者雇用でない場合に比べ低くなるケースも少なくありません。
ただし、障害があっても給料アップを目指すことは可能です。ここでは具体的な方法を紹介します。
資格やスキルを習得する
障害者雇用では事務職、専門職、軽作業を主としたルーティンワークが多く、大幅な給料アップの機会は少ないといわれています。しかし、資格取得やスキルの習得によって専門的な業務が可能になると、給料アップにつながりやすいでしょう。
ただし、どのような資格やスキルを取るべきなのかわからない状態でやみくもに手を出すのはおすすめできません。まずはしっかりと実務能力や勤怠を安定させることを重視したうえで、業務にプラスになり自分の技量に合う資格やスキルを無理のないペースで取得するのが望ましいでしょう。
正社員登用制度を活用
障害者雇用は多くが契約社員からのスタートで、採用時から正社員として雇用する企業に出会えるのは稀なケースです。しかし、始めから正社員雇用は行っていなくても、入社後に数年の期間を経て正社員登用を行う企業は増えてきています。
正社員になれば給与アップや収入の安定が見込めるため、正社員登用制度がある企業かどうかも併せて就職先を選ぶとよいでしょう。なお、すべての企業が正社員登用制度を設けているとは限らないため、過去の正社員登用実績の有無も調べておくことをおすすめします。
キャリアアップの転職を検討
近年はキャリアアップのために障害者雇用での転職をする方も増えてきています。一般雇用よりも、障害者雇用は違う業種・職種へのキャリアチェンジがしやすいのが特徴です。
例えば、軽作業の職種に就いていた人が経験のない事務職に転職するのは、一般雇用ではなかなかハードルが高いでしょう。しかし、障害者雇用の場合は年齢や経験に関係なく、一般雇用よりは比較的容易に転職が可能とされています。
ただし、障害者雇用では実習を通した選考が多いため、面接のみで内定をもらうのは難しいかもしれません。在職者が転職活動をする際は、実習の時間を確保できない可能性がある点にも注意が必要です。
支援機関やサービスを利用する
障害者雇用での就職や、キャリアアップのための転職を希望する方は、以下の支援機関やサービスを利用するのもよい方法です。
地域障害者職業センター
障害の特性やニーズに応じて、専門的な職業リハビリテーションを行う機関です。ハローワークと連携しながら、さまざまな支援を実施しています。
障害者就業・生活支援センター
障害のある利用者に対し、就業面・生活面のそれぞれに支援担当者がつき、職業や生活の自立、安定を目指した支援を行います。
ハローワーク
障害の有無に関わらず、求職者と人材を募集する企業との間にたち、仕事の紹介や入職のサポートなどさまざまな支援を行う機関です。障害者専用の窓口を設置しているところもあり、専門知識を持つスタッフの手厚いサポートが受けられます。
就労移行支援
職業訓練や就活支援、就職後の定着まで就労に関するトータルサポートが受けられる福祉サービスです。障害のある方を対象に一般企業への就職を目指し、特性やこれまでの経験などを踏まえ一人ひとりに合った支援を行います。
給料アップを目指すならKaienの就労移行支援がおすすめ

就労移行支援サービスを行うKaienでは、職業訓練や就職活動、就職後の定着まで一貫した支援が受けられるほか、給与面やキャリアアップに向けたサポートも幅広く行っています。
Kaienでは100職種を超える多種多様な職業訓練や、50以上のスキル向上を目指す講座が用意されています。就職に向けた支援はもちろん、自分に合う職業を見つけ正社員登用を目指したい方、給料アップにつながる資格取得やスキルを身につけたい方を手厚くサポートできるのもKaienの強みです。
さらに担当カウンセラーと二人三脚で、200以上の障害に理解のある企業の求人の中から、あなたの特性や能力を活かせる職場を見つけられます。求人は他事業所にはない業種や独自求人も豊富です。
Kaienを利用された方の就職率は約86%、1年後の離職率はわずか9%に留まっており、3人に1人が20万円以上の給与を得ています。
就職や転職を検討している方はKaienにご相談ください
障害者雇用を理由に安い給与で雇用するのは法律で禁止されています。しかし、障害の特性に応じた雇用形態や雇用時間、勤務日数の調整などにより、給与設定が低くならざるを得ないケースはあります。
Kaienの就労移行支援なら、就職活動から定着支援までのトータルサポートをはじめ、給料アップを目指すための資格取得やスキルの向上まで手厚い支援が可能です。障害者雇用を希望して自身の特性や強みを活かせる仕事に就きたい方、キャリアアップなどの転職を考えている方は、ぜひKaienにご相談ください。
また、Kaienでは、就職活動を始める前に生活の基盤を整えたいという方に向けて、「自立訓練(生活訓練)」を提供しています。生活リズムの整え方や家事の方法、感情コントロールなど、日常や仕事で欠かせないスキルを学べます。金銭管理の訓練もあるため、給料を計画的に使えない不安がある方もご活用ください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。


