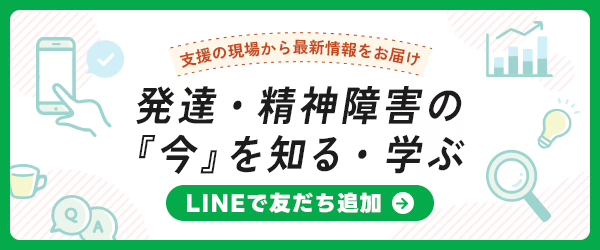「リワークは復職のために意味があるの?」と、疑問に思っていませんか?
メンタル不調で休職すると、職場から「リワークプログラムを受けるように」と言われる場合もあるでしょう。
しかし、本当に効果があるのか疑問に思ったり、あまり気乗りしなかったりする方もいるかもしれません。
この記事では、リワークの役割と目的、リワークを意味ないと感じる理由・対処法、リワークによる効果を得るためのポイントについて詳しく解説します。
目次
リワークは意味がない?リワークの役割や支援の目的とは
「リワークに行っても意味がない」と思う方もいるかもしれませんが、リワークを効果的に利用するには、リワークの役割や支援の目的を理解することが大切です。
リワーク支援では、復職に向けたプログラムである「リワークプログラム」が用意されています。
リワークプログラムは、ただやらされているのではなく「何のためにやっているのか」を意識すると、リワーク支援の価値を再認識できるでしょう。
リワークの役割
リワークとは、うつ病や適応障害などのメンタル不調により休職した方が、職場復帰できるよう支援する制度・仕組みです。リワークは「return to work」の略で「職場復帰そのもの」を意味しますが、日本では「リワーク支援」「リワークプログラム」といった支援サービス全体を指す言葉として広く使われています。
リワークを提供している機関は、医療機関(精神科・心療内科など)やリワーク専門の支援施設、就労移行支援(福祉サービス)などです。これらの機関は、主治医や産業医、職場と連携しながら、復職に向けた段階的な準備を支援し、さらに復職後のサポートを行っています。
リワークは、ストレス社会と呼ばれる現代において重要な役割を果たしています。厚生労働省の2022年の調査によると、連続1か月以上の休職者がいた事業所の割合は10.6%、そのうち退職者がいた事業所の割合は5.9%でした。また、メンタルヘルス不調による連続1か月以上の休業者の割合は0.6%にのぼります。社会人であれば、誰もが休職の可能性があり、リワークを利用する可能性もあるといえるでしょう。
参考:厚生労働省「令和4年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況」
リワークの意味や目的
リワークを利用する最大の目的は、再休職を防ぐことです。精神疾患は再発率が高く、特に復職直後はストレスの影響を受けやすいため、以下のようなリワークプログラムを通じて、再休職のリスクの軽減に取り組みます。
- 生活リズムの構築・体調管理
- 基礎体力・集中力・持続力の向上
- コミュニケーションスキルの習得
- ストレス対処法の習得・キャリアの振り返り
これらのプログラムは、再休職の予防に加えて、自己理解やセルフケア能力の向上、復職に向けた段階的な準備、安定して働き続けるためのスキル習得にもつながります。
実際、ある研究によると、リワークを受けた方は復職後の就労継続率が高いという結果が出ています(約3年後時点の比較)。
- リワークを利用した方(復職後フォローあり):90%
- リワークを利用した方(復職後フォローなし):70%
- リワークを利用しなかった方:20%
リワークの効果を疑う方もいるかもしれませんが、統計的には高い効果が示されています。
参考:厚生労働省 地域におけるうつ病対策検討会「うつ対応マニュアル-保健医療従事者のために-」
参考:特集「第19回日本産業精神保健学会」2012,Vol.20,No.4
関連記事:リワークプログラムとは?種類や対象者、利用の流れやメリットを解説
リワークが意味ない・しんどいと感じる6つの理由
リワーク支援が「意味ない」「しんどい」と感じる理由として、以下の6つが挙げられます。
- 生活リズムが乱れている
- 体力がない
- 周囲とのコミュニケーションが疲れる
- プログラムの内容が合っていない
- リワーク施設の環境やスタッフが厳しい
- 復職許可が下りない
リワークプログラムの内容や難易度によっては「自分に合わない」と感じる場合もあるかもしれません。
また、休職によって体力が低下していたり、生活リズムが崩れていたりする場合も、リワークがしんどいと感じる場合があります。
生活リズムが乱れている
生活リズムが乱れていると、リワークをしんどいと感じやすいでしょう。
リワークの目的の一つとして「生活リズムを整えること」が挙げられます。
休職中にリワークに通う方のなかには、生活リズムが乱れている方もいるため、しんどいと感じる場合もあります。
休職前は「決まった時間に起きて出勤退勤し、決まった時間に寝る」といった生活リズムができていたかもしれません。
しかし、休職中はメンタル不調の影響で睡眠時間が不規則になり、生活リズムが崩れてしまう方もいます。
リワークに行き始めた頃は、決まった時刻に起床・食事・就寝することを目標にしましょう。
生活リズムが整ってきたら個人プログラムに取り組み、体調を崩さずに継続できたら、少しずつ集団プログラムにも参加することをおすすめします。
休職中に生活リズムが乱れてしまうのは、珍しいことではありません。
定期的にリワークに通い、自宅療養によって乱れた生活リズムを立て直しましょう。
体力がない
体力がない方も、リワークを苦痛に感じやすい傾向にあります。
休職中は体を休めている時が多いため、体力が落ちている方が多いためです。
特にリワークに通い始めたばかりで、体力があまりない状態にあると「リワークに通っても意味がないのでは?」と思うかもしれません。
自宅療養で体力が落ちると、休職前は当たり前にできていたことも、想像以上にしんどいと感じるでしょう。
通所当初は、電車やバスで施設に通ったり、半日プログラムに参加したりするだけでも、疲れてしまいます。
しかし、リワークを始めた頃は誰もがしんどいと感じるため、少しずつ取り組むことが重要です。
「最初は週2日から」など、できる範囲から始めても問題ありません。
リワークは、疲労やストレスとの付き合い方を学ぶために実施されます。
「体力がないからリワークに行く意味がない」と思うかもしれませんが、まずは通所に慣れていきましょう。
参考:高齢障害求職者雇用支援機構「職場復帰支援についてよくいただくご質問への回答」p1
周囲とのコミュニケーションが疲れる
周囲とのコミュニケーションも、リワークがしんどいと感じる原因の一つです。
休職中は人との関わりが少ないため、コミュニケーションを取ると精神的に疲れてしまう方もいます。
リワークに通い始めると、他の参加者や支援スタッフとコミュニケーションを取る機会が増えるでしょう。
さまざまな人と関わるため、人によっては「この人とは合わないな」と感じるかもしれません。
また、リワークを利用する場合、支援スタッフとの相性も重要です。
リワーク参加者と支援スタッフの考え方に相違があると、効果を感じられない場合もあるためです。
「リワークに苦手な人がいる」「居心地がよくない」と感じる場合は、次の対処法を取ってみましょう。
- 信頼できる支援スタッフに相談する
- リワーク施設を変更する
参加者や支援スタッフとの相性を見極めるには、体験利用がおすすめです。
人間関係が原因でリワークがしんどいと感じる前に、ぜひ体験プログラムにご参加ください。
プログラムの内容が合っていない
リワークプログラムは、基本的に一人ひとりの状態に合わせて作られますが、実際には自分の体調や状況と合わない内容に参加してしまう場合もあります。その場合、疲労がたまったり、心に負担がかかったりして、「リワークは意味がないのでは?」と感じることもあるでしょう。
たとえば、まだ体力や集中力が十分に回復していない段階で長時間の活動が続いたり、人とのやり取りが苦手なのにグループワークが多かったりすると、疲れやストレスを強く感じやすくなります。リワークは不調が回復しきっていない段階で参加する場合が多いため、自分の調子や得意・苦手がまだよくわからず、こうしたミスマッチが起こる可能性があります。
とはいえ、プログラムが合うかどうかは、実際にやってみないとわからない部分もあるかもしれません。もし「合わない」と感じた時には、スタッフに相談してプログラムの調整をしてもらうのがよいでしょう。
リワーク施設の環境やスタッフが厳しい
リワーク施設の環境やスタッフが厳しい場合も、しんどいと感じやすいです。
施設によっては「週に〇日休んだら退所」といった、厳しいルールを設けているところもあります。
ルールを破ってはいけないプレッシャーから、リワークをしんどいと思う方もいるでしょう。
また、プログラムのレベルが合ってないのが原因で「厳しい」と感じるケースもあります。
「リワーク施設が厳しすぎる」と感じる場合は、プログラムを中断して別の施設に変更してもよいでしょう。
復職を目指してリワークに通っているにもかかわらず、リワークによって精神的に辛い思いをして、調子を崩す事態は避けるべきです。
リワーク支援はさまざまな施設で行われていますが、必ずしも自分に合うとは限りません。厳しい環境や支援スタッフが合う方もいれば、できるだけ優しく支援して欲しい方もいます。
リワークに参加する前に体験利用をしてみて、自分に合ったリワーク施設を選びましょう。
復職許可が下りない
主治医から復職許可が下りない場合も、リワークをしんどいと感じるかもしれません。
リワーク参加者の多くは復職を目標にしているため、許可が下りない状況が続くと「リワークに行く意味がない」と考える方もいるでしょう。
人によっては「復職許可が下りない自分はダメな存在なんだ」と、ネガティブな気持ちになり、症状が悪化するケースもあります。
復職許可は、主治医や支援スタッフなどの第三者が客観的に評価するものです。
自分では「もう復職してもいいだろう」と感じていても、条件がクリアできていないと、復職許可が下りない場合もあります。
具体的には、以下の条件がクリアできていないケースが考えられます。
- 通所が安定していない
- 集中力が回復していない
- 生活リズムが乱れている
- 体調が安定していない
復職可能な条件については、主治医や支援スタッフにご確認ください。
自分の課題を確認したら、関連するプログラムを重点的に取り組んでみましょう。
リワークのメリット
リワークには「意味がない」と感じる意見もありますが、実際には自己理解を深めたり、ストレスへの対処法を身につけたりと、多くのメリットがあります。これらを理解したうえで参加すれば、モチベーションも保ちやすくなるでしょう。ここでは、リワークの主なメリットを4つに分けて紹介します。
自己理解を深められる
リワークでは、専門スタッフのサポートを受けながら、自分の体調や考え方のくせ、ストレスを感じやすい場面を振り返り自己理解を深める時間が設けられています。
たとえば、自分史を書いたり、心理検査を受けたり、面談の中で「どんな場面でつらさを感じたか」「休職前はどんな働き方をしていたか」などを振り返ると「自分はこういう時に疲れやすい」「人との距離感を取るのが苦手だった」といった特徴がみえてくるでしょう。
自己理解が進めば、日々の働き方や生活が少しずつ楽になります。強みや苦手なことを理解すると無理をせずにすむよう日頃から工夫でき、ストレスもためにくくなります。
また、不調のサインに早めに気づき、対処しやすくなるのもメリットです。さらに、自分について言葉で説明できるようになると、同僚や家族などに助けや配慮を求めやすくなるでしょう。
ストレスへの対処法が身につく
リワークでは、実践的なプログラムを通してストレスへの向き合い方を学びます。学べるストレス対処法はプログラムによって異なりますが、具体例をいくつか紹介します。
- 認知行動療法(CBT)
ものの見方や考え方のくせを見直し、ストレスを感じやすい場面や思考のパターンを整理します。
- アサーション
自分の気持ちや考えを、相手を傷つけず、自分も無理をしすぎずに伝える方法を学びます。
- アンガーマネジメント
怒りの感情がわいた時に、すぐに爆発させず、上手に扱うための方法を身につけます。
このようなリワークプログラムを通じて、少しずつストレスと上手に付き合う感覚が育っていきます。たとえば、ストレスを感じやすい状況から距離を取ったり、不安や怒りをため込む前にリフレッシュする習慣をつけたりしやすくなるでしょう。
専門家のサポートを受けて復職準備ができる
リワークでは、専門家のサポートを受けながら、段階的に復職準備ができる点もメリットです。このメリットは、医療職や心理職が常駐する医療機関(精神科・心療内科など)や就労移行支援(福祉サービス)でのリワークで特に感じやすいでしょう。
医療機関でのリワークは、リワークデイケアや復職支援デイケアなどと呼ばれ、医師、看護師、作業療法士などの専門職がチームで関わります。病状の安定や再発予防も目的に含まれ、治療と復職支援を同時に受けられるのがメリットです。
また、就労移行支援でのリワークは、障害福祉サービスとして提供されているため、精神障害や発達障害の専門知識を持った支援員やカウンセラーが常駐しています。障害の特性に合った手厚いサポートを受けられます。
一方、企業内でのリワーク(職場リワーク)は、社内の人事部門や産業医などが主導することが多く、専門職による継続的な支援が受けにくいケースもある点に注意が必要です。
職場復帰後のフォローアップが受けられる
リワークでは、復職後も定期的な面談が用意されている場合があります。面談では「仕事が負担になっていないか」「生活リズムは安定しているか」などを確認し、必要な助言を受けられます。
また、施設によっては、復職後にしばらく通所を続けたり、電話やオンライン面談を受けることも可能です。相談内容によっては、リワーク機関のスタッフが復職先の人事担当や産業医と連携して、環境や業務量の調整を提案するケースもあります。
こうした支援を受けられることで、不調を感じた際に、早めに対応しやすくなるでしょう。再休職のリスクを減らしながら、安心して働き続ける土台を整えられます。復職はゴールではなく再スタートであるため、フォローアップが受けられる点は、大きなメリットです。
リワークが意味ないしんどいと感じる時の対処法
リワークが「意味ない」「しんどい」と感じる時の対処法として、以下の3つが挙げられます。
- 支援スタッフに気持ちを伝えて相談する
- 一時的にリワークを休む
- リワーク施設の変更を検討する
リワーク開始当初や、なかなか復職できない時は、リワーク施設への通所がしんどい時もあります。
一人で悩みを抱え込んだり、自己判断で休んだりしないためには、上記の対処法をお試しください。
それぞれの対処法について、以下より詳しく見てみましょう。
支援スタッフに気持ちを伝えて相談する
リワークの効果を高めるには、リワークの目的を理解したうえで、支援スタッフに頼る姿勢が大切です。
リワークを「意味ない」と感じている方の中には、「目的がわからないまま参加している」「プログラムが合わないのに我慢している」といった状況に陥っている場合があります。そうしたまま無理を続けると、体力や気力がすり減り、リワーク自体がつらい体験になりかねません。
そうならないためにも、つらさや不安を抱えたままにせず、支援スタッフに今の気持ちや状況を伝えてみてください。たとえば、「どんな働き方が向いているのかわからない」といった悩みを共有すれば、目標の立て直しや今後の進め方を一緒に考えてもらえます。
こうした対話を重ねることで、リワークの目的や各プログラムの意図も少しずつみえてきます。目的意識を持って取り組めば、多くの気づきや成長につながるでしょう。
一時的にリワークを休む
体調不良やメンタル不調でリワークを休むのは、決して悪いことではありません。
リワークへの通所が苦痛に感じる場合、一時的に休んでみましょう。
リワークに参加すると、人との関わりの中で精神的な疲労を感じたり、気持ちが焦って調子を崩してしまったりする方もいます。
無理してリワークを続けるよりかは、プログラムを一時中断し、体と心を休養させる方が大事です。
ただし、リワークを休む際には、必ず支援スタッフに相談しましょう。
リワークを無断欠席してしまうと、次の利用日に通所しにくくなり、復職が遠のいてしまうケースもあるためです。
リワークを休むと「なぜ自分は体調不良になったのか」を振り返る機会になります。
再びリワークに通えるようになったら、体調不良やストレスの原因について、支援スタッフと一緒に考えてみましょう。
リワーク施設の変更を検討する
人間関係のトラブルや、プログラム内容が自分に合わないと感じている場合は、リワーク施設を変更するのも一つの方法です。
ただし、まずは支援スタッフに悩みを相談して、解決方法を模索してみましょう。
リワーク施設を変えると、今抱えている問題が解消され、リワークプログラムに集中して取り組める場合もあります。
リワークプログラムの実施機関・特徴は、以下のとおりです。
| 実施機関 | プログラムの特徴 |
| 医療機関 | 自己理解やコミュニケーションスキル向上を目的としたプログラムが豊富 |
| 地域障害者職業センター | 本人・企業・主治医の3者が連携して支援が行われる |
| 企業 | 実際の職場でリワーク支援を受けられる |
| 就労移行支援 | 復職に必要な知識やスキルの習得を目的とした、独自のプログラムが受けられる |
各機関の特徴を理解し、自分に合ったリワーク施設を選びましょう。
リワークが意味ないと感じている方はKaienのリワーク支援も検討してみて
リワークの効果に疑問を持つ方もいますが、実際には復職や再発予防に役立ちます。自分に合ったリワークプログラムを選べば、自己理解が深まり、ストレスへの対処力も身につくなど、多くの効果を得られるでしょう。
Kaienでは、精神障害や発達障害のある方を対象に、福祉サービスとしてのリワーク支援を行っています。就労移行支援(一般企業での就職や復職を目指す障害福祉サービス)のノウハウを活かし、医療機関や所属企業とも連携しながら、安定した職場復帰を目指すプログラムを提供しています。
プログラムでは、性格検査などの各種アセスメントを積極活用し、「生きづらさ」を可視化できる仕組みを整えているのが特徴です。さらに、復職後の定着支援が充実している点もKaienの強みです。「再休職を避けたい」「自分に合う働き方をみつけたい」と感じている方は、ぜひご相談ください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修者コメント
休職から復職を考えるとき、リワークを利用して生活リズムを掴み、復職に繋げていくのは選択肢として良い時がありますね。休職を長く続けていると、どうしても復職に向けた生活リズムを作ることが難しくなることがあります。また、元の仕事のペースに慣れること、人に会うことへの不安感が強まることがあり、一旦職場の前のクッションとしてリワークを使うと自信に繋がることがある印象です。
どの実施機関によるリワークが良いかは、その方の持つ条件(病気、病態、職に就いていない期間、前年度収入)によっても違います。復職を目指してリワークに通っているにもかかわらず、リワークによって精神的に辛い思いをして、調子を崩す事態は避けるべきです。これはと思う実施機関に電話したり、主治医と相談することをお勧めします。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。