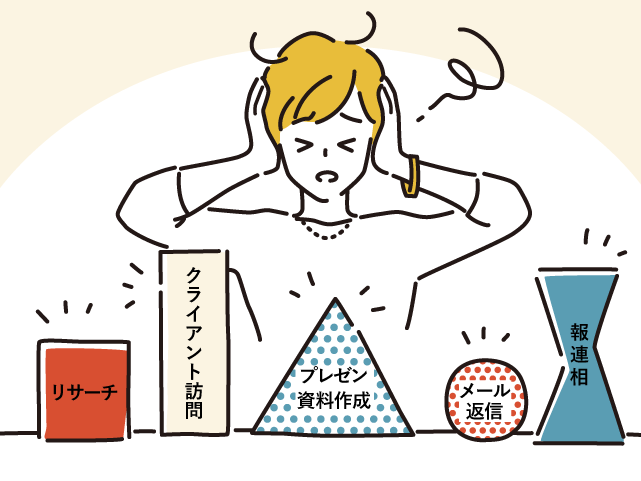
「周囲に比べて仕事を覚えるのが遅い」
「ミスが多く悪目立ちしてしまう」
「職場の人やお客さんとのコミュニケーションがうまくいかない」
いくら努力しても仕事に対する困りごとが改善しないのは、背景に発達障害*¹が隠れている可能性があります。しかし、発達障害かもしれないと過度に不安に思い、慌てる必要はありません。
本記事では、発達障害の症状や特徴、仕事の困りごとへの対処法について解説します。仕事ができないときの具体的なアクションも紹介しているので、ぜひお役立てください。
発達障害の主な種類と特徴
発達障害と一言でいっても、種類や特性は人によりさまざまです。ここでは、発達障害の3つの種類と症状の特徴を解説します。
注意欠如多動症(ADHD)
注意欠如多動症(ADHD)はその名の通り、「注意欠如」と「多動症」の2つの特徴を兼ね備えています。注意欠如は注意や関心が散漫になる、もしくは過集中してしまう状態を指します。特性により時間が守れなかったり、ミスが多くなってしまったりするのが特徴です。また、注意関心の切り替えが上手くいかず、1つのものごとに中毒的にハマってしまう人もいます。
一方、多動症はじっとしていることが難しく、衝動的に動いてしまうのが特徴です。
大人になると多くの人は多動性がおさまるため、落ち着きがないという印象を持たれる程度にとどまるケースもあります。
自閉スペクトラム症(ASD)
自閉スペクトラム症(ASD)は、表現力の乏しさや独特なこだわりの強さ、空気が読めないなどのコミュニケーション、社会性の難しさ、感覚過敏または鈍感といった特性が見られます。これらの特性は人により顕著に現れる特徴がさまざまで、程度の強さも異なります。
そのため、ひとえに自閉スペクトラム症と言っても、全く同じ症状やタイプの人はいないと言っても過言ではありません。
学習障害(LD)
学習障害*²(LD)は主に読み書き障害と算数障害に分けられます。読み書き障害は読んで字の如く、文字の読み書きに困難さが現れるのが特徴です。文字の形をとらえるのが難しい、漢字などをなかなか思い出せないといった特性により、文字の読み書きに時間がかかってしまいます。
一方、算数障害は数字や計算に必要な概念やスキルの取得に困難を極める障害です。
両者とも先天性のもので、短期記憶や認知能力の発達の凹凸に起因しています。
発達障害だと仕事ができないって本当?
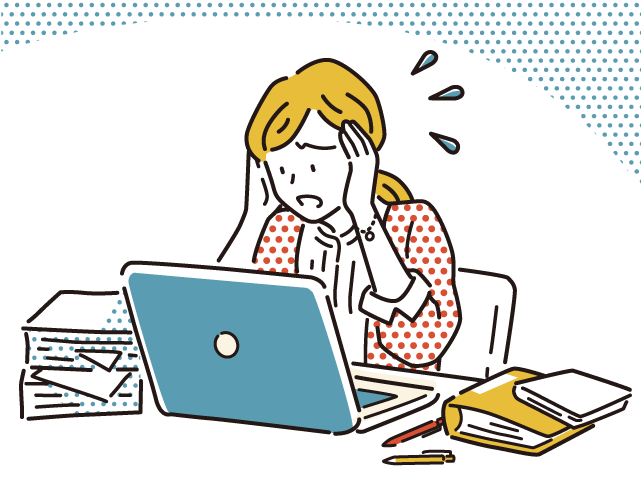
発達障害の特性により、働きづらさを感じる人は少なくありません。しかし、発達障害があるからと言って、仕事ができないと思い込んでしまうのは早計です。現れる特徴により仕事に対する困りごとや影響が生じるのは事実ですが、自分の状態を知り自己理解を深めることで対策や対処法をとることができます。ここでは障害の種類別に、見られやすい仕事の困りごとについて紹介します。
注意欠如多動症(ADHD)の方の仕事の困りごと
ADHDの方の場合、優先順位をつけることを苦手とし、うっかりミスが多くなる傾向にあります。そのため、仕事の予定を立てることや複数のタスクを同時進行することが困難を極めるケースが多いです。
また、不注意やうっかりにより何度も同じミスをしたり、締め切りを守れなかったりする様子も見受けられます。長時間集中することが苦手な場合は、同じ作業を続けることでミスが誘発されるケースもあるため注意が必要です。
自閉スペクトラム症(ASD)の方の仕事の困りごと
ASDの方の場合、集団活動を苦手とし、独特なこだわりを持つ特性により空気が読めないという印象を持たれがちです。仕事においては職場の人間関係が上手くいかなかったり、完璧主義が影響して何事も全力で取り組みすぎるため疲れたり、他責したりという困りごとが見られます。
また、細かなニュアンスを読み取るのが難しいため、抽象的な指示がわからない、空気を読んで臨機応変に対応するといった対処も苦手とする人が多いです。一方で、感覚過敏により職場の音や光、においといった環境面に拒否反応を示してしまう場合もあるので、職場環境にも配慮が必要になります。
学習障害(LD)の方の仕事の困りごと
LDの方は文字の読み書きが苦手なため、マニュアルを読んで仕事を進める、わからないことなどをメモ書きするといった作業は困難を極めます。また算数障害がある場合は、数式や計算の必要な業務も避けた方が良いでしょう。図解のマニュアルやタブレット入力など、視覚的に理解できるような工夫が必要です。
発達障害で仕事ができないときの対処法

前段の通り、発達障害の特性により仕事中は日常生活ではあまり気にすることのなかった困りごとを感じる方も多いかもしれません。しかし、自分が何を苦手としているかがわかれば、適切な対処をとることで円滑に仕事を進めることが可能です。
ここからは、自分の障害の特性や特徴に合わせた適切な対処法を、各アクションごとに確認していきましょう。
周囲に自分の見え方を相談する
仕事がうまくいっていない原因を考えるうえで、まずは自分自身の特徴を正しく理解することがとても重要です。しかし自分のことを客観的にとらえるのは難しいもの。自分を正しく理解するには、周りの意見を聞いてみるのが一番です。
相談する相手を選ぶ際には、自分のことを良く知っているか、相談相手は自分が信頼できる相手かどうか、の2点をポイントに考えるとよいです。特に、親など家族に相談できるのであればぜひ相談してください。自分が覚えていないような子どものころのエピソードが自分を理解する上で大きなヒントになることもあります。なるべくなら、複数の人から意見が聞けるとよいでしょう。
医療機関を受診する
周囲の意見を聞いたうえで、やはり仕事がうまくいかない原因は発達障害かもしれないと思う場合は医療機関を受診しましょう。精神科や心療内科を受診したことがない人は、少し尻込みするかもしれませんが余り気構えせずに行っていただけたらと思います。
医療機関で発達障害かどうかを調べるために行うことは、おもに問診(医師などによる状況の聞き取り)と心理検査の2点です。発達障害の診断が下されるかどうかを深刻に考える必要はありません。
発達障害の診断があるかどうかに限らず、人は誰もが能力に凸凹があるものです。心理検査の結果や、医師や心理士からの客観的なアドバイスにより、自分の得意不得意を知ることが出来ます。仕事を円滑に進める解決法が見つかるかもしれません。自分自身を理解する手段の一つだとおもって、まずは気軽に相談してみてください。
就労移行支援の利用を検討する
発達障害がありながら仕事を続けるためには、専門家や外部のサポートを受けることも有効な手段です。具体的な方法としては、服薬やカウンセリングといった医療サポートや、勤務先へ配慮を求める職場サポートなどが挙げられます。
そして重要なのが、就労に関する支援が受けられる福祉サポートです。自分に合った仕事探しは、自分の努力だけでは限界を感じてしまうこともあるかもしれません。そんなとき頼りになるのが、職業訓練や就活相談などにより障害のある方の就労をサポートする就労移行支援です。
就労移行支援は障害のある方を対象とした福祉サービスで、仕事に関する困りごとに対する訓練や、就活サポートなどを受けることができます。通所型で原則2年間という期間が設けられているのが特徴です。障害の特性やこれまでの職歴、経験を踏まえ、個々に支援計画を作成してもらえるため、自分のペースで適職を探したい方や仕事の困りごとへの対処法を身につけたい方にもおすすめです。
就労移行支援の主なサービス内容

就労移行支援は全国各地に事業所を設けており、特色や支援内容はさまざまです。Kaienの場合は、精神医学や発達心理学に基づいた就労移行支援を行っており、約2,000人を超える就職実績を誇っています。Kaienの主な支援サービスの内容は以下の通りです。
100種類以上の職業訓練
自分に合っている仕事を探すためには、あらゆる職種や仕事内容との出会いが大切です。Kaienでは事務職や軽作業などから、プログラミングやデザインといった専門職まで、幅広い分野の職業が体験できます。
困りごとに対処するスキルの習得
自己理解や困りごとへの対策として、豊富なカリキュラムの中からさまざまな講座の受講が可能です。発達障害の困りごとにも挙げられる優先順位のつけ方や、うっかりミスへの対策など、幅広くビジネススキルが習得できます。また就活支援として、自己PRの書き方やマナーなどを学べるのもKaienの強みです。
200社以上と提携した求人紹介
仕事を続けるためには、職場の障害への理解が不可欠となります。Kaienが取り扱う求人は、200社以上の障害に理解のある企業が中心です。ほかにも他事業所にはない独自求人も豊富に揃っているため、自身の発達障害の特性や症状にマッチした職場を見つけることができます。
充実の定着支援
せっかく就職が決まっても、すぐに離職してしまっては残念です。Kaienでは就労後の困りごとや生活習慣などの相談にのりながら、職場と円滑な関係を築けるよう定着支援を行っています。必要に応じて職場訪問や勤務先との調整も可能ですので、働いてみて悩みや困りごとが生じたときも安心です。
発達障害の特徴を理解して適切な対策と支援を受けよう
「仕事ができない=発達障害だから」というのは誤りで、大事なのは障害の有無ではなく自己理解ができているかどうかです。自分の特徴を理解し、適切な支援を求めることは恥ずかしいことではありません。
Kaienの就労移行支援は、あなたの仕事における苦手や困りごとをサポートし、働きやすい環境や仕事を見つけるアシストを行います。無料体験や説明会も随時開催していますので、発達障害により仕事に困りごとが生じている場合はお気軽にご相談ください。
*1発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
*2学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます
監修者コメント
発達障害特性を持った方の職業選び、まさにKaienさんのような就労移行支援事業所が活躍してくださっている分野です。外来で当事者の方と話していると、特性と能力がその方のやりたい仕事にマッチして能力を発揮されている方にも出会います。また仕事というのは、必ずしも自分の志望/適性とマッチしないものでもありますが、やってみると事前に思っていたよりも、ずっと継続しやすいこともあったりします。その意味でも、よく自分を理解してもらえる支援者と相談しながら就職活動をしていくメリットは大きいですね。自分に発達障害特性があると感じたなら、発達障害支援センターなど公的機関や、近隣の診断可能な診療所/病院を探して受診されることをお勧めします。発達障害特性そのものは多くの人が少なからず当てはまるものを持っています。診断そのものを恐れること無く、診断や検査結果を上手く活用して自己理解を深めたり、適性にあった生き方の一助にしてもらえばと考えます。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189