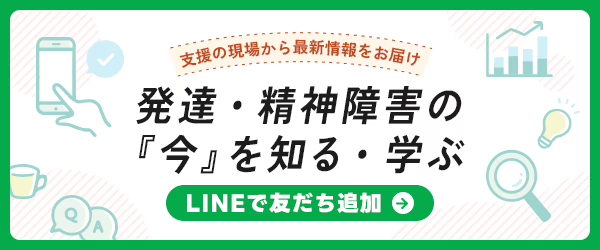発達障害*のグレーゾーンの方は、仕事においてミスやトラブルなどが多くなりがちなため、「仕事ができない」と思われてしまう場合があります。しかし自分の特性を知り、適切な対処ができればミスを減らすことが可能です。
この記事では発達障害のグレーゾーンの特徴や仕事上でのよくあるトラブルを取り上げ、対処法について解説します。適職を探す際に利用できる支援機関も紹介しているので、発達障害の特性で仕事がうまくいかずにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
目次
発達障害のグレーゾーンとは
発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の特性が見られるものの診断基準をすべて満たしていないため、発達障害とは診断できない状態のことです。グレーゾーンは程度を示すものであり、正式な診断名ではありません。しかし確定診断のないグレーゾーンであっても、発達障害の特性や症状が軽いわけではない点に注意が必要です。
発達障害は就職などの環境の変化を機に困りごとが増え、大人になってから自身の特性に気づく場合もあります。大人の発達障害については以下で詳しく説明していますので、併せてご覧ください。
大人の発達障害(神経発達症)とは?種類と症状、診断方法や相談先を解説
グレーゾーンの方が仕事ができないと言われる理由
発達障害のグレーゾーンの方が仕事ができないと言われる主な理由は、特性によって職場や仕事内容にうまく適応できないためです。
発達障害の主な特性として、認知機能のズレや判断力の弱さなどが挙げられます。認知機能にズレや弱さがあると、指示された内容を正確に理解することやリスクの想定が難しく、思い込みや勘違いなどのトラブルが多くなります。
一方、判断力が弱い場合は、優先順位を見極めて作業を進めることやマルチタスクが苦手だったり、周りに相談せず自己流で仕事を進めるなど、常識的な対応ができないケースも多いでしょう。
発達障害と診断されていないグレーゾーンの方の場合も、こうした特性が見られるため仕事ができないと悩む方は少なくありません。
グレーゾーンの方の仕事上の困りごと&トラブル例
発達障害のグレーゾーンの方に多く見られる仕事上の困りごとやトラブルは、次の通りです。
- 仕事の指示などを自己流に解釈してそのまま進めてしまう
- 集中力が続かずミスを繰り返してしまう
- あいまいな指示を出されると混乱してしまう
- 優先順位付けが苦手なため締切に間に合わない
- マルチタスクができなくて仕事が遅い
加えて、ASDのグレーゾーンの方は「すぐに疲れてしまう」「仕事に対する不安が強い」といった困りごとが見られる場合があります。これは空気を読もうと周囲に合わせて気配りをし過ぎてしまうことで、過剰適応が起こるためです。
上記はあくまで一例ですが、いずれの困りごとも無理をしすぎるとうつ病などの精神疾患を発症する二次障害につながる恐れがあるため、早めの対処が重要です。
グレーゾーンの方が仕事ができない場合の対処法
発達障害のグレーゾーンの方ができる仕事の対処法として、主に次の5つが挙げられます。
- 自身の特性を理解する
- 会社に合理的配慮を求める
- 障害者雇用や転職を検討する
- 支援機関を利用する
- 就労に関するスキルを取得する
それぞれの対処法について以下で詳しく解説します。
自身の特性を理解する
自身の特性を理解することで失敗しやすいパターンを予測できるようになり、勘違いやミス、周囲の人とのトラブルなどの予防につながります。自己理解を深めることで、自分の得意不得意や活かせる能力、配慮してほしい事項などが見えてくるはずです。
具体的なやり方としては、ノートなどに困りごとや失敗した状況などを記録し、振り返りをしてみましょう。可視化されることで、自分を客観視できるようになります。
会社に合理的配慮を求める
雇用の形態や障害者手帳の有無を問わず、障害の特性による困りごとがある方は会社に合理的配慮を求めることができます。合理的配慮とは、障害のある方が障害のない方と同等に社会生活を送れるよう、特性や困りごとに合わせた配慮を行うことで、すべての事業者に対して合理的配慮の提供が義務付けられています。
したがって、発達障害の診断のないグレーゾーンの方も合理的配慮を求めることは可能です。例えば「曖昧な指示ではなく、具体的に指示してほしい」「休憩をこまめにとりたい」など、会社の負担になりすぎない範囲で相談してみましょう。
障害者雇用や転職を検討する
職場によっては合理的配慮を求めても十分な対応ができないなど、仕事を続けるのが難しいケースもあります。その場合は無理をせず、より働きやすい職場を求めて転職するのも1つの手段です。
雇用形態は主に一般雇用と障害者雇用があり、障害者手帳を取得していればどちらにも応募できます。障害者雇用の場合、障害のある方の採用を前提としているため特性への理解や配慮を受けやすいメリットがあります。
グレーゾーンの方は発達障害の確定診断が出ていないため、障害者手帳の取得ができません。しかし特性のあらわれかたは個人差や幅が大きく、受診のタイミングによって判定基準に当てはまらなくなってしまうケースもあります。障害者雇用を検討している場合は、良心的に診断をつけてもらえるようセカンドオピニオンを検討してみるのも1つの方法です。
支援機関を利用する
発達障害の方はさまざまな支援機関を利用できます。生活を含む発達障害のお悩み全般を相談できる主な支援機関は次の通りです。
- 発達障害者支援センター
- 精神保健福祉センター
また、発達障害の方が仕事や就職・転職について相談したい場合は、主に次の支援機関が利用できます。
- 就労移行支援事業所
- ハローワーク
- 障害者就業・生活支援センター
- 地域障害者職業センター
就労に関する支援機関の概要や、具体的な支援内容は後述します。
就労に関するスキルを取得する
発達障害のグレーゾーンの方が仕事の困りごとに対処するためには、就労に関するスキルの習得が有効です。人間関係やコミュニケーションに関わるソーシャルスキルや、基本的なビジネススキルなどを身につけておくことで、ミスやトラブルの軽減につながるでしょう。
こうした就労に関するスキルは、障害がある方向けの就労支援機関で習得可能です。仕事ができないと悩んでいる方は、支援機関を上手に活用してみましょう。
発達障害のグレーゾーンの方に向いている仕事
「発達障害のグレーゾーンだからこの仕事に向いている」など、特性を一括りにして言うことはできません。発達障害の特性の出方は人それぞれであり、自身の特性や得意分野に合わせて仕事を選ぶことが大切です。
ここでは、発達障害の主な特性をいくつか取り上げ、それぞれに適した職種の例を紹介します。
ルールやルーティンに則った作業が得意な方の場合
- データ入力
- 経理・財務・法務担当
- 部品などの整理や管理
- 倉庫での仕分け作業
- 図書館司書
- 設備点検 など
自分の興味・関心のある分野で高い集中力を発揮できる方の場合
- 研究者
- Webデザイナー
- イラストレーター
- プログラマー など
コミュニケーションが苦手で、自分のペースで作業をこなしたい方の場合
- エンジニア
- ライター など
このように、適職を選ぶためには得意・不得意などの自己理解が欠かせません。
グレーゾーンの方の適職探しに利用できる支援機関
グレーゾーンの方専門の就活支援機関というものはありませんが、発達障害などの障害がある方向けの就労に関する支援機関はいくつかあります。主な支援機関と特徴は以下の通りです。
- 就労移行支援事業所
一般就労を目指す障害がある方を対象に、職業訓練や就活支援、定着支援など、スキルの習得から職場定着まで一貫したサポートを行う。
- ハローワーク
障害の有無を問わず誰でも利用できるが、障害に対する専門知識を持つ職員が就職・転職サポートを行うほか、障害者雇用の求人の取り扱いも多数ある。
- 障害者就業・生活支援センター
個別相談への対応や就労支援プログラムの提供、企業との連携による障害のある方の雇用促進サポートなどを実施。
- 地域障害者職業センター
障害がある方を対象に職業リハビリテーションや講習、基本的な労働習慣やソーシャルスキルの習得などのサポートを行う。
発達障害の特性により仕事でお悩みの方へ
Kaienでは、発達障害の方に特化した福祉支援サービスを実施しています。
Kaienの就労移行支援は、100職種以上の実践的な職業訓練や、ソーシャルスキル、ビジネススキルの習得に役立つ講座を毎日実施しています。また支援に当たっては、幅広い分野の専門的な知識経験を有するスタッフがいることもKaienの強みです。就活支援では、他事業所で取り扱っていない独自求人の紹介や、就職後の定着支援も行っています。
就活をする前にまずは生活習慣を整えたい、働く自信がまだ持てないという方には、Kaienの自立訓練(生活訓練)がおすすめです。自立訓練(生活訓練)では、障害理解や将来設計に役立つ講座や、生活習慣を整えソーシャルスキルを習得できる実践的なブログラムを実施しています。
どちらも無料で見学や体験利用を行っておりますので、興味がある方はお気軽にご連絡ください。
仕事ができない原因に応じた対処法を
発達障害のグレーゾーンに該当する方は、その特性によって仕事上の困りごとを抱えやすい傾向があります。自身の特性と仕事ができない原因を把握し、障害者雇用も視野に入れた働き方の見直しを行うなど、特性に合った対処法をとることが大切です。
Kaienでは発達障害の方に特化した就労支援を実施しています。障害者手帳を取得していない方も利用できますので、仕事に関するお悩みのある方はお気軽にお問い合わせください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
「グレーゾーン」はいつ聞いても悩ましい言葉です。発達障害特性はある、でも診断までは難しいということですから。精神科診断は検査値によって自動的につけられるものではないので、診察する医師によるバラツキと呼べる面もあります。いずれにしても、困りごとはあるので、それがグレーゾーンと表現されるかはともかく、自分に必要な支援があると考えるのであれば、職場に要請したり、支援機関を頼ってみるのは選択肢ですね。
もし、診断を求めて医療機関を訪ねた場合にグレーゾーンと言われて納得ができない場合には、改めて別な医療機関に掛かるのもお勧めします。発達障害診断に非常に慎重であったり、どちらかといえばしない方針の医師もいるためです。私自身は支援が必要な場合には積極的に診断することが多いです。特に「グレーゾーン」では今の問題が解決しない場合には尚更です。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。