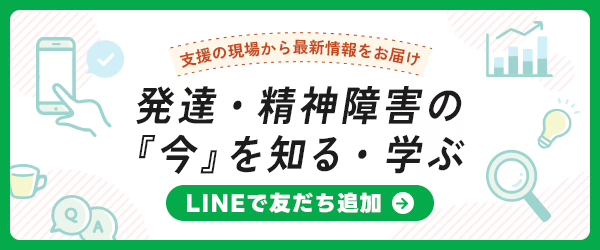メンタルの不調で仕事を休みがちで、自分は甘えているのではないかと感じる方もいるでしょう。「仕事に行けない」と感じたとしても、それは甘えとは言い切れません。まずはなぜメンタルの不調が続くのか、原因と解決策を考える必要があります。
今回は、仕事に行けないと感じやすくなる原因や仕事に行けないときの対処法、メンタルの不調で仕事を休んだほうがいいサインなどについて解説します。メンタルの不調と仕事に関して悩む方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
仕事に行けないのは甘え?メンタル不調との関係性
はじめに、「仕事に行けない」と悩んでいる方に向けて、その気持ちが本当に甘えなのかどうか、そう感じてしまう背景に隠れているメンタル不調について解説します。
仕事に行けないのは甘えではない
「仕事に行けない」と悩む人は決して少なくありません。まず知っておいてほしいのは、「仕事に行けない=甘え」ではないということです。そもそも「甘えかどうか」は本質的な問題ではなく、「なぜ行けないのか?」という原因を明らかにし、それに合った対策を講じることが大切です。
仕事に行けなくなってしまったときは一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人、上司、または専門家に相談してみましょう。
「仕事に行けない」の背景にメンタル不調が隠れている可能性がある
「仕事に行けない」という気持ちの背景には、メンタルの不調が隠れている可能性があります。心の不調を放置してしまうと、うつ病や統合失調症などの精神疾患につながるおそれがあり、無理をして働き続けるのは非常にリスクが高いと考えてください。
もしメンタルの不調が見られる場合は、できるだけ早く上司に伝え、働き方の見直しや休暇の取得など、適切な対応を取りましょう。会社によっては、上司でなく産業医に相談することも可能です。
「甘え」と考えるとさらにメンタルの不調が悪化する恐れも
「甘え」と捉えて無理に仕事に行くと、メンタルの不調がさらに悪化する可能性もあります。「休みたいと思うのは甘えだ」と思って無理をすると、重い精神疾患へつながり長期の離職・療養を余儀なくされる場合もあります。
また、寝ても疲れが取れなかったり、胃腸の不調が続くようになったりと、メンタルの不調は自身の体調にも影響を及ぼす場合が多いです。この中で無理をし続けると、働き続けるのが困難になり長期的な休養が必要な状態になっていくでしょう。
心身ともに限界を迎える前に、職場に相談をして適切な対処を考えることが重要です。
まずは直属の上司に相談をして、自分の体調に合わせた働き方やシフトの組み方などを共に考えていく必要があります。身近の信頼できる上司や同僚に話して、解決策を探っていきましょう。
仕事に行けないと感じやすくなる原因
仕事に行けないと感じる原因は人それぞれです。ここでは、業務内容や職場環境など、仕事に行きたくないと感じやすい具体的な理由を分かりやすく解説します。
業務内容があっていない
「自分にはこの仕事が向いていないかもしれない」と感じると、出勤すること自体が大きなストレスになってしまいます。例えば、業務の難易度が高すぎてプレッシャーを感じたり、反対に単調でやりがいを感じられなかったりすると、精神的な負担を強く感じるでしょう。
また、苦手な作業が多いなど自分の強みを発揮できない環境では、仕事へのモチベーションが下がりがちです。こうしたミスマッチが長期的に続くと、やる気の低下や体調不良を引き起こすことがあり、「仕事に行けない」と感じやすくなります。
業務量が多すぎる・給与と見合っていない
「働いても働いても仕事が終わらない」「こんなに頑張っているのに給料が少ない」と感じる状況では、仕事への意欲が削がれてしまうのも無理はありません。業務量が過剰である上、その努力に見合った評価や報酬がないと、心身ともに疲弊してしまうのは当然です。
業務量と給与が見合っていないと自己肯定感の低下にもつながり、「もう仕事に行きたくない」という気持ちがより強くなる原因になります。
業務時間や通勤時間が長すぎる
長時間労働や長距離通勤は、それだけで大きなストレスになります。家に帰っても休む時間がほとんどなく、心も体も休まらない日々が続くと、仕事へのモチベーションはどんどん下がってしまいます。
また、プライベートの時間がほぼ取れない状況では、疲労回復やリフレッシュが十分にできません。仕事中心の生活に疑問を感じるようになることもあるでしょう。さらに通勤ラッシュのストレスも積み重なると、「もう行きたくない」と感じるのは自然なことです。
職場の人間関係に問題がある
上司や同僚との人間関係がうまくいっていないと、どれだけ仕事が好きでも「行きたくない」と感じることが増えます。例えば、上司や同僚との軋轢、パワハラやいじめなどがあると、出勤そのものが苦痛になるでしょう。
また、「特定の人物が苦手」「相談しにくい雰囲気」「孤立感がある」なども、心に大きな負荷をかけます。こうした人間関係の悩みはメンタル不調を招く原因にもなるため、我慢や無理をせず早めに対応を考えることが重要です。
職場環境があっていない
「周囲の音がうるさい」「設備が古く使いづらい」「人との距離が近すぎる」など、物理的な職場環境が自分に合っていないと感じる場合も、出勤が苦痛に感じる原因になります。また、会社の方針や働き方が自分の価値観と合わず、「仕事に行きたくない」と感じるケースも少なくありません。
例えば、「効率より根性論が重視されている」「無理なノルマが課せられる」といった状況では、自分らしく働くことができません。こうした環境で無理に働き続けると、知らず知らずのうちに精神的な負担が蓄積し、メンタル不調を引き起こす原因となります。
仕事に行けないときにできる対処法とは?
「もう仕事に行けない」と感じたとき、何をすればいいのか分からず不安になりますよね。ここでは、仕事に行けないときにできる具体的な対処法を5つ紹介します。「これならできそう」と感じるものから取り組んでみてくださいね。
生活リズムや生活習慣を改善する
規則正しい生活習慣を取り戻すことは、心身のバランスを整える第一歩になります。例えば、「食事の内容が偏っている」「夜更かしが続いている」といった日常の乱れは、少しずつ心身に影響を及ぼすため、改善が必要です。
まずは、毎日同じ時間に寝て起きる生活リズムを整えることから始めましょう。さらに、軽い運動やストレッチを取り入れることで体の調子が整い、気分も前向きになります。こうした小さな習慣の見直しが、不調の軽減につながるケースも少なくありません。
ストレス発散やリフレッシュを行う
ストレスを放っておくと、知らず知らずのうちに心が疲弊してしまいます。趣味に没頭する時間を設けたり、好きな音楽や本に触れたりして、意識的に気分転換を図りましょう。思い切って1日休暇を取るのも、心身のリフレッシュに効果的です。
さらに、自然の中を散歩したり、軽い運動で汗を流すのもおすすめ。出かけるのが負担になる人は、自宅でゆっくりと好きなことに没頭するのもよいでしょう。自分に合ったストレス発散やリフレッシュの方法を見つけておくと、仕事へのモチベーション維持にも役立ちます。
異動や配置転換を申し出る
今の業務内容や職場の人間関係がどうしても合わないと感じる場合は、人事担当者や上司に異動や配置転換を相談するのも選択肢のひとつです。異動が認められれば合わない環境から離れられるため、ストレスを大きく軽減できるでしょう。人事や上司に直接相談しづらいときは、産業医に相談してみてください。
ただし、会社の状況や人員配置の都合によっては、希望が必ずしも通るとは限らない点には注意が必要です。
転職する
「生活習慣を改善しても変化が感じられない」「異動や配置転換が認められなかった」「会社の経営方針そのものが合わない」といった場合は、転職も視野に入れてみましょう。今の職場に無理に留まっていても、心身の疲れが蓄積し、精神疾患につながるなど事態が悪化するケースもあります。
転職先を選ぶ際は、仕事内容や報酬、通勤時間に加え、自分の価値観やライフスタイルに合った働き方ができるかどうかも確認しましょう。焦って決めるのではなく、無理なく長く働ける職場かを意識し、自分にとって納得のいく環境を探すことが大切です。
休職や退職をする
「もう限界かもしれない」と感じたときは、一度職場から離れて心身を休めることが大切です。特に、気分の落ち込みが続いたり、体調不良が強く表れていたりする場合は、休職や退職といった選択肢も真剣に検討してください。
無理に働き続けるよりも、しっかりと休養を取るほうが回復が見込めるでしょう。会社によっては休職期間中に異動先を調整してくれる場合もあるため、まずは相談してみるのもおすすめです。
メンタルの不調かも?仕事を休んだほうがいい時のサイン
メンタルの不調によって仕事を休んだ方がいい時のサインには、下記のようなものがあります。
- めまいや動悸がする
- 夜眠れず朝早くに起きられない
- 吐き気や腹痛などの体調不良がある
- 音や光、匂いに敏感になる
- 暴飲暴食または食欲低下がみられる
- 趣味などの楽しみへのエネルギーがなくなる
- 感情の起伏が激しく涙が出る
これらは体が休息を必要としているサインなので、もし出現していたら無理をせず仕事を休むのが最優先です。このまま無理をして出勤すると、症状が悪化する可能性もあります。
この章では、それぞれのサインについてどのようなものか詳しく解説します。
めまいや動悸がする
精神的な疲労があると、めまいや動悸が出現し日常生活で動きにくくなる場合もあります。朝起きてフラフラしたり、動悸がしたりする際に無理をするのは危険です。
めまいや動悸の症状が軽い場合でも無理をして出勤すると、仕事中に転倒してしまうなど仕事に支障をきたす場合もあるでしょう。
もし症状が重い場合は、呼吸器や心臓の疾患の可能性や、起立性調整障害やメニエール病の可能性も疑われます。そのため、医療機関を受診して慎重に経過をみる必要があります。
起立性調整障害やメニエール病ならば、仕事を長期的に休むことも検討した方が良いでしょう。
起性調整障害やメニエール病の症状については、それぞれ別の記事で解説しているので併せてご覧ください。
大人の起立性調節障害でも仕事は続けられる?治療法や支援についても紹介
メニエール病とは?働きやすい職場環境や向いている仕事、支援制度を解説
夜眠れず朝早くに起きられない
精神的に不安定な状態になると、睡眠に支障をきたす場合もあります。夜になかなか寝付けず、朝に起床するのも億劫になってしまい日中の活動に影響が出てしまいます。そうなると仕事をしているときに、眠気が出たり寝不足による頭痛が起きたりして、いつも通り仕事ができなくなってしまうでしょう。
睡眠不足によって仕事への影響が出ると、職場での印象を落とす可能性もあります。
パフォーマンスが思うようにいかず、本人にとっても苦しい状況になりかねません。心療内科で睡眠を改善するための薬を処方してもらったり、日々の生活習慣を見直したりして、体内時計を正していく必要があるでしょう。
自律神経の乱れやストレスなど、睡眠に影響が出る理由は人それぞれのため、医師に相談しながら睡眠や生活リズムを改善していくのが大切です。
症状によっては長期的な通院が必要のため、睡眠に悩みがあれば早めに医療機関を受診してください。
吐き気や腹痛などの体調不良がある
吐き気や腹痛などの消化器症状や、頭痛や悪寒などの体調不良がある場合、単純に身体的な不調だけが原因だと考える方もいます。しかし、心と体は密接に関係しているため、メンタルの不調が体の調子に影響を与えていることも多いのです。たとえば、過度なストレスを抱えた生活が続くと、心身ともに疲弊し、身体的な症状が現れる場合があります。
特に、仕事でのストレスが溜まり、自覚しないうちに心と体のバランスが崩れてしまうことがあります。これは、身体が無理をしすぎて「休んでほしい」というサインを送っている証拠です。このようなサインを無視すると、状態が悪化してしまうことがあるため、早めに対応することが大切です。
もし、ストレスが原因で吐き気や胃腸の不調などが続いている場合、それを放置してしまうと、さらなる体調の悪化や大きな病気につながる恐れがあります。できるだけ早く医師の診察を受け、原因を突き止めて適切な治療に取り組むことが重要です。
もし、胃潰瘍や過敏性大腸症候群などの病気が疑われる場合は、一定期間の通院や入院が必要になる場合もあります。これらの病気にかかっている可能性があるのであれば、病院で検査を受けて適切な治療を受けるようにしましょう。
音や光、匂いに敏感になる
ストレスがかかると、周囲の音や光、匂いに敏感になる方がいます。これは『感覚過敏』と呼ばれる状態です。
日常生活の中で、苦手な音や匂い、さらにはスマートフォンやテレビなどの光に過剰に反応してしまい、生活に支障をきたす場合もあります。
普段は気にならない音や光、匂いでも、精神的なストレスが増えると、そうした刺激に対して過敏に反応してしまう場合があります。特にもともと感覚過敏がある方は、ストレスが加わることで症状がさらに強くなることがあるのが特徴です。
感覚過敏そのものに対して直接的な治療方法や治療薬はないものの、ストレスを軽減させることで症状が緩和される可能性があります。
感覚過敏の症状を少しでも軽減するためには、イヤーマフや耳栓で音の刺激を和らげたり、サングラスで光の刺激を減らしたりすることが効果的です。
感覚過敏のうち、匂いに敏感になる嗅覚過敏の症状については、下記で解説しているため併せてご覧ください。
嗅覚過敏とはどんな状態?原因や感覚過敏の種類、仕事での対策と伝え方を解説
暴飲暴食または食欲低下がみられる
暴飲暴食や食欲低下など、極端な食欲の変動も精神的な不調のサインの1つと考えられています。通常、食事を摂るとレプチンというホルモンが分泌され、食欲を抑制しエネルギー消費を促進します。しかし過労や睡眠不足などでストレスが溜まると、レプチンの分泌が減少するため、食欲が抑制できなくなり暴飲暴食につながる場合もあります。
またストレスが溜まると分泌されると言われているのが、コルチゾールという抗ストレスホルモンの1つです。コルチゾールは糖や脂質を体内に蓄える働きを持っているもので、暴飲暴食を助長してしまう可能性があります。
一方で、ストレスによる食欲低下は、脳内で交感神経と副交感神経のバランスが乱れている状態です。過度のストレスを受けると、胃腸のぜん動運動や消化吸収が正常に機能しなくなり、胃酸過多や消化不良といった症状が現れる場合があります。
食欲の大きな変動は、気分変調症などの精神的な疾患の一症状である可能性も考えられます。気分変調症の詳しい症状については、下記で解説しているため併せてご覧ください。
気分変調症とは?うつ病との違いや過ごし方の注意点、仕事を続けるコツを解説
趣味などの楽しみへのエネルギーがなくなる
メンタルの調子が悪くなると、これまで楽しんでいた趣味に対してもやる気が起きなくなることがあります。趣味に取り組んでも、それがただの作業のように感じてしまい、かえってストレスに感じる方もいるでしょう。ストレスによる疲労が蓄積すると、物事に対する感受性が鈍くなるのが特徴です。
趣味に限らず、何をしても楽しさを感じられない日々が続く場合、精神的な不調が原因となっている可能性があります。身体のだるさや疲労感が増し、気分が落ち込んでしまう方も少なくありません。たとえば、普段なら笑えるテレビ番組が笑えなかったり、好きな小説や漫画を読んでも心が動かないと感じた場合は、心身の不調のサインかもしれません。
このような日々が続くときは、精神的な疾患が関わっている可能性もあり、治療が必要な場合もあります。早めに精神科や心療内科を受診するのをおすすめします。
感情の起伏が激しく涙が出る
感情の起伏が激しくなったり、わけもなく涙が出たりするのも、メンタル不調の方によく見られます。通常であれば泣かない場面で、急に泣き出したり怒ったりするのも、心に不調が現れているサインです。仕事や日常生活でも、感情のコントロールが難しくなり、自分自身も辛い状態になります。
感情の起伏が激しくなる理由は、心身ともに緊張状態になっているからです。緊張状態になると、感情のコントロールが難しくなります。慢性的にストレスを抱えていると、些細なことで涙が出たり怒りが抑えられなくなったりすることもあるでしょう。
あまり感情をさらけ出しすぎると、家族や友人も困惑するため早めの対処が必要です。
ストレスはもちろん、慢性的な睡眠不足や疲労も感情のコントロールがうまくいかない原因になります。規則正しい生活を心がけたり、十分な休息を取れるよう工夫をする必要があります。自分自身で対処に悩んだ場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
メンタルの不調が原因で仕事を休みたい!甘えと思われないための伝え方
メンタルの不調が原因で「仕事に行けない」と思うとき、職場にどう伝えればよいか悩む方もいるでしょう。職場の上司に『甘え』だと思われないためには、休みを取りたい期間を明確にし、伝え方に配慮することが大切です。また、会社の勤務シフトや配置に影響を与えてしまう場合もあるため、早めに相談や報告をするようにしましょう。
急な体調不良で当日または前日に休む場合、自分自身や家族の病気を理由にすると、比較的休みやすくなります。症状を簡潔に説明し、医療機関の受診予定を伝えておくことで、復職時にスムーズに対応できるでしょう。
長期的に休暇を取りたい場合は、冠婚葬祭や有給休暇の消化などが理由として考えられます。しかし、どうしても心身ともに限界を感じる場合は、かかりつけ医に相談し、診断書を発行してもらうことが重要です。診断書を基に上司と休職について相談すれば、会社の規定に従って休職を取得できる可能性があります。
ストレスの原因から一時的に離れることで、心身の回復が期待できます。休暇が取れたら、無理をせずに体をしっかり休めるのが大切です。
メンタルの不調で長期的に仕事を休みたい時の対処法
「仕事に行けない」という気持ちが続き、休職したり長期的に休んだりしたい時には、所定の手続きを取ります。医療機関に必要書類を記載してもらい、会社で休職の手続きを取ります。
この章では、メンタル不調で仕事を長期間休みたい場合の対処法についてそれぞれ解説します。不調による休職を検討している方は、ぜひご確認ください。
医療機関を受診する
まずは、自分のメンタルの調子について医師に相談しましょう。医師による診察を受けることで、どれくらいの休息が必要か、またどのように治療を進めるべきかを具体的にアドバイスしてもらえます。受診時には、仕事でどのようなストレスがあるのか、体調不良がいつから続いているのかをしっかりと伝えることが重要です。
医師は、必要に応じて薬を処方したり、精神療法を行ったりして治療を進めます。また、生活習慣の改善に関しても相談できるため、日常生活におけるアドバイスを受けましょう。もし、仕事に支障をきたすほどの不調がある場合は、会社での休職手続きに必要な診断書を医師にお願いすることができます。
心療内科や精神科の受診に抵抗がある場合は、オンラインカウンセリングを利用するのも一つの方法です。まずはオンラインでカウンセラーに相談し、必要と判断されたら医療機関を受診することを考えてみてください。
自宅や勤務先から通いやすい心療内科や精神科を見つけておくと、通院が便利で緊急時にも頼りやすくなります。定期的な相談を通じて、自分の状態を把握することができます。
早めに会社に連絡する
メンタルの不調で仕事ができない場合は、できるだけ早めに会社に連絡をしましょう。急な欠勤の場合は、電話で早めに伝えることが重要です。特に、当日や前日に休む場合は、勤務開始1時間前までに連絡すると、職場の準備にも余裕が生まれます。
もし「仕事に行けない」という気持ちが続き、長期的な休養が必要な場合は、まず医療機関を受診して、医師に診断してもらいましょう。診断書を受け取ったら、会社の休職手続きを進められます。
また、休職前には同僚や上司に業務の引き継ぎを行い、スムーズに休職できるようにしておきましょう。
家族に相談して理解を得る
メンタル不調で休職する際は、家族の理解が不可欠です。収入が減る可能性があるため、家族も不安を感じるかもしれませんが、自身の不調によって仕事に支障が出ているなど正直に伝えて、協力をお願いしましょう。
無理をして働き続けるとさらに悪化するリスクがあり、治療と休養が必要である点を説明する必要があります。家族に相談する上では、決して「甘え」ではないと理解してもらうのが重要です。家族と定期的に話し合い、家事などできる範囲で手伝いながら、復職に向けた準備を進めていくのも良いでしょう。
休養中にやるべきことや今後の予定を明確にしておくと、復職後の見通しが立ちやすくなります。
仕事に行けないのは甘えではない!心と体を休め少しずつ前に進もう
「仕事に行けない」と思ってしまうのは、決して甘えではありません。「業務内容が合っていない」「職場の人間関係が悪い」「業務時間が長すぎてリフレッシュできない」といった状況が続くと心身への負担が積み重なり、メンタル不調を引き起こす原因になります。生活習慣の改善や異動の希望を出すなど、できる対処法から取り組んでみてください。
メンタルの不調で心身ともに症状が出ている場合は、一日でも早く休みを取るのが大切です。症状が長引く場合は、医療機関で適切な治療を受けながら、仕事に復帰できるよう体調を整えましょう。
「仕事を休む」と会社に伝えるのは勇気がいりますが、メンタル不調になった自分の心身を労うためには必要な行動です。上司と相談をしながら、休職・休暇をしっかりと取って療養に専念するようにしましょう。場合によっては、少し休んでから違う仕事を探すのも1つの選択肢です。
しばらく長期療養を取って体調が回復し、休職から復職をするにはリワークの利用もおすすめです。自分の仕事の適性を知って、少しずつでも社会性を取り戻せます。担当スタッフに相談しながら、職場復帰のプログラムにも取り組めます。
リワークプログラムに関心のある方は、ぜひお問い合わせください。
監修者コメント
メンタルの不調とは「職場や社会生活における心理社会的要因(ストレス要因)が契機となって、心身に不調をきたすこと」と言えるのではないでしょうか。難しいのは、何がストレス要因になるのかは人によって違い、誰もが同じ結果にはならないということです。個人個人にその人なりのストレスへの脆弱性や回復に向かう力(レジリエンス)があるとも言えるでしょう。私は外来でメンタル不調が「甘え」と感じられたことは一度としてありません。不調の理由には、精神疾患であることもあれば、その方をとりまく環境への適性が問題な場合もあります。メンタル不調にはその不調に至った理由があるはずです。状況打開のために、本記事の対策を参考にしてどこかに相談してみましょう。尚、精神科医としては、現れているのがメンタルの不調であっても、身体疾患がベースになっている可能性は必ず念頭に置いています。メンタルに影響する身体疾患は、甲状腺機能異常が代表的ですが、鉄欠乏性貧血が理由なことだってあります。そういう意味で医療機関の選択肢はとりあえず検討してみることをお勧めします。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。