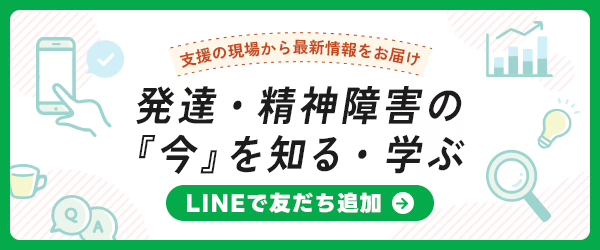発達障害*がある方が就職活動をするとき、発達障害をどの程度考慮すべきか、成功のポイントは何か、そもそも就職活動をして大丈夫なのかなど疑問が浮かぶことがあると思います。「発達障害」があることは分かっていても、具体的な対策が分からないと進むべき道を決めることは難しいですよね。
そこでこの記事では、発達障害の方が就職活動にどう向き合っていけばよいか、具体的な道筋やポイント、就活に活用できる支援サービスなどを紹介します。発達障害の方の就職事例や就活でつまずきやすいポイント、よくある質問についても解説しますので、就職を成功させるためにも、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
発達障害の方の就活が難しい理由
発達障害の方の就職活動を難しくしている理由は、以下のような特性によるところが大きいです。
- マルチタスクが苦手
- 生活リズムが乱れがち
- 適切なマナーがわからない
- 遅刻や欠席など時間を守れないことが多い
- コミュニケーションが困難で思ったことを伝えられない
- 思いつきで行動してしまうのでスケジュール管理が苦手
ビジネスは「会社」という集団のコミュニケーションが求められる場です。仕事そのものは問題なくこなせても、上記のように「それ以外」の部分で失敗をしてしまうと、間接的な自信の喪失や、職場における評価への悪影響などが懸念されます。
発達障害の方が就活前にまずやること

発達障害がある場合いきなり就職先を探すのではなく、まずは発達障害を取り巻く就職状況の「情報収集」と、自分の特性について知る「自己分析」から始めましょう。
発達障害の方は仕事の能力自体が低いわけではないので、最適な職場さえ見つかれば、十分な活躍が見込めます。そのためにも、職場と自分の相性を測るための下準備を念入りにすることが大切です。
情報収集
発達障害がある方たちの互助組織である「当事者会」や、障害がある方の就職を支援する「就労移行支援」などでは、発達障害の方の「悩み事」や「困りごと」について体験談を聞くことができます。
体験談を役立てるには、特性やタイプが自分に似ている方や、性別、年齢、目指す職種などが近い方の話を参考にするとよいでしょう。
なお、就労移行支援は65歳未満で一般就労を希望する障害がある方なら誰でも利用できます。実際に利用するかはさておき、ひとまず話を聞きに行くだけでも問題ありません。
自己分析
発達障害がある方は、行動や思考などの特徴からASD(自閉スペクトラム症)傾向がある方やADHD(注意欠如多動症)傾向がある方などに分けられます。ここではASD傾向がある方とADHD傾向がある方によく見られる特徴を9つ紹介します。
ASD傾向のある方によく見られる特徴
- 同時並行が苦手。変化に弱い
- こだわりが強く、柔軟さに欠ける
- 柔軟な会話や文章が苦手
- 大きな流れを見極められない
- 砕けた会話が苦手。嘘をつけない
ADHD傾向のある方よく見られる特徴
- 切り替えが苦手で、好きなことばかり集中する
- 小さなミスが多く、注意力が散漫
- 気持ち・やる気にムラがある
- 独断で動きやすく、チームプレーが苦手
情報収集や自己分析については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
働き方を決める
自分の特性や想定されるであろう困りごと・悩みごとが分かったら、自分に向いていると思われる環境や働き方を決めましょう。
働き方は大きく「障害者雇用」と「一般雇用」の2種類に分けられます。障害者雇用と一般雇用の両方に申し込むことも可能なので、必要に応じて使い分けましょう。また、障害者雇用で就職したあとに、再度一般雇用に申し込むことも可能です。
ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。
障害者雇用
障害者雇用とは、障害者雇用促進法に基づいて、障害者の職業の安定を図るために一定規模以上の会社や自治体に実施が義務付けられている制度です。障害者雇用に応募するには、障害者手帳を取得している必要があります。
障害者雇用のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
- 残業が少ない
- 規模要件があるので、大企業やその系列会社など安定した就職先が多い
- 契約社員としての就職した場合でも契約打ち切りは稀
- 正社員登用されるケースが増えている
デメリット
- 専門職が少ない
- キャリアを磨きにくい
- 大きな昇給を期待しにくい
- 一般雇用に比べ、求人数が少ない
障害者雇用は特性への配慮がしっかり受けられるものの、スキルやキャリアを磨きにくい傾向があります。ただし、障害者雇用における専門職は首都圏を中心に増加傾向で、徐々に一般雇用とのギャップが埋まりつつあります。
一般雇用
一般雇用は通常の就活と同じなので、選べる会社や職種の幅が広いメリットがあります。結果を出せばキャリアを積めますし、大きな昇給も期待できるでしょう。
ただし、職責が増せば自分に求められる負担が大きくなることは理解しておきましょう。特に中小企業では一人でいろいろな仕事をすることが多く、マルチタスクが苦手な方にとっては負担が大きい環境になるかもしれません。
また、管理職になると人付き合いやグループ全体の進捗管理など、コミュニケーション面の負担が増す点も注意しましょう。
働き方については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
一般雇用か障害者雇用かそれとも…4択で考える発達障害の人の就活事情
障害者雇用の動向
障害者の雇用数は、年々増加傾向にあります。
厚生労働省が2024年に行った調査によると、民間企業に雇用されている障害者の数は67万7,461.5人で、前年と比べ3万5,283.5人増加(前年比5.5%増加)しました。実雇用率(企業で実際に雇用されている障害者の割合)は2.41%で、前年と比べ0.08ポイントの上昇です。
雇用障害者数は21年連続、実雇用率は13年連続で過去最高を更新しており、障害者雇用の状況は年々改善されています。
障害の種類別で雇用数を見ても、全ての種類で前年から増加しており、特に伸び率が大きいのは精神障害者で、前年比15.7%の増加です。
障害者雇用数増加の背景には、民間企業の法定雇用率が徐々に引き上げられていることや、障害者雇用の認知度が高まっていること、障害者人口が増加傾向にあることなどがあります。
発達障害のある方が就活を行う上でのポイント
発達障害のある方が就活を行う際には押さえておきたいポイントがあります。具体的には次の4点です。
- 企業研究を行う
- 条件を絞り過ぎない
- 障害者雇用の場合は配慮事項をまとめる
- 支援サービスや制度を活用する
以下で詳しく解説します。
企業研究を行う
自分に合った企業を見つけるためにも企業研究を行いましょう。
就活前にやることとして「自己分析」について先に紹介しましたが、そこで把握した自分の特性や配慮してほしい希望などを踏まえて興味関心のある業界や企業を探しましょう。目星がついたら、下記のような点についてより詳しく調べてみましょう。
- 障害者雇用の実績はどうか
- 障害者雇用に対してどのような取り組みを行っているか
- 企業理念や企業の求める人材像、社風はどのようなものか
上記の点に注目して、自分にとって働きやすい企業かどうか検討することがおすすめです。
条件を絞り過ぎない
希望条件を絞り過ぎないことも大切です。
就活では、希望条件をある程度絞ることが大切だといわれるケースもあります。これは、多くの条件にこだわりすぎると、条件に該当する求人が少なくなるためです。
しかし、障害者雇用を希望する場合は、求人数が一般雇用と比べて少ないこともあり、条件を絞りすぎずに、視野を広くもって求人を検討することがおすすめです。
選択肢を増やすためにも、希望条件を絞り込み過ぎずに、数ある希望条件に少しでも合うような求人があれば、検討していくようにしましょう。
障害者雇用の場合は配慮事項をまとめる
障害者雇用を希望している場合は、企業側にどういう配慮をしてもらいたいか配慮事項をまとめておきましょう。
自分の障害特性と、その特性のためにどのような配慮が欲しいかを具体的に書くのがポイントです。例えば、下記のように配慮してほしい理由(特性・困りごと)と対策を記載します。
- ADHDで、集中し続けられない傾向があるため、タスクを小さな単位に分割してほしい。
- ASDで、曖昧な表現が理解できないため、業務指示は具体的な言葉やイラストで指示してほしい。
配慮事項を一人で考え、まとめることは簡単な作業ではありません。具体的にどのような状況で困るか、どのような支援が欲しいかが容易に想像できない人もいるでしょう。その場合は、次に紹介する支援制度の活用がおすすめです。
支援サービスや制度を活用する
発達障害で就活をする場合には、支援サービスや制度も活用しましょう。
就労移行支援やハローワークの障害者専門窓口などを活用すると、障害者の特性や雇用に詳しい専門スタッフが、自己分析や求人探しを手伝ってくれます。
自分一人ではわからなかった自身の特性や企業の情報を把握できるようになるでしょう。障害に理解のある企業を紹介してもらえるほか、就職後も職場に定着できるように支援してもらえるなど、利用には数多くの利点があります。
先述の「配慮事項」をまとめるにあたっても、支援サービスは役立つでしょう。支援サービスにおける職場訓練などを受けることで、自分が働く上で必要な配慮事項が実感できるほか、スタッフが配慮事項をまとめるサポートをしてくれます。
発達障害のある大学生の就活のポイント

これから就活生になる大学生の方は、あらかじめ就活のポイントを押さえておき、可能な限り就活の難易度を下げておきましょう。特に以下の4つのポイントは押さえておくべきです。
- 3年生までに単位をほぼ取り終えておく
就活と卒論に加えて単位の取得までするのは負担が大きい。4年生になったら学校へ行く頻度を週1~2日程度に調整しておくとよい。 - 大学の就職課のサポートを受ける
就職課は発達障害がある学生にも適性がある求人や、合同面接会などの情報を持っている場合がある。最初に相談に行き、積極的な利用を。 - 就労移行支援やハローワークを活用する
障害者雇用の情報は、大学の就職課だけでは不十分。専門のサービスが受けられる機関の活用を。 - 就活のスケジュールを把握する
採用情報の解禁時期、面接など選考の解禁時期、内定の解禁時期など就活の全体のスケジュール、流れを把握する。
大学生の就活のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
就活に成功する履歴書の書き方
発達障害がある場合でも、履歴書の基本的な書き方に違いはありません。ただ、発達障害の記載については必須ではないものの、合理的配慮の具体的な相談を考えると、障害の詳細や配慮事項を記載するための記載欄を設けたテンプレートを使用したほうがよいでしょう。2024年からは、一般雇用でも合理的配慮の提供が義務化されています。
そのうえで「パソコンで記入する」、「誤字脱字や書き方の基本的なルールに気を付ける」など基礎的な点に注意して作成します。
また、記載する情報は「和暦・西暦を統一する」、「名前は戸籍に登録された漢字で書く」、「住所を省略しない」などの点に気を付けましょう。
履歴書の書き方や障害の配慮事項の伝え方については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
障害者雇用で採用される履歴書とは?志望動機や配慮事項の書き方、作成ポイントを解説
就活に関するよくある質問
就活に関するよくある質問として、次のようなものがあります。
- 資格は就活に有利?
- 在職中でも転職は可能?
就活をスムーズに進めるためにも、疑問を解消しておきましょう。質問に対する回答は次の通りです。
資格は就活に有利?
資格は就活に必ずしも有利とはいえないものの、プラスに働くこともあるでしょう。
実際の就活市場では資格よりも実務能力が重視されがちです。特に戦力として求められる30代以降はこの傾向が強くなります。
そもそも、障害者雇用でまず求められるのは「安定して出勤する」ことです。雇用者側からすれば、短期的な結果よりも長期的に安定して勤務できる方が安心して雇えます。
とはいえ、資格は自分の自信にもつながりますし、モチベーションの高さをあらわす指標としても有用です。資格を取得した理由を仕事内容と紐づけて説明できれば、面接のときにもプラスに働くでしょう。
以下の記事では、就活において資格を取る意義を体験談を交えて解説しています。ぜひご参照ください。
在職中でも転職は可能?
仕事をしながら転職を目指す場合は、在職者向けの障害者雇用求人がある転職サイトを活用しましょう。例えば、Kaienには障害者向けの転職サイト「マイナーリーグ」というサービスがあります。
マイナーリーグは強みや専門性を生かせる求人が多いのが特徴で、専門スキル求人も取り扱っています。有名大手企業も多数参加しており、各社の人事担当者をゲストに迎えたオンライン採用説明会の開催があり、応募前に企業に質問できるのも強みです。
さらに、求人に応募するときは業務速度や電話対応、業務外の付き合いといった、配慮事項のすり合わせもできます。自分では聞きにくい点も調整できるので、求人とのミスマッチが心配な方にもおすすめです。
強みや専門性を活かせる障害者向け転職サイト「マイナーリーグ」
発達障害の方の就職事例
発達障害の方の就職事例を紹介します。自己分析や企業選び、面接対策などの就活における取り組みや、就職後の仕事の内容など、さまざまな点について具体例がわかるため、ぜひ参考にしてください。
ASDの方の事例
40代後半で、IT系の専門職に障害者雇用で就職したOさんのケースです。
Oさんは、リハビリ士として医療機関で働いていた折に、ASDと診断を受けました。苦手なことは、マルチタスクや臨機応変な行動、口頭指示、感情のコントロールなどです。臨機応変な対応を求められる医療業界には向いていないと感じ、転職を決意しました。
その後、Kaienの就労移行支援の職業訓練で「自己分析」「グループワーク」「パソコン訓練」に取り組みました。訓練を通じ、自分の持ち味や活かし方がわかり、システム関連の仕事に興味があったこともあり、IT業界を目指すこととしたそうです。
IT業界の複数企業に応募し、面接前にはKaienのスタッフと想定問答を作って練習をし、面接に臨みました。苦手な口頭でのやり取りも、十分な練習をしていたことでクリアできました。
希望していた企業に就職ができ、現在は、AIが作った文章のチェック作業やパスワードの発行代行などの仕事に従事しています。
自己分析が、自分を知るきっかけに!Oさんが“第一希望の会社”に就職できた理由 –
ADHD/ASDの方の事例
30代で、IT業界に勤めるAさん(仮)のケースです。
Aさんは、大学院で、教員からアカデミックハラスメントを受け、抑うつ状態となり、休学を余儀なくされました。当時から「人と違ってうまくいかない」と感じており、その後、ASDとADHDの診断を受けました。診断後も、どのように自分を活かすべきかがわからず、社会との接点を持つことが難しく感じていたそうです。
Aさんは、自分の特性を理解し、どう活かすかを探るため、Kaienの就労移行支援を利用しました。興味を持ったクリエイティブコースで、VBA(Visual Basic for Applications)を学び、論理的思考を発揮できる場面が多いことに気付きました。
この気づきにより、障害者雇用でIT企業の事務職に絞り、就職活動を行う際のアピールポイントとしました。現在は企業の情報システム部門で社内ツールの開発に携わっています。
発達障害の方が就職・転職活動中に受けられる経済支援
ここでは、中長期的にお金を受け取れる可能性がある経済支援を3つ紹介します。
- 傷病手当
支給額は基本的に給与の3分の2で、受け取れる期間は最長1年6ヵ月まで。失業保険(雇用保険)との同時利用はできない。 - 失業保険
働いていたときの給与額の5〜8割程度が支給される。障害がある場合は「就職困難者」として最長で360日まで給付日数が延長される。心身の障害で離職した「特定理由離職者」は3ヵ月間の給付制限が免除される。 - 障害年金
病気やケガにより生活や仕事などが制限される場合に受給できる。現役世代も対象。初診時に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金の対象となる。障害者手帳と別に審査が必要。
なお、これらの他にも住居確保給付金や総合支援資金といった給付金・貸付金制度も用意されているので、必要に応じて活用しましょう。また、どうしてもお金のめどが立たない場合は、生活保護の受給も視野に入れておきましょう。
就職・転職活動中に受けられる経済支援については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
発達障害の方の就活・転職におすすめの支援サービス
発達障害がある方を対象にした支援サービスには、以下のような種類があります。
| サービス名 | 就労移行支援 | ハローワーク | 発達障害者支援センター | 障害者就業・生活支援センター |
| 主なサービス | スキルアップ、就職支援、定着支援など | 障害者求人の提供、専門知識を持つ職員による相談受付 | 相談支援、発達支援、就労支援。スタッフによる就労先との連絡調整 | 就業に関する相談支援、準備支援、職務の選定 |
| 利用料 | 世帯収入に応じて算出(無料~月額最大3万7,200円) | 無料 | 無料 | 無料 |
なかでも相談からスキルアップ、就職、職場定着までを一貫して支援してもらえるのが、就労移行支援です。民間が運営している事業所も多く、場所によっては良質な求人を多く持っている場合があるのも魅力的です
Kaienの就労移行支援
Kaienの就労移行支援は、発達障害や精神疾患に理解のある企業200社以上と連携することで、専門性を生かせる求人を多く取り扱っています。
実際に就職に成功した方のうち、コンサル業界が13%、IT・ハイテク業界が10%、金融・保険業界が8%を占めており、月給も3人に1人が20万円以上という高い水準にあります。
また、利用者の就職率は86%と高く、最長3年間の定着支援により就職してから1年後の離職率は9%まで抑えられています。
さらに、100種類以上の実践的な職業訓練や、50種類以上の社会スキル・自己理解講座があり、スキルアップや障害理解を深めることも可能です。多くの場合、自己負担なしで利用できるので、新たな一歩を踏み出したい方はぜひ気軽にご相談ください。
Kaienの自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)とは、生活リズムや生活習慣の改善、コミュニケーションなどソーシャルスキルの習得、ライフプランの相談などを目的とするプログラムです。プログラムは大きく以下の4種類に分けられています。
- 障害を理解しよう
自分の特性を理解すると共に周囲への配慮要求の仕方を学ぶ - 自立生活をしよう
一人暮らしでも安定して生活できる知識やスキルを学ぶ - 進路を選択しよう
自分の将来のために、今後考えられる選択肢や判断方法を学ぶ - みんなと暮らそう
職場や地域の人たちと一緒に暮らすための学習やロールプレイなど
移行までの期間は平均9.5ヵ月で、修了者の52%が就労移行支援へ進んでいます。就活に向けた準備段階の場として利用するのもおすすめです。なお、多くの場合無料で利用できるので、費用を気にせず自分のペースで進められる点も魅力的です。
発達障害の方の就活は支援機関を活用しよう
発達障害からくる「生きづらさ」は、就職の難易度を高めるだけでなく、ときには自信や自己肯定感にも影響を与えます。しかし、発達障害がある方は自分に合った職場を見つけられれば活躍できる可能性があるので、必要以上に自分を卑下する必要はありません。
就労移行支援を始めとした支援機関を活用し、あなたに適した仕事や職場が分かれば、自分の歩む道や目指すべき場所も開けてくるはずです。
まずは焦らず、自分の特性を知るところから始めましょう。Kaienでは、随時無料で見学会や体験利用を実施していますので、お気軽にご連絡ください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます

監修 : 鈴木 慶太(株式会社Kaien 代表取締役)
元NHKアナウンサー。自身の長男が発達障害の診断を受けたことをきっかけに、米国留学(MBA取得)を経て株式会社Kaienを設立。 「数的な凸凹があっても、強みを活かして働ける社会」を目指し、大人向けの就労支援から子ども向けの学習支援(TEENS)まで幅広く事業を展開している。 経営者として、また一人の親としての視点を交えた発信は、多くの当事者・家族から支持を得ている。
▼ 代表・鈴木に直接質問できるライブ配信も開催中。毎週開催の「Kaienお悩み解決ルーム」ほか、就職や生活に役立つ情報を配信しています。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます