「ASD(自閉スペクトラム症)」と「ADHD(注意欠如多動症)」の違いは医学の定義上は明確です。しかし、ASDとADHDは併発することもあり、専門家でもどちらの診断なのか断定できない場面にしばしば出くわします。
そもそも精神医学では発達障害*¹のメカニズムが完全に解明されておらず、ASDとADHDの診断基準はあるものの、診断やその見分け方については医師によって異なります。そのため、診断の区分けや併発についても微妙に異なる見解がある点に注意が必要です。
診断名にこだわるのではなく、診断の特徴が重なる部分も多いことを理解し、自分はどちらの傾向がより強いのかを把握する程度にとどめておきましょう。この記事では、ASDとADHDの特性の違いや診断基準、判断が難しい理由、発達障害の方が利用できる支援機関などについて解説します。
大人の発達障害とは
大人の発達障害とは、主に大学生以上の年齢になってから気づく発達障害のことを指します。
発達障害自体は先天性であり、脳の機能発達に生まれつきかたよりがあることで、日常生活や社会生活に支障をきたす状態です。子どものうちは特性に気づかなくても、大人になって就職などを機に状況が変わり、生きづらさやストレスを感じることで発覚するケースが大人の発達障害の場合は多くあります。
職場での人間関係や仕事上のミスなど、大人になると発達障害の特性が浮き彫りになる場面が増えるでしょう。発達障害の特性によるストレスなどがうつ病などの二次障害に発展するケースもあるため、適切な方法で対処する必要があります。
まずは、併発の可能性もあると言われている発達障害の「ASD」と「ADHD」の特徴を簡単におさらいしましょう。
大人のASD(自閉スペクトラム症)の特徴
ASD(自閉スペクトラム症)にはコミュニケーションが苦手、独自のこだわり、感覚過敏または鈍麻があるといった特性が見られます。職場でうまくコミュニケーションが取れない、チームで業務を進めるのが難しいといった理由で、大人になってからASDが発覚する例も多いです。
最新の定義とはやや異なりますが一般的に使われる3つのチェックポイントで考えましょう。
- 社会性の難しさ
相手の気持ちをすぐに読めない、新しい環境が苦手、自分視点だけの思い込みが多い、いわゆる空気が読めない等 - 表現・表出の難しさ
すぐに言葉が出ない、書き言葉で話したり喋り言葉で書くなど表現力が乏しい、言葉の定義が狭く周囲とのやりとりがずれやすい、いわゆるコミュニケーションが苦手等 - こだわりの強さ
好き嫌いが極端、自分のルールを曲げられない、ルーティン通りにしないと不安等
大人のADHD(注意欠如多動症)の特徴
ADHDは「注意欠如多動症」といわれます。注意関心が散漫だったり、身体の多動が見られたりという状態です。大人になるとほとんどの人は多動性は収まりますので、注意欠如の部分のみが残ることが多いでしょう。一般的には、以下の二つに分けて考えると分かりやすいと言われています。
- 不注意優勢型
物をなくしやすい、ミスが多い、気が散りやすい、過集中で切り替えが難しい、段取り良くできない等 - 多動 / 衝動性優勢型
思いつくとすぐに行動する、順番を待てない、人の発言に割り込む、一方的に喋る等
【項目別】ASDとADHDの特性の違い

ここからは、以下6つの項目別に、ADHDとASDの違いを詳しく解説します。
- 仕事
- 集中力の持続
- 対人関係
- 計画性・計画的な行動
- 整理整頓
- 感覚に対するこだわり
ASDやADHDの特性の現れ方には個人差があり、必ずしも当てはまるとは限りませんが、大まかな傾向や起こりがちなトラブルを知る上で参考にしてください。
仕事に関する違い
ASDの場合は繰り返しの作業など規則性のある仕事を好み、作業の一部分にこだわって熱中しやすい傾向があります。一方で、アイデアを提案することや優先順位を付けて計画を立てることに苦手意識を持ちやすいでしょう。
また、人の表情や言葉のニュアンスから感情を汲み取ることが困難なため、職場の人間関係に悩むケースも見られます。
ADHDの場合、不注意や衝動性によるケアレスミスが目立ちやすい傾向があります。また、面倒だと感じたことや苦手な仕事を後回しにしてしまい、期限に間に合わなくなることもあります。
計画的なタスク管理や、同じ作業を継続的に繰り返す作業に苦手意識を持つ人も多く見られます。
集中力に関する違い
ASDの場合は、興味があるものや好きなことに対するこだわりが強いために、特定の物事に集中して取り組み続けるケースが見られます。
また、同じ作業や行動を繰り返すことに安心感を覚えやすく、ルーティン的に続けやすいことや規則性のあるものに対して特に高い集中力を発揮する人もいます。
一方、ADHDの場合は、強い関心のあることには非常に集中しますが、飽きるのも早く、興味の対象が次々と移り変わっていく傾向があります。そのため、一つのことに集中し続けることを苦手とするケースも少なくありません。
対人関係に関する違い
ASDの場合、他人の気持ちを汲み取ることを苦手とするため、場違いな発言や失礼な態度によって不本意に相手を怒らせてしまうことがあります。
また、人との適度な距離感がつかめず関係性が深まらない、あるいは反対に馴れ馴れしすぎて警戒されてしまう、といった悩みを持つ人もいます。
会話の細かいニュアンスや行間を読み取ることができず、雑談のようなコミュニケーションが苦手で、対人関係を築くことに困難を生じる場合があります。
ADHDの場合、遅刻やうっかりミスなど忘れっぽい特性により人を怒らせてしまうことがあります。
また、「衝動性が抑えられずに一方的に話し続けてしまう」「相手が話しているときについ遮ってしゃべり出してしまう」など、適切なコミュニケーションが取れないために関係構築が困難になっているケースも見られます。
計画性・計画的な行動に関する違い
ASDの方は規則性を好むため、計画的な行動やあらかじめ決まっている通りに行動することは比較的得意とされます。
ただ、優先順位を考えることや、他者の意向を汲み取って計画を立てることは苦手とし、急なハプニングや予定変更に対応することに不快感を覚えやすく、困難を感じる傾向があります。
一方、ADHDの方は物事を計画的に進めることを苦手とし、その場の思いつきによる衝動的な行動が目立ちがちです。スケジュールや計画に従うことを不得意とする傾向があります。
整理整頓に関する違い
ASDの場合、モノに対して強い思い入れや好みを持つことが多く、ものを捨てることを極端に嫌がる傾向があります。また、散らかっている部屋に見えても、本人にとっては規則性があり、何がどこにあるか把握できています。
一方、ADHDの場合は注意力が散漫になりやすく、整理整頓が苦手な傾向があります。注意力が散漫になり、何かをやりっぱなしのままその場を離れる、散らかしたまま放置する、といったことも多く、結果的に忘れ物やなくし物が増えてしまいます。
感覚に対するこだわりの違い
感覚に対するこだわりは、ASDに強く見られやすい特性です。ASDのある方は感覚過敏のケースが多く、五感のいずれかが過敏になっているか、反対に特定の感覚の鈍さが見られる感覚鈍麻を抱えています。
そのため、感覚に対する強いこだわりがあるケースが多く見られます。聴覚過敏の場合、駅のような人混みや職場、教室などで過ごすことに苦痛を感じる人もいます。
一方、ADHDのみを持つ人の場合は、ASDのような感覚へのこだわりは少ない傾向にあります。
ASDとADHDの診断基準とは?

ASDとADHDは、いずれも医師が最新の診断基準「DSM-5※」に基づいて診断を下すことが多いのですが、当然ながら診断基準にも違いがあります。ここでは、ASDとADHDそれぞれの診断基準について解説します。
なお、発達障害の最新の診断基準は2022年刊行の「DSM-5-TR」です。DSM-5-TRでは、DSM-5の刊行以降に収集された膨大なデータに基づいて、診断名や診断基準などを改定しています。
また、先述したように精神医学では医学的に発達障害のメカニズムが解明しつくされてはいません。ASDとADHDの診断基準はあるものの、医師によって診断や見分け方は異なります。発達障害については、診断の区分けや併発において医師により微妙に異なる見解があることを念頭に置いておきましょう。
※DSM-5 =「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版」アメリカ精神医学会作成
ASDの診断基準
最新の診断基準(DSM-5)によるASDの診断では、以下の4つの基準を満たした際にASDという確定診断が下せるとしています。
- 社会でのコミュニケーションや対人交流の持続的な障害
- 限られた反復されるパターンの行動や興味、活動
- 症状が早期の発達段階までに発現していなければならない(ただし、社会的な要求が限られた能力を超えるまですべてが現れないかもしれない。もしくは後天的に学んだ対処法で見えなくなっているかもしれない)
- 症状によって、社会生活や仕事、または他の重要な分野で臨床的に重大な機能障害がある
「社会でのコミュニケーションや対人交流の持続的な障害」には、人との関わり方やコミュニケーションの取り方の偏りや、人間関係の構築、人との交流への極端な興味関心の欠如といったものが含まれます。
なお、DSM-5-TRではこの「持続的な障害」について、以下に挙げるようなすべての特徴に該当する場合にASDと診断できるとしています。なお、以下に挙げるのはあくまで典型的な例であり、すべてが網羅されているわけではありません。
- 通常の会話のやり取りができない
- 愛情を他人と共有できない
- 異常なアイコンタクトやボディランゲージがある
- 社会的場面にふさわしく行動するのが難しい
「限られた反復されるパターンの行動や興味、活動」は、型にはまった体の動きや発話、同一性へのこだわりといった4つの項目のうち、最低2つ以上当てはまっている必要があります。
ADHDの診断基準
DSM-5におけるADHDの診断基準では、「不注意傾向」と「多動性/衝動性傾向」の2つの軸があります。それぞれの具体的な項目は以下の通りです。
【不注意傾向】
以下の項目のうち、5つ以上当てはまる状態が6ヶ月以上ある場合。
- 細かい注意を払うことができない
- 不注意から失敗することがよくある
- 注意を持続し続けることが難しい
- 話しかけられても、聞いていないように見える
- 指示されたことをやり遂げることが難しい
- 順序立てて課題を進めることが難しい
- 継続して課題に取り組むことが難しい
- 必要な物をなくしやすい
- 関係ないことで気が散ることが多い
- 忘れる、抜け漏れることがある
【多動性/衝動性傾向】
以下の項目のうち、5つ以上あてはまる状態が6ヶ月以上ある場合。
- そわそわと手足を動かす、座っていてももじもじ動いてしまう
- 着席し続けることが難しく、席を離れてしまう
- じっとしていられないような気分になる
- 遊びや余暇活動に静かに取り組むことが難しい
- 勢いよく行動し続ける、じっとしていると落ち着かない
- しゃべり過ぎることが多い
- 相手の話が終わる前に話し始めてしまう、相手の言葉を先取りしてしまう
- 他の人の活動を遮ってしまう
ASDとADHDは併発・合併することもある
ASDとADHDの特性の現れ方は個人によって大きく異なりますが、ASDとADHDが併存するケースも少なくありません。というのも、発達障害の症状は診断名によって明確に区分できるものではなく、併発していることがよくあるからです。
また、先に紹介したように、ASDとADHDとでは似ている症状や特性が多いため、双方が合併しているケースも認められます。ちなみに、以前はASDとADHDの併存が認められていませんでしたが、DSM-5から認められるようになりました。
ADHDとASDが併発・合併している場合、本人の社会適応度が大きく低下しやすい傾向があります。例えば、「不注意でミスが多く、コミュニケーションが苦手」となると、チームワークが重要視される環境では周囲の人と協力的に仕事を進めることは難しいでしょう。
どちらか一方の障害がある人よりも、両方の特性を持つ人の方が、社会に適応するのが難しく、より困りごとが多くなりやすいといえます。
厚生労働省の報告によると、ある調査では発達障害の診断を受けた方838名のうち、ASDとADHDの合併の診断を受けた方が225名で、全体の26.8%でした。
この調査では、ASDとADHDを併発している方は、ASD・ADHD単独の診断を受けた方に比べて、全体的にうつ病などの精神疾患や突発性難聴などの身体疾患を合併する割合が多いという結果も得られています。
出典:成人の発達障害に合併する精神及び身体症状・疾患に関する研究
ASDやADHDの方によく見られる併存症
ASDの方は約70%以上が1つの精神疾患、約40%の人が2つ以上の精神疾患があると言われています。併存症としてADHDだけでなく、知的障害やうつ病、統合失調症、強迫症、社交不安症などが多く挙げられます。また、身体症状として便秘やてんかん、睡眠疾患なども併発しやすいことが知られています。
ADHDについてはASDのほか、SLD/LD(限局性学習症/学習障害*²)やチック症、うつ病、双極性障害、不安症、反抗挑発症などの併存が多いです。ADHDの中でも、特に不注意優勢型の場合はSLD/LDの併存率が高いとされています。
ASDとADHDの判断が難しい理由
実はASDとADHDは様々な共通する特徴があり、専門家でも見極めは難しいものです。専門医など発達障害の人に接すれば接するほど、本当に二つは違う特性なのかと定義を改めて検討し始める人も多くいます。なぜ判断が難しいのか、具体的な事例3つを基に考えてみましょう。
ミスが多い
ミスが多いというのは確かにADHDの特徴になります。それは注意の切り替えがうまくいっていないため、抜け漏れやうっかりが多いからです。例えば、商談で提出するはずの重要な書類を机の上に準備したのに、隙間時間でメールを読んでいるうちに書類の存在を忘れてしまい、打ち合わせの場で上司に怒られてしまった、などです。
しかし、ミスはADHDの専売特許ではありません。ASDでもミスは頻繁に起こりえます。たとえば、臨機応変に質問ができず、上司から言われた内容を勘違いしたまま作業をして、後でミスを指摘されるというような状況です。つまりミスをしたという表面的な部分だけをみるのではなく、原因と状況を深く考えないと、それがADHD的なミスなのか、ASD的なミスなのかわかりにくいわけです。
空気が読めない
空気が読めないのはASDの典型例と言われて来ました。確かにそういう部分もありますが、ASDでも空気を読むことができる方もいます。また、空気を読むことに苦手さを感じているからこそ、空気を読もうと人一倍努力して疲れている人もいるでしょう。
周囲に順応するために必要以上に努力する状態のことを「過剰適応」といいます。自分の考えや行動よりも他人を優先し、気を配りすぎてしまう状態です。過剰適応はグレーゾーン、いわゆる薄い自閉の方に多いといわれており、過剰適応によるストレスによってうつ病などの二次障害につながる恐れもあります。
一方で、ADHD的にも「この人空気読めていないな」という印象を持たれやすい場面はあります。
ADHD的なケースとして、人が発表をしている時に、質疑の時間ではないが気になったことを次々に質問して場の進行を大きく妨げてしまったり、みんなで集団行動をしているのに道の雑踏に気を取られて周囲から「聴いてる?ぼーっとして自分の世界にいたよ」等というようなことを言われてしまうことが頻繁にあったりする人は、ADHD的に空気が読めていないと考えることもできるでしょう。
確かにADHD的な空気の読めなさというのは冷静に考えると分かる、とか、わざと空気を読まないでやっているんだ、という主張が当てはまりそうな場合や状況ではあるのですが、それでも周囲からすると、もう少し全体感を理解してほしいな、自己中心的に見えるな、という状況には変わりありません。
ASDの中にはその人の努力や対策によって、人の気持ちをある程度読むことができ、気配りも丁寧にできるため、常識的にも思われる人も少なくないです。特に女性や知的に高い方にそのようなタイプが多いと言われています。そのような人の中には「人からどう見られるか」を気にしすぎてしまう、過剰適応タイプの人もいます。過剰適応タイプは、強迫症や社交不安症との合併が考えられるかもしれません。
こだわりの強さと切り替えの難しさ
こだわりの強さはASD的(自閉スペクトラム症)、一方で切り替えの難しさはADHD的(注意欠如多動症)です。しかし、これらは混同されることが多いのが実際です。
例えば、スマホにはまっている人を考えましょう。いくら言ってもスマホのゲームの課金をしている状態です。この場合、本当にそのゲームが好きで、自分の損得がわからずはまっている状態だからこだわりと言えるでしょうか?おそらく違います。発達障害の面から説明するとADHD的のほうがありえるでしょう。つまり何か始めてしまうと切り替えが難しく次の行動や考えに移りにくいということです。
ADHDの方は、興味のあることに集中しすぎてしまう「過集中」を起こすことがしばしばあります。特に「不注意優勢型」の場合は、切り替えのタイミングがわからずに同じ作業をやり続けてしまい、生活に支障をきたすケースも多いです。
ASD的なこだわりは、肌ざわりへのこだわりから汚くなっても同じ服を着続けるとか、パソコンを片付ける時にマウスの置き方にこだわって誰かが触ると不快感を強く示す、などであり、こういったこだわりはADHD的には説明しづらいものです。ただし専門家ではないとこのようにこだわっているのか、それとも単に切り替えが苦手なのかも、取り違えられてしまう可能性があります。
脳の働きが解明されていないため発達障害の診断は困難
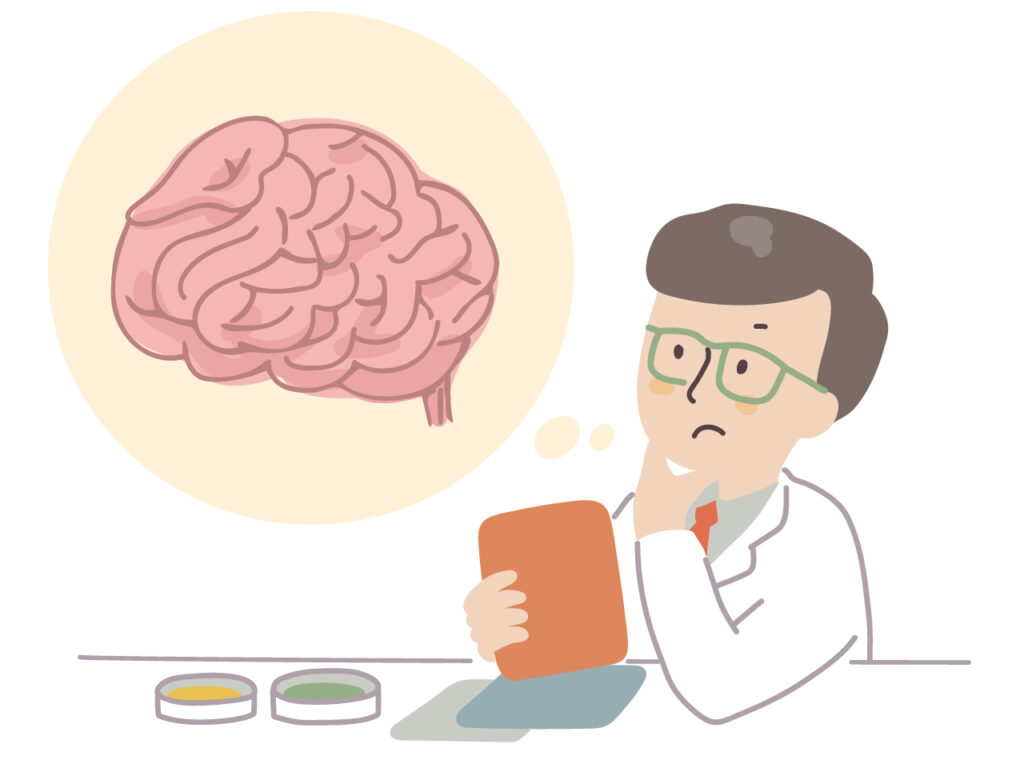
どうしてここまで判断が難しいのか?それは難しい話を少しだけすると、ASDであれADHDであれ、前頭前野という脳の部分に関わっている、つまり実行機能という判断や行動をつかさどるところが他の人と違うから、ということになるでしょう。
「想像」、「こだわり」、「切り替え」、「段取り」、「不注意」、などという点は、ほぼすべて前頭前野の機能が関係しています。もっとも、すべての脳機能が解明されているわけではありません。「想像が弱いからこだわりがある」、「こだわりがあるから段取りが苦手」、「想像が乏しいから切り替えが弱い」、「不注意があるから無くそうとしてこだわりがより強くなる」など、原因と結果の因果関係が絡まり合ってしまい、専門家でもなんだかわからなくなってしまうのが実状です。
違う言い方をすると、ADHDっぽいからASD的にも見えますし、ASD的だからADHDの要素も見えやすくなるかもしれません。ですので、ASDもADHDもまとめて発達障害特性を持っているという大きなくくりで捉えたほうが良い場合もありそうです。
結局、ADHDやASD特性の背景にある脳機能の解明がいまだ不十分なため、診断の困難がつきまとうのです。
どうしても見極めたいときは専門機関で診断を
そうといっても、よりASD優位なのか、ADHD優位なのか、見定めたい人はいるでしょう。その時の方法としては、やはり専門家に訊くということになります。専門医は数百、数千の症例を見ています。ミスの原因をしっかりと分析したり、他の人の事例と比較をすることで、ASD的に考えたほうが良いのか、ADHD的に考えたほうが良いのか、きちんと答えを出してくれる医者・専門家が多いでしょう。ただし、医者や専門家によって、診断基準にどのくらいの強さの症状で当てはめるのかという基準(閾値といいます)が異なっているので、その点は留意する必要があります。
なお、専門家が判断するには、①症状が幼いころから継続しているか、②IQテストなど脳機能に凸凹が見られるか、③AQテストやADHDチェックリストなどで高い点数が出るか、などを複合的に判断します。特に③の部分は自分である程度は確認できる部分ですので、診察前に自己チェックをされることもよいでしょう。
また、薬の効きやすさというのもポイントと言えます。ADHDには治療薬が出ています。服薬で根源的に解決するということは無いようですが、ある程度生きづらさが改善することが多いようです。例えば集中力が維持できるようになったとか、イライラが抑えられることが多くなったなど、そのような生活の質の向上です。
一方でASDには、周辺症状への緩和の薬はあるものの、根源的な部分を解消する薬はまだ開発されていません。たとえば相手の気持ちに共感しやすくするとか、言葉や表現が滑らかになる薬がないということです。つまりすでに発達障害の診断を受けて薬を服用している場合、特にADHDに対する薬の効果がある程度出た場合はADHD的な要素は少なくともあるということでしょう。
ただし、薬には副作用もあり、どの薬がいいのかなど自分勝手に判断して、医師の指示に従わずに服薬することは絶対に避けましょう。ADHDとASD、どちらの症状かなと勝手に判断して医者の指示に従わずに服薬するのは絶対によしましょう。
またADHDの症状が明らかに強くてもお薬が効かない場合も多数あります。ですので、お薬が効かないからASDというわけでもありません。あくまでお薬が効いたということはADHDの傾向が強い可能性があるな、という判断材料の一つにしてください。
ASDの方向けの就活支援とADHDの方向けの就活支援
Kaienでは、自分の特徴・強みを生かして就職を目指す就労移行支援や、自立に向けた基礎力を上げる自立訓練(生活訓練)、また学生向けのガクプロというセッションを運営しています。それらの中でASD向け、ADHD向けに対応は”若干”変えることがあります。
ASD的な困難さには予習で、ADHD的な困難さには復習で、支援を行っています。
具体的に考えてみましょう。例えば、ASD的な困難さの一つである、想像の苦手さ。職場で上司やお客様の意図がつかみづらい人は、事前に対応方法をインプット(予習)して練習を繰り返します。一方でADHD的な困難さの一つである、衝動性について、職場で距離感がつかみづらく迷惑がられてしまう人は、同じような失敗を就労移行支援や自立訓練(生活訓練)で出てしまったときに復習として振り返ることが多くあります。
ただし、予習的・復習的というのはあくまでも支援の大きな方針です。ASDの方もADHDの方も、生きづらさを軽減するうえで専門機関の支援が役に立つという点では変わりません。就労移行支援や自立訓練(生活訓練)などの福祉サービスを利用して、将来の可能性を広げてみてはいかがでしょうか。
次からは、Kaienの就労移行支援と自立訓練(生活訓練)について詳しく紹介します。
Kaienの就労移行支援
Kaienでは、一般企業での就労を目指す障害のある方に向けて、就労移行支援サービスを実施しています。
Kaienの就労移行支援の魅力は、充実したプログラムです。実践的な職業訓練を通して自身に合った職業が見極められ、講座形式のセッションで自己理解を深めたり、社会スキルを向上させたりすることができます。発達障害に理解のある企業と提携しており、就職先が見つかりやすいこともポイントの1つです。
Kaienの利用者の就職率は86%で、過去10年で約2,000人が一般企業での就業を実現しています。1年後の離職率も9%と他社に比べて低く、カリキュラムや定着サポートの効果が数字に表れています。
一般企業で働きたいと考えている方は、ぜひKaienの就労移行支援をご利用ください。
Kaienの自立訓練(生活訓練)
自立を目指す方にはKaienの自立訓練(生活訓練)の利用がおすすめです。数千人への支援を基に厳選したスキルが習得できるよう、実践的なプログラムを用意しています。
講座では生活スキルやコミュニケーション、発達障害の特性、進路選択などについて学び、健やかに人生を送るための基礎を構築します。
そのうえで、2~8週間かけて学んだソーシャルスキルを実践するのがマイ・プロジェクトです。社会で暮らすための練習や将来に向けての話し合いなどを通して、ソーシャルスキルへの理解を深めていきます。
最後のステップでは、担当スタッフとのカウンセリングで生活を振り返ったり、将来に活かせる強みを一緒に探したりします。発達障害で生きづらさを抱えている方は、Kaienの自立訓練(生活訓練)をぜひ利用してみてください。
ASDとADHDは重なる部分が多く併発も起こり得る
ASDとADHDにはそれぞれ異なる診断基準が設けられていますが、両者には重なる部分も多くあります。併存している場合もあるため、診断名にとらわれすぎないことが大切です。また、ASDやADHDは二次障害としてうつ病や不安症などの併存症があるケースも珍しくありません。
自分の状態を正確に把握したい場合は、専門機関で診断を受けるとよいでしょう。就労移行支援などの福祉サービスを活用し、自己理解を深める方法もおすすめです。
Kaienの就労移行支援や自立訓練(生活訓練)では、無料で見学会や体験利用を実施しています。気になる方はぜひお気軽にご連絡ください。
*1発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
*2学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます
監修者コメント
ASDとADHD、診断基準は明確に分けられていますが、現実には一個人の個性/特性がそこまで明確に分けられるわけではありません。どちらの要素が強いかという差を考えたときに、より当てはまる方に診断がついたり、どちらの診断もつく、ということにもなります。実は以前は小児科医と大人の精神科医で見解が異なることが多くありました。小児科医の多くは「ASDとADHDは併発が中心で特に単独のADHDは少ないよね」と語り、大人の精神科医は「どちらか単独診断の方も多いよね」と語っていたものです。今から考えれば、併発していると小さい頃から特性が周囲から見てわかりやすく顕在化していることが多い、ということでしょう。「上手く行かない部分」がASDやADHDといった発達特性があるかの視点から見ると対策がわかりやすいときは確かにあります。生活の困難さが自分の中にあると感じられたときには、身近な支援者にどう考えると対策が立てられるのか、尋ねてみると良いかもしれません。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189
