発達障害*¹は大きく分けるとASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、SLD*²(限局性学習症)の3種類があります。しかし、これらの診断名は度重なる区分や診断名の見直しが行われたため、正しく理解されていないことも少なくありません。
そこで本記事では最新の診断基準である、アメリカ精神医学会による診断基準のDSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル)とWHO(世界保健機関)による診断基準のICD-11(国際疾病分類)に基づき、正しい診断名や診断基準の変化のポイントについて解説します。
自閉スペクトラム症と広汎性発達障害、アスペルガー症候群の違い
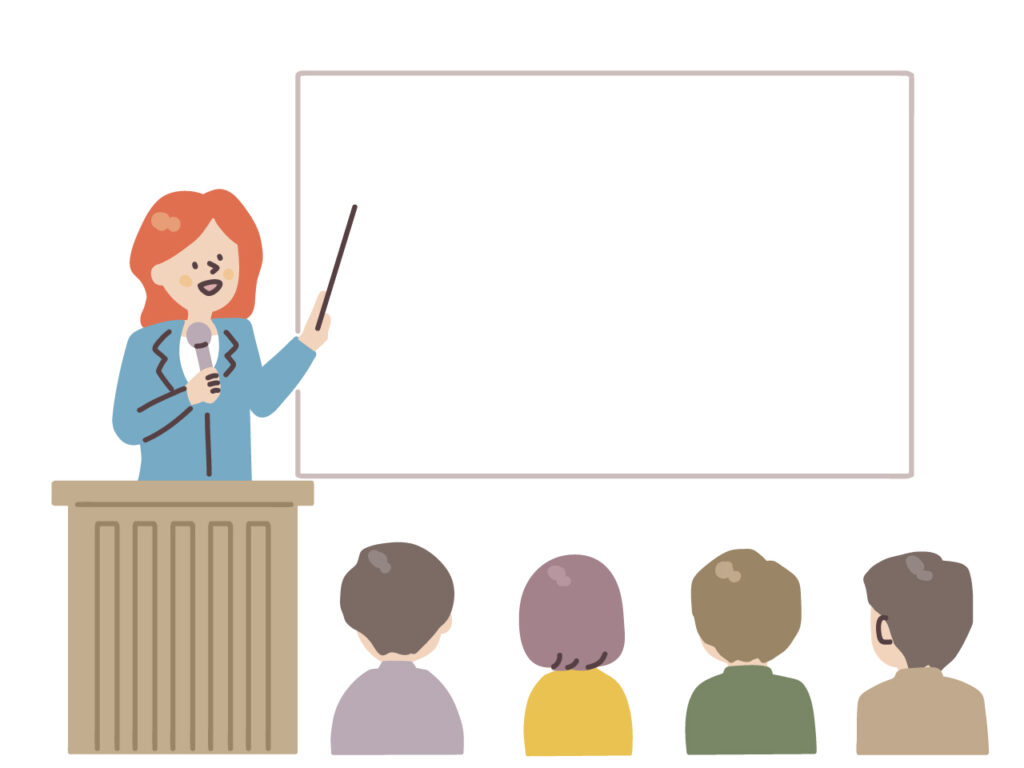
まずは、「自閉スペクトラム症(ASD)」と「広汎性発達障害(PDD)」、「アスペルガー症候群」の診断名の違いを整理しておきましょう。これらは現在使われている診断名と、過去に使われていた診断名が混在しており、それにより理解が難しくなっています。
日本で発達障害の診断基準として使われているのは、世界保健機関(WHO)が公表している「国際疾病分類(ICD)」と、アメリカ精神医学会が公表している「精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)」の2つです。
日本における発達障害の診断基準は以下の2つ
診断基準 公表機関
国際疾病分類(ICD) 世界保健機関(WHO)
精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM) アメリカ精神医学会
現在使われている診断名は、上記の中では自閉スペクトラム症のみです。広汎性発達障害とアスペルガー症候群は過去に使われていた診断名となります。過去には広汎性発達障害の中に自閉症やアスペルガー症候群などが含まれていましたが、2013年に公表された「DSM-5」では細かい分類をなくし、「自閉スペクトラム症」という大きな1つのくくりにまとめました。また2018年6月に公表された「ICD-11」でも同様に「自閉スペクトラム症」にまとめられました。
日本における発達障害の診断基準

日本では発達障害の診断基準として、WHOによる診断基準であるICD(国際疾病分類)と、アメリカ精神医学会による診断基準のDSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)の2種類が用いられています。
両者の間に優位性はなく、また、診断基準は大きなズレが生じないように構成されています。では両者にどのような違いがあるのか、それぞれの特徴や主に使われる場面などを見ていきましょう。
国際疾病分類(ICD)
WHOによるICD(国際疾病分類)は世界中で使われている診断基準です。約18,000もの分類項目数が掲載されており、世界中のあらゆる病因や死因の分析が可能です。都度改定されており、現在は第11回改訂版のICD-11が最新です(2024年6月時点)。
世界的にスタンダードな診断基準なので、日本においては医療機関の診断の参考に使用されるほか、行政機関で用いられることも多いです。例えば、障害者手帳の取得手続きや発達障害者支援法に基づく支援対象者の定義付け、厚生労働省の人口動態調査などの統計調査といった場面などでICDの診断基準が用いられています。
精神疾患の診断・統計マニュアル(DSM)
DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)はアメリカ精神医学会という一国の組織が定めた診断基準ですが、ICDと同じように国際的な診断基準として用いられています。1952年に初版のDSM-Iが出版され、改定を重ねて現在はDSM-5-TRが最新版です(2024年6月時点)。
扱っている内容は精神疾患のみで、精神疾患を大カテゴリー、カテゴリー、サブカテゴリ―、細分化により体系的に分類しています。
日本においては医療分野で用いられることが多く、多くの精神科医が診断の際にDSMを参照しています。
ICD-11における神経発達症群(発達障害)の診断
ICD-11において、発達障害は神経発達症群に分類されます。神経発達症群の項目には、ASDとADHDの診断基準が掲載されており、それぞれの診断基準は以下のとおりです。
- ASD
「社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥」と「行動、興味、または活動の限定された反復的な様式」の2点を軸として診断される。詳細には、複数の具体的な症例によって判断され、症状の程度も加味される。
- ADHD
主な診断基準は、不注意症状と多動性・衝動性症状の組み合わせが、年齢や知的発達レベルから予想される正常範囲を超えた状態が6ヶ月以上続いていること。ASDと同じように、複数の具体的な症例によって判断される。
なお、ICD-10ではASDをPDD(広汎性発達障害)、ADHDを多動性障害の診断名で扱っていました。これらを始めとして、ICD-11では区分や診断基準など多くの内容が改訂されています。
DSMにおける自閉スペクトラム症の診断基準の変化
DSMにおいては、DSM-IVまでPDD(広汎性発達障害)の診断名が用いられていましたが、DSM-5からはASD(自閉スペクトラム症)に診断名が変更されました。また、これに併せて診断基準も以下のように3軸から2軸へと統合されました。
診断基準の変化
DSM-IV(1994-2012)
PDD(広汎性発達障害)
- コミュニケーションの障害
- 社会性の障害
- こだわり
DSM-5(2013-現在)
ASD(自閉スペクトラム症)
- 社会的コミュニケーションの障害
- こだわり(感覚過敏・鈍麻含む)
他にも、「DSM-5」からこだわりの中に感覚過敏や鈍麻が含まれるようになったり、これまでは「広汎性発達障害」と「ADHD」の両方が疑われる場合は「広汎性発達障害」を優先して診断していたのが、「自閉スペクトラム症」と「ADHD」は併存していると診断できるようになるなどの変更がありました。
DSM-5-TRにおける自閉スペクトラム症の診断基準の変更点
DSM-5-TRとは、2022年に出版されたDSM-5の改訂版です。日本では2023年6月に日本語訳本が改訂となり、この改訂によりICDと同様に、発達障害から神経発達症に用語が変更されました。また、神経発達症(発達障害)の診断基準や診断名にも以下のような変更が加えられています。
※発達障害は現在、「神経発達症」に名前が変更されていますが、最新版『DSM-5-TR』以前の名称である「発達障害」といわれることが多くあるため、ここでは「発達障害」と表記しています。
- ASD
病名を「自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害」から「自閉スペクトラム症」に統一。
「複数の状況で社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応における持続的な欠陥」の具体的な症例を追加。診断的特徴に、認知機能や言語の障害を伴わない場合、欠陥を隠すために多大な努力をしている可能性があることなどを追記。
- ADHD
病名を「注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害」から「注意欠如多動症」に統一。 - SLD
病名を「限局性学習症/限局性学習障害」から「限局性学習症」に統一。
なお、行政・法律分野で使われている用語は、医療分野よりもワンテンポ遅い現状があります。例えば神経発達症(発達障害)は、行政分野ではいまだに発達障害という言葉が使われています。
また、医療の分野ではICD-11が用いられているものの、行政の分野ではいまだに旧版のICD-10が用いられてることが多いです。
この差を理解しておかないと、医療機関を受診するときと行政手続きをするときとで診断名などにギャップを感じる可能性があります。前提知識として頭に入れておきましょう。
障害特性でお困りの方の相談や支援はKaienへ
発達障害の特性は仕事における自己評価を下げる原因にもなり得ます。発達障害と向き合っても、特性と仕事が合わないと、実力を十分に発揮できないかもしれません。
そんな悩みを解決するために、Kaienでは精神医学や発達心理学に基づいた就労移行支援や自立訓練(生活訓練)を行っています。
就労移行支援とは、障害がある方を対象に職業訓練や就活支援、定着支援などを行い一般就労を目指す障害福祉サービスです。特性への向き合い方や適した仕事などを理解することで、より良い環境での就労を目指します。Kaienが就職をお手伝いした人数は過去10年間で約2,000人。就職率86%、給与額は3人に1人が20万円以上と高い水準になっています。
まだ働く気持ちになれない、生活習慣が乱れているという方は、ソーシャルスキルを習得して自立を目指すKaienの自立訓練(生活訓練)がおすすめです。
発達障害がある方に必要なのはさらなる努力や配慮ではなく、特性の正しい理解と適した職場を見つけることです。もしあなたが生きづらさを抱えているのであれば、一度Kaienにご相談ください。あなたが輝ける場所を一緒に探しましょう。
発達障害の診断名や診断基準は時代とともに変遷する
発達障害に含まれるASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如多動症)、SLD(限局性学習症)は、度重なる定義の見直しが行われてきたことから、時代によって診断名や診断基準が異なります。
現在、診断にはDSM-5-TRとICD-11が用いられていますが、いまだに前世代の呼び名が用いられることもあり、正しい情報が分かりにくくなっています。
発達障害への理解はいまだ道半ばです。今後も診断名や診断基準が変わる可能性があるので、最新の情報を積極的に取り入れていきましょう。
*1発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
*2学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます
監修者コメント
自閉圏の診断名は本記事にある通り揺れています。診断基準が改訂される度に名称に変化があります。我々医療者はその理由も含めて事前に色々と聞いたり調べたりした上で名称変更の時を迎えますが、一般の方は混乱されているのでは、と推察します。さて、アメリカの精神医学会診断基準であるDSMの記述を私達医療者はよく使っているのですが、DSM-IVからDSM-5への改訂(数字表記、違うぞと思うかもしれませんが、この通りです)にあたり、自閉圏診断は非常に大きく変わりました。細かい分類から、共通性質を包含してまとめたと言って良いかと思います。例えば、以前あった「アスペルガー症候群」の呼称は一般にも流布しましたが、今回は消えています。理由としては幾つかあるのですが、DSM-IVで細かく分類しても、実際に多かった診断名は「特定不能の広汎性発達障害」であり、細かい分類よりは現在のスペクトラム的な捉え方のほうがしっくりくるというのが1つあるでしょう。もう1点は、かつてはナチス・ドイツから自閉症児への迫害をかばったというアスペルガー医師への認識が、現在では大きく悪い方向に変わったということもあります。いずれにしても、医療者もまだまだ発達障害的な特性をどのように捉えるか勉強中であり、今後も名称は変わっていくでしょう。その是非はまだ評価できないと正直思いますが、実際に変わった名称に慣れていくしかないですね。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189