診断書は、休職や福祉制度の利用、保険の手続きなどに必要な公的書類です。医療機関で医師に相談し、症状や状況を把握した上で作成を依頼しますが、診療するだけで診断書を出してもらえるか不安な人もいるでしょう。
本記事では、診断書とは何か、記載される項目、診断書が必要になるシーン、作成を依頼する方法などを詳しく解説します。また、診断書がもらえないケースや有効期限切れなどの注意点と、診断書に関してよくある質問などについても取り挙げて解説しています。
必要な診断書をスムーズに作成してもらうために、ぜひ参考にしてください。
診断書とは
診断書とは、医師が作成する公的書類の1つで、患者の診断内容や症状についての所見などを記載します。医師法にて、診察した医師のみが診断書を作成できることが定められています。
広義の意味では「証明書」と書かれた書類でも、必要な内容が記されていれば診断書として扱われます。診断書には決められた形式がなく、病院や施設によって記載項目や書き方は異なります。
休職や障害や疾患による業務を会社に申請する場合や、福祉制度を利用する際などに診断書の提出が必要です。
診断書の項目
診断書に記載される主な項目は、以下があります。
- 患者情報(氏名、生年月日、年齢、住所、性別など)
- 病名(診断名)
- 受診日
- 発症日
- 治療内容
- 治療の見込み期間
- 治癒日(死亡・出生年月日など)
- 問診内容(既往歴、主訴、現病歴など)
- 身体所見および検査結果
診断書の項目は決まっているわけではないため、本人の意向を書面に反映する場合もあります。また、提出先や使用目的によっては省略されることがありますが、反対に特別に記載を求められる内容もあります。
例えば、休職のために職場に提出する場合は、就労の可否や病状を必要とするケースが多く、医療保険の利用が目的であれば、手術内容や入院期間まで記載を求められます。
診断書が求められるシーン

診断書を求められるシーンとして、主に以下4つが挙げられます。
- 休職
- 社会保障制度や福祉制度の利用
- 医療保険の利用
- 障害や疾患による業務内容の調整
それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
1.休職
病気や怪我、障害などを理由に休職する場合には、診断書を勤務先に提出して手続きを進めるのが一般的です。診断書の提出は労働基準法では規定されておらず、必須ではありません。ただ、企業にとっては就労可能かどうかの重要な判断材料となります。
休職の理由や社員の状態を把握するために、診断書の提出を求める企業が多い傾向にあります。また、就業規則にて診断書の提出を定めている企業もあり、この場合は診断書の提出が必須です。
休職が必要だと医師が判断した場合、診断書を医師が作成し、社員が上司や人事担当者に提出して、休職の具体的な相談をします。休職の診断書には「一定期間の休養が必要」と書かれることが多く、具体的にどのくらいの期間休職するかは企業と相談して決める場合もあります。
2.社会保障制度・福祉制度の利用
国の社会保障制度や福祉制度を利用する際の申請書類として、診断書を求められることがあります。申請する制度によって診断書の書式が異なるため、医師に申請用途を具体的に伝えて作成してもらう必要があります。
利用申請時に診断書が必要となる福祉制度の例としては、以下があります。
- 療養費(国内・海外)
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 傷病手当
- 自立支援医療(精神通院医療)
- 障害者手帳の取得
- 障害年金
- 労災保険(休業補償等給付、障害補償等給付、傷病補償等年金)
制度によっては、申請書類の中に「医師の証明欄」が設けられている場合もあります。
3.医療保険の利用
入院や手術に伴う医療保険の給付金請求を行う場合、通常は医師の診断書を提出し、手続きを行います。保険会社は診断書に書かれた診断や治療内容を見て、給付金の支払事由に該当しているかどうかを確認します。
加入している保険会社や医療保険のプランによっては、一定の条件を満たしている場合などに「簡易請求」が認められています。簡易請求は診断書がなくても退院証明書や領収書、診療明細書で代用できます。
保険会社が診断書の書式を定めている場合、給付金を請求するために規定の書式で作成してもらう必要があります。医療保険の給付金請求の手続きは各保険会社で異なるため、保険の担当者または相談窓口に問い合わせましょう。
4.障害や疾患による業務内容の調整
障害の特性や疾患によって業務や職場環境に困難を感じている場合に、必要かつ合理的な範囲で調整を行うことを「合理的配慮」と言います。合理的配慮による業務の調整にも、診断書を求められる場合があります。
例えば「聴覚過敏があって周りの話し声や設備の機械音が気になって集中しにくい」といった場合に、静かな座席に移動させる、あるいは在宅勤務やリモートワークを認める、などの対応を行うことです。
医師の診断や本人の希望に基づき、合理的配慮による個別の要望をスムーズに受け入れてもらうために、医師の診断書が有用です。
診断書を作成してもらう方法

診断書は、医療機関にて医師に作成してもらいます。大学病院など規模の大きな機関では、診断書や各種証明書発行専用の窓口で申請するケースもあります。
まずは、疾患や症状に詳しい医師の診察を受ける必要があります。精神的な不調であれば精神科あるいは心療内科にかかり、診察時に「診断書を発行してほしい」と申し出ましょう。
依頼する際には、「仕事を休職する」「医療保険を申請する」など診断書の目的と提出先を伝えましょう。診断書に必要な情報を伝えることで、スムーズに発行してもらえる可能性が高まります。大きな病院の窓口で申し込む場合は、手紙などで必要な情報を伝えると良いでしょう。
診断書の料金と作成期間
診断書の作成は、原則有料です。医療機関や記載項目によって料金は異なりますが、一般的な相場は2,000円〜10,000円前後とされています。また、作成料金は自費扱いで、医療保険や自立支援医療制度などの対象にはなりません。
診断書の作成までは、通常1〜2週間ほどかかります。初診日に診断書をもらえる場合もありますが、即日発行のケースはそう多くありません。また、診断名が定まらないときなどは再度診察が必要となり、場合によっては1ヶ月以上要することもあります。
急ぎで必要だと伝えても、希望通りに発行してもらえるとは限らないので、診断書を使いたいタイミングを考慮して早めに相談しましょう。
診断書を依頼する際の注意点
診断書は医師の診断により作成されるため、場合によっては発行されない可能性があります。また、有効期限が設けられており、福祉制度や医療保険などで使う場合は期限内に提出することが大切です。ここでは、診断書を依頼する際に気をつけるべき注意点について説明します。
診断書がもらえないケースもある
診断書は、依頼すれば必ず発行される訳ではありません。医師法19条2項には「医師は患者から依頼があった場合には正当な事由がない限り診断書作成を拒否できない」と規定があり、医師が必要だと判断した場合に発行されます。
診察時に症状が見られないなどの理由で、診断書がもらえないこともあります。また、初診時は会って話を聞いたばかりで、診断名まで確定できないことも少なくありません。その際には、後日診断名が確定した際に診断書が発行可能となるはずです。
また、担当した医師が専門外で、医学的判断が適切にできない場合も、診断書の発行は難しいため、症状や障害の特性の分野に詳しい医師に診てもらいましょう。
診断書には有効期限がある
診断書には有効期限が設けられており、一般的には発行から3ヶ月とされています。有効期限を過ぎた診断書は証明書としての効力がなくなるため、必要な手続きに利用できなくなります。
再発行を依頼する場合には、費用も時間もかかるので、診断書を依頼するタイミングをよく考慮するとともに、有効期限内に提出することが大切です。
診断書に関するよくある質問
ここでは診断書についてよくある以下の質問を紹介します。
- 診断書の費用を会社に負担してもらうことはできる?
- 診断書の記載内容について要望はできる?
- 診察なしでも診断書をもらうことはできる?
- 体調不良で会社に行けない場合は診断書の提出は郵送でもよい?
- 休職を希望する場合、診断書はいつ提出したらよい?
対処法がある場合は併せて解説していますので、スムーズな診断書の作成と提出に役立ててください。
診断書の費用を会社に負担してもらうことはできる?
ほとんどの場合は自己負担になります。
明らかに仕事が原因の病気や怪我でない限り、会社は従業員に対して自費で診断書をもらってくるように求めるからです。仕事以外の理由で心身が不調になる場合もあるため、やむを得ないことと言えるでしょう。
しかし、会社と交渉する余地はあります。例えば、「自分は発達障害*でこういう特性があるから配慮してほしい」と要求した際に、「それなら診断書を提出してください」と言われたとします。この場合は「業務に関する診断書ですので、雇用側が費用を負担してください」と交渉することも可能です。
診断書の記載内容について要望はできる?
記載してほしいこと・ほしくないことについて希望を伝えることはできますが、最終的には医師の判断になります。医師はあくまで、問診内容や診察時の様子などを元に診断書を作成するため、事実に反する内容を書いてもらうことはできません。
注意が必要なのは、担当した医師が専門外で適切な診断ができないために希望の診断書を書いてもらえないケースです。例えば、発達障害の症状は「虹色」と呼ばれるように境界線があいまいなケースが多く、専門知識を持った医師でなければ適切な診断書を書いてもらえない場合もあります。
つまり、希望の診断を書いてもらうには、自身の症状をよく理解していて信頼できる医師に依頼することも重要なのです。
診察なしでも診断書をもらうことはできる?
できません。
医師法第20条において、医師は自ら診察しないで診断書を交付してはならないと定められているからです。このため、看護師や医療事務員といった診察できない人に診断書を書いてもらうこともできません。
「外に出るのがつらい」「病院までの移動が大変」などの理由で診察を受けるのが難しい場合は、オンライン診療という選択もあります。オンライン診療でも診断書を発行してもらえるので、利用できる医療機関がないか検討してみるとよいでしょう。
体調不良で会社に行けない場合は診断書の提出は郵送でもよい?
体調不良や入院などの理由があって出社できない場合は、郵送で診断書を送ってもかまいません。
事前に会社に送り先を聞いてから郵送しましょう。直属の上司に送るのか、それとも人事部や総務部の担当者に送るのかは、状況によって変わるからです。
なお、休職届や復職申請書のように診断書と一緒に提出する書類があれば、同梱して郵送できます。
休職を希望する場合、診断書はいつ提出したらよい?
休職届と同じタイミングで提出するのが一般的です。
休職届と診断書をいつ提出すればよいのか、全体の流れを下記にまとめました。
- 就業規則で申請先や休職できる期間などを確認する
- 医師に依頼して診断書を書いてもらう
- 休職届と診断書を提出する
- 傷病手当金を受けたい場合は申請する
- 休職中の連絡方法を確認する
診断書は最短即日で発行してもらえますが、数週間~1ヶ月以上かかる場合もあるため、期間に余裕を持っておくとよいでしょう。傷病手当金については次項で解説します。
休職中に利用できる制度
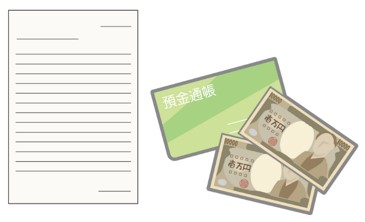
休職中に利用できる制度として、傷病手当金があります。傷病手当金とは、病気や怪我で会社を休む間、健康保険の加入者とその家族の生活を守るための制度です。
以下の条件をすべて満たしたときに、傷病手当金を受け取れます。
- 業務以外の理由による病気・怪我のための休業である
- 仕事ができない正当な理由がある
- 3日間連続で休んだ後、さらに休業した場合
- 休業期間について給与の支払いがない
4については、給与が出ていても傷病手当金より額が少ない場合は差額が支給されます。
傷病手当金の金額は、休業前の給与の2/3が目安です。また、給付期間は通年1年6ヶ月までです。途中出勤して給与の支払いがあった期間は通算されません。
傷病手当金の申請に診断書は不要です。しかし、通院している医療機関の医師から意見書を書いてもらう必要があります。意見書の代わりに診断書を提出することはできないので注意しておきましょう。
診断書は早めに準備しておこう
診断書は、休職や福祉制度の利用、医療保険の給付金申請など多くの場面で求められます。医師が書いた診断書を提出することで、不安なく休業や業務調整を依頼できる、スムーズな手続きを進められる、といったメリットが考えられます。
診断書の作成には通常1〜2週間ほど要します。診断名が出るまで長引くと1ヶ月以上かかることもあるため、必要となりそうな場合は早めに相談しましょう。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
診断書は、医師であるなら必要に応じて書きますので、私も様々な種類の診断書を毎日のように書いています。診断書が必要な場合、主治医には遠慮なく申し出てください。ただ、注意点として、医学的に判断が不可能なことは書くことはできません。時折要望があるものの、書くことが難しいものには、例えば、治療終了に至るまでの時期の見通しや、原因を特定することがあります。精神科診断の多くが、整形外科疾患のように全治3ヶ月など具体的な見通しを推測することが困難です。また、法律家の方から要請されることもありますが、基本的には、何が原因でうつ病を発症した、などはそもそも個人の疾患発症の原因については、現在考えられる医学的プロセスを考えると、原因を特定して何かを発症したと書くことは非常に困難な場合がほとんどです。診断書の記述内容は、状況を鑑みて、医学的判断が可能な範囲になることは理解していただきたいポイントです。
また、特性を考えて、こういう配慮を要請したい、ということはよくあります。その点は、診断書から、提出先にわかって欲しい内容を、具体的に書いてもらうと良いでしょう。予め、紙に書いて渡すのも良い手段ですね。全部ではないかもしれませんが、診断書に反映させることができます。外来で診察している医師の立場として、診断書がご本人にとって状況が改善するために役立つことを願っています。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189