強迫性障害(強迫症)がある場合、症状の影響などにより仕事に支障をきたしている方もいるのではないでしょうか。障害がありながら仕事を続けるためには、強迫性障害について正しい知識を身につけ、対処法や支援先を知ることが大切です。
本記事では、強迫性障害の症状や仕事への影響について解説します。無理なく働くためのポイントや休職、復職の流れ、就職・転職活動の進め方も紹介しているので、自身の障害についてしっかりと理解を深めていきましょう。
強迫性障害(強迫症)とは

強迫性障害(強迫症)は、強い不安やこだわりなどから強迫症状が起こる病気です。強迫症状とは主に、不安感や恐怖心が高まる「強迫観念」と、強迫観念を消し去るために自分の意思で行う「強迫行為」の2つです、
強迫性障害は、自分でもおかしな行動だと分かっていても行為を止めることができず、就労や日常生活にまで支障が出てしまうことも少なくありません。必要以上に強迫行為を繰り返している自覚はあることから、「変な人だと思われてしまう」という恐怖感が高まり、行動範囲が縮小されてしまうケースもあります。
また、強迫性障害は発達障害*と併発するケースも少なくありません。特にASDのこだわりが強いという特性は、強迫行為に似ている部分があります。他にも、特性により学校生活や対人関係での失敗や自信を失う経験をする可能性が高く、生きづらさから二次障害として強迫性障害などの精神疾患を発症しやすいといわれています。発達障害の二次障害については以下の記事で詳しく紹介しています。併せてご覧ください。
発達障害の二次障害とは?症状と種類、予防法や支援機関を解説
強迫性障害(強迫症)の主な症状
強迫性障害の症状の1つである強迫観念には、「手の汚れ」や「家の鍵の施錠」をしたか気になるなど特定の対象物に対する不安と、「誰かに危害を加えたかもしれない」という加害恐怖など対象物のない不安が含まれます。
強迫観念が生まれることで発生する強迫行為は、鍵の施錠やガス栓、電気の消し忘れなどが気になって不安になる強迫観念に対して、何度も繰り返し確認してしまう行為などを指します。
また、物の配置などに過度のこだわりがあり、必ず自分の決めた位置にないと不安で何度も位置を直すといった行動も強迫行為の1つです。このように、強迫観念と強迫行為を繰り返してしまうのが、強迫性障害の主な症状となります。
強迫性障害(強迫症)と発達障害の関連性
不安障害の1つである強迫性障害は、発達障害*との関連性が指摘されています。日常生活や将来に大きな不安を感じ、強いこだわりなどの特性がある発達障害は、不安障害と区別がつきにくいのが特徴です。ただし、発達障害は生まれつきの障害であるのに対し、強迫性障害などの精神障害は後天的な精神疾患であるという大きな違いがあります。
発達障害は生まれながらに特性があり、その特性により多くの困りごとや不安を抱えているケースが多いです。日常生活や仕事などにおける生きづらさやストレスが原因で精神障害を発症する場合があり、これらは後天的な障害であることから二次障害と呼ばれます。
二次障害がきっかけで発達障害が分かることもありますが、二次障害の症状が辛い場合には、発達障害の特性の対処よりも二次障害への治療や対応を優先することが大切です。
強迫性障害(強迫症)による仕事への影響
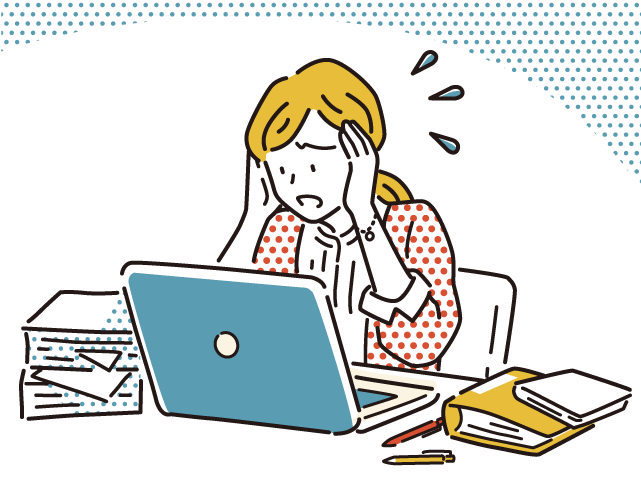
強迫性障害の方は、こだわりや不安などから仕事に支障をきたすケースが多いです。症状による仕事への影響として、考えられる困りごとは以下の通りです。
- 強迫行為に時間がとられることで、遅刻や納期に遅れる
- こだわりが強い難しい人などと誤解を受けやすい
- 強迫観念により業務に集中できなくなる
- 障害として認知されず理解を得られない
上記のように、納期のある仕事に対しても自分の強迫行為を優先してしまうため、時間が余計にかかって間に合わなくなる傾向があります。また、数字や物の配置など細かなことへのこだわりが周囲にとって近寄りがたい印象を与え、職場内の人間関係に影響を及ぼす可能性も少なくありません。
強迫性障害(強迫症)の方が無理なく働くポイント

強迫性障害の方が無理なく働くためには、ストレスを溜めない生活を心がけることが大切です。そのためには、主治医や家族、周囲の人などの協力が必要で、働く場合は職場への理解も重要となります。
また、職場環境や業務内容が自分に合わず、強迫観念や強迫行為が強く表れている場合には休職や転職を考えるのも1つの選択肢です。ここでしっかりと無理なく働くポイントを抑えておきましょう。
早めに医療機関を受診する
強迫性障害の症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診して適切な治療を受けることが大切です。しかし、クリニックによっては強迫性障害に対応できないこともあるため、受診する前に実績や評判などを確認し、自分に合いそうな医療機関を選択しましょう。
自分は大丈夫と思って無理して仕事を続けると、症状の悪化や長期化を招く恐れがあります。自己判断せず、専門家の診断を仰ぎましょう。
リラックスした生活を心がける
強迫性障害は強いストレスから発症するケースもあるため、まずはストレスを溜めずリラックスした生活を心がけることが大切です。しかし、家族や周囲の人に専門知識がない場合、安易な行動や言動からストレスが溜まり症状を悪化させる可能性があります。
例えば「がんばれ」や「我慢しなさい」などの言葉は負担になるケースが多く、ストレスが溜まる原因の1つです。強迫性障害の方だけでなく、家族や周囲の人も障害への理解や正しい知識が必要といえます。
生活環境にストレスを感じる場合は、可能であればそこから離れて生活することも有効な対処法です。
職場に理解を求める
職場の上司などに障害への理解を求めるのも無理なく働くポイントです。強迫性障害は周りから障害であると気づかれない場合も多く、こだわりが強い特徴からマイナスな印象を与えやすくなります。
上司に障害について相談することで、働き方や職場環境などの配慮が求めやすくなるでしょう。仕事が大きなストレスになっている場合は、ストレスのある環境から離れることが改善につながるケースも多いため、休職も視野に入れて今後を考える必要があります。医師による診断書があると会社側の理解を得やすくなるので取得するのも有効です。
休職や転職を考える
職場環境や業務内容が自分に合っていないことが強迫性障害の要因となっている場合は、休職や転職も視野に入れて考える必要があります。
例えば、確認作業が多い、業務内容や手順に変更が生じがち、不特定多数の人とものを共有しなければいけないといった仕事などは、強迫性障害の方の症状を悪化させてしまう恐れがあります。必要以上に確認を繰り返し業務が滞る、変更に対応できず集中できないなど、強迫行為を繰り返してしまい仕事に支障がでる可能性が高いでしょう。
今の職場や業務が辛いまま仕事を続けていると、強迫性障害の症状が重くなったり回復に時間がかかったりする恐れもあります。無理をせず、仕事から離れて心身を休めることを優先しましょう。
強迫性障害(強迫症)で休職する際の流れ
休職制度とは、ストレスなどにより心身に不調があり働けない場合に、会社と雇用関係を継続したまま一定の期間仕事を休める制度です。なお、休職をする際は医師の診断書が必要となる場合が多いため、就業規則等を確認しておきましょう。休職までの基本的な流れは以下のとおりです。
- 休職制度の有無や内容の確認
- 会社に休職の相談をする
- 必要書類を提出する
休職制度は法律で義務付けられていないため、会社によっては制度がなかったり、休める期間や条件なども違ったりする場合があります。休職をしたくても制度がなくてできない場合もあるため、事前に確認が必要です。会社に休職の相談をする際は、直属の上司または担当部署に相談し、休職が決まったら医師の診断書や休職届などの必要書類を提出します。
なお、休職中の給与は原則無給となる場合がほとんどのため、傷病手当金などの経済面の支援制度も押さえておくと安心して休養できるでしょう。
休職の手順や休職中に利用できる支援制度の詳細は、以下の記事で詳しく解説しています。
休職するにはどうすれば良い?休職の流れや注意点、利用できるサービスも紹介
強迫性障害(強迫症)の方が復職するには
強迫性障害の方が休職をして症状が回復し、復職をする場合は主治医から復職可能の判断が必要です。許可がおりたら会社に復職の意志を伝え、届け出を提出するなどの手続きを行います。復職を目指す際には、症状の再発による再休職を防ぐためにもリワークや試し(リハビリ)出勤制度を活用するのがおすすめです。
リワークは医療機関や就労移行支援事業所、障害者職業センター、職場などで実施されている復職のための支援制度です。認知行動療法や対人スキル向上トレーニング、体力作り、生活リズムを整えるなどのプログラムを通して復職に向けた準備を進めます。
試し(リハビリ)出勤は、企業が休職者の職場復帰をサポートするために設けた支援制度です。模擬出勤、通勤訓練、試し出勤などを通して本格的な復職に向けて徐々に体を慣らしていきます。
ただし、職場環境が自分に合っておらず、復職が難しい場合は症状が落ち着いた後に転職することも視野に入れましょう。無理に復職を焦らず、しっかり休養することが大切です。
強迫性障害(強迫症)の方の就職・転職活動
強迫性障害の方が就職や転職活動を進めるためには、働き方の選択や支援機関の利用がポイントです。ここでは、職場で障害に対する必要な配慮を求め無理のない環境で働くための選択肢や、就職・転職活動をサポートする支援機関を押さえておきましょう。
働き方を選択する
強迫性障害の方が就職・転職活動をする際には、障害者手帳を取得していれば一般雇用だけでなく、障害者雇用での応募が可能です。障害者雇用で就職するには障害者手帳が必須のため、事前に取得しておきましょう。
障害者雇用は障害の理解や特性に応じた配慮が前提となるため、強迫性障害への理解を得やすく、業務内容や勤務形態などの面で無理なく働けるよう配慮が受けられます。通院もしやすいため治療を続けながら働くことができ、就職後の定着率も高い傾向です。
支援機関を頼る
自分だけでは対処しきれない場合は、支援機関を頼るのも1つの手段です。強迫性障害の方が休職や転職を考えた際に利用できる支援機関は以下のようなものがあります。
- 就労移行支援
- ハローワーク
- 地域障害者職業センター
- 精神保健福祉センター
- 障害者就業・生活支援センター
これらの支援機関は強迫性障害などの障害への知識のある支援経験が豊富なスタッフが在籍していることも多く、症状や特性に合わせたサポートを行ってくれるのが特徴です。利用に障害者手帳の有無は問われないので、まずはお近くの支援機関に相談してみましょう。
Kaienの支援サービス

強迫性障害の方が一般就労を目指す際や、就労に向けて準備を整えたい場合には、Kaienが行う就労移行支援、自立訓練(生活訓練)の利用がおすすめです。
Kaienの就労移行支援では、自身の障害を理解するための講座や就活対策、100種以上の豊富な職業訓練などを通じ、無理なく働ける職場を見つけるために担当スタッフが徹底サポートを行います。就活から定着まで一貫した支援が受けられるため、就職後の困りごとも相談しやすいのが特徴です。
まずは生活リズムを安定させたい、将来の進路をゆっくり考えていきたいという方は、Kaienの自立訓練(生活訓練)が適しています。実践プログラムを通し、無理なく自立を目指しながら必要な知識の習得が可能です。
Kaienでは無料で見学や体験利用を実施していますので、興味のある方はお気軽にご連絡ください。
強迫性障害(強迫症)の方の仕事探しは適切な支援の活用を
強迫性障害の方は、症状や特性から就労が困難になるケースも少なくありません。無理なく働くためには、医療機関での適切な治療や職場に理解を求めることが大切です。ただし、症状が改善されない場合には、しっかりと休養を取って回復に専念するために休職も視野に入れましょう。休職後の復職は医師と相談しながら進めますが、復職が難しい場合は無理をせず、転職の検討も大切です。
就職・転職の際には、障害者雇用を含めた働き方を検討したり、就労移行支援などの支援機関を利用したりしながら無理なく探しましょう。Kaienでも障害のある方への就労移行支援や自立訓練(生活訓練)を行っています。強迫性障害により仕事や日常生活で困りごとがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
強迫症は、非常に大きな苦痛を伴う疾患です。理性では不合理だと分かっていても、何度も確認を繰り返したり、過度に手を洗ったりする強迫行為に多くの時間を費やしてしまい、大きな負担となります。些細なきっかけから特定の数字にこだわるようになったり、階段を上る際に「右足を最後にしないと気が済まない」といった強迫観念に支配されることもあります。こうした観念に基づく行為の反復は、非常に苦しく、心身ともに疲弊を招きます。
さらに、中途半端な作業では満足できないため、本来「清潔でないことが耐えられない」はずなのに、「中途半端にしか入浴できないなら、いっそ入らない」という矛盾した状態に陥ることもあります。かつては「最も苦痛な精神疾患」とも言われましたが、現在では治療薬の進歩に加え、適切な認知行動療法を受けることで、大幅な改善が期待できるようになりました。ぜひ、専門的な治療を受けることをお勧めします。また、強迫症を克服した当事者による体験記も出版されています。実際の経験を知ることで、より深く理解し、治療に前向きになれるかもしれません。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。
