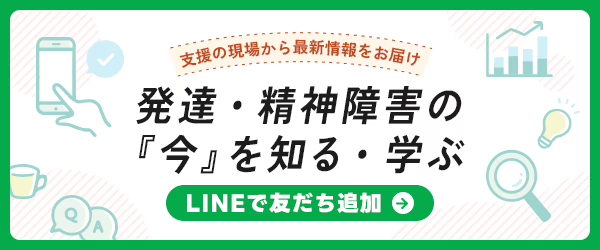就労継続支援B型は、障害によって一般企業で働くことが難しい人が、働く経験を積める就労支援サービスのひとつです。勤務日数や勤務時間を事業所と相談しながら柔軟に決められるので、自分のペースで働きたい人におすすめです。
この記事では就労継続支援B型について、利用対象者や工賃、働き方や利用までの流れについて詳しく解説します。就労継続支援A型や就労移行支援などのほかの就労支援サービスとの違いや、2025年10月から始まる就労選択支援の影響についても解説するので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
就労継続支援B型とは?
就労継続支援B型は障害者総合支援法に基づいて国が定める福祉サービスのひとつで、障害によって一般企業で働くことが難しい人に働く機会を提供する制度です。簡単なデータ入力やパッキング、清掃作業などの作業を行い、工賃をもらいながら働く経験も積むことができます。
就労継続支援B型は事業所に通って作業をすることになりますが、雇用契約は結びません。そのため働く日数や時間を柔軟に決められて、障害や体調などの事情に合わせやすいのがメリットです。
国の就労支援制度には、ほかに就労移行支援や就労継続支援A型がありますが、そのなかでも就労継続支援B型は障害のある方にとって身近なサービスです。就労移行支援の利用者が約3.7万人、就労継続支援A型の利用者が約8.9万人であるのに対して、就労継続支援B型の利用者は約34.8万人と、多くの方が利用しています。(2023年12月時点)
参考:厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」
就労継続支援B型は国の福祉サービスのため、利用するにはお住まいの市区町村の障害福祉窓口への申請が必要です。申請の前に直接事業所を訪れても作業ができるわけではないので、まずは役所の窓口に相談しましょう。
就労継続支援B型の対象者
就労継続支援B型の対象者は、以下のいずれかに該当する人です。
- 就労経験があり、年齢や体力などの事情で一般企業で働くことが難しい人
- 年齢が50歳以上の人
- 障害基礎年金1級を受給している人
- 就労移行支援事業者などによって「就労面の課題がある」「就労継続支援B型の利用が適している」などと判断された人
参考:厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」
上記のような条件はあるものの自治体によっては柔軟に対応しているところもあり、実際には幅広い方が利用しています。そのため、「制度を利用したいけれど、条件に当てはまらないかもしれない」と心配な方は、まず主治医に相談して事業所での作業が問題ないか確認したうえで、お住まいの地域の障害福祉窓口に相談してみましょう。
就労継続支援などの障害福祉サービスは障害者手帳を持っていなければ利用できないと思っている人もいるかもしれませんが、障害者手帳は必須ではありません。障害者手帳を持っていなくても、「障害福祉サービス受給者証」があれば就労継続支援B型を利用できます。
就労継続支援B型の働き方
就労継続支援B型では、障害のある方が自分のペースで働きながらスキルを身に付けられる環境が提供されています。主な仕事内容や勤務日数、工賃について以下で詳しく紹介します。
仕事・作業内容
作業内容は利用する事業所によってさまざまですが、以下のようなものが例として挙げられます。
- 簡単なデータ入力などパソコン作業
- 工場でのパッキングやピッキング作業
- 製品の発送作業
- 書類整理などの軽作業
- 農作業
- 清掃作業
- 衣類のクリーニング
- パンやお菓子の製造
- ミシン作業や手工芸品の制作
- 部品加工
- 飲食店での調理や配膳 など
基本的には事業所で作業に取り組みますが、外出が困難な場合は在宅での就労も認められています。在宅での就労を希望する人は、市区町村の障害福祉窓口に相談してみましょう。
勤務日数・勤務時間
就労継続支援B型の勤務日数・勤務時間は、事業所と相談しながら柔軟に決めることが可能です。障害やその日の体調に合わせて働く時間を決められるので、長時間働くことが難しい人でも安心して利用できます。
「週1日・1時間程度から始めて、慣れてきたら勤務日数を少しずつ増やしていく」なども可能なので、事業所と相談して自分のペースで進めていきましょう。
就労継続支援B型の工賃と平均額
工賃の金額を決める方法は、作業した量に応じて金額が決まる歩合制と、「1日あたり◯円」と決まっている日額制のいずれかになります。
近年の就労継続支援B型の工賃の平均額は、以下のとおりです。
- 2021年度:月額1万6,507円 / 時間額233円
- 2022年度:月額1万7,031円 / 時間額243円
- 2023年度:月額2万3,057円 / 時間額(開示なし)
2023年度の平均工賃は、計算方法が変更となったため、前年度と比べ数値が大幅に増加しています。単純比較はできないものの、時系列でみると、就労継続支援B型の平均工賃は2020年度に少し落ち込んだものの、年々右肩上がりに上昇しています。また「2024年度障害福祉サービス等報酬改定」により、平均工賃月額が高い区分に分類される事業所は基本報酬が引き上げられることなどが発表されました。これは就労継続支援B型の平均工賃の引き上げを狙った改定です。
近年、このような平均工賃アップのための取り組みが行われているため、今後も平均工賃は上昇傾向が続くことが期待されます。
上記の金額は全国平均ですが、都道府県別の平均を見ると地域によって平均工賃に差がある点には注意が必要です。お住まいの地域の平均工賃が気になる方は、以下の厚生労働省の資料からチェックしてみましょう。
参考:厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について」
参考:厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」
就労継続支援B型の利用期間と利用料金
国の就労支援のなかには、利用期間や利用料金が定められているものがあります。就労継続支援B型の利用を検討している人は、利用期間と利用料金についても知っておきましょう。
利用期間
就労継続支援B型は、利用期間が定められていません。「ゆっくり時間をかけて就労経験を積みたい」という人は自分のペースで何年でも利用できますし、就労移行支援や就労継続支援A型に切り替えたあとで「やっぱりB型に戻したい」という場合は利用を再開することも可能です。
就労継続支援B型には年齢制限がないため、65歳以上の人でも利用できます。就労継続支援A型には65歳未満という年齢制限がありますが、B型なら利用中に65歳を迎える人もそのまま利用を続けられます。
利用料金
就労継続支援B型の事業所を利用するには、国が定めた利用料金がかかります。ただし、全額を利用者が支払うわけではなく、9割は自治体負担、残りの1割が利用者負担となります。また、世帯収入に応じて負担額の上限が定められていて、上限以上の料金を請求されることはありません。
世帯収入ごとの負担額の上限は以下のとおりです。
| 世帯の収入状況 | 世帯収入目安 | 負担額の上限(月額) |
| 生活保護受給世帯 | 年収がおおむね300万円未満 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 年収がおおむね300万円未満 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 年収がおおむね600万円未満 | 9,300円 |
| 上記以外 | 年収がおおむね600万円以上 | 37,200円 |
利用日数が多くなっても上記以上の料金はかからないので、安心して利用できます。また、収入の関係で就労継続支援B型を無料で利用している人も少なくありません。
就労継続支援B型のメリット・デメリット
就労継続支援B型のメリット・デメリットには次のような点があります。
<メリット>
- 無理なく自分のペースで働ける
- 利用年齢に制限がなく、65歳以上でも働ける
- 利用期間に制限がなく、長く働ける
- 工賃をもらえる
- 就労継続支援A型で働けない場合でも働ける
<デメリット>
- 工賃が安い
- 世帯収入によっては利用料がかかることもある
就労継続支援B型では、事業所と利用者との間に基本的に雇用契約がありません。
雇用契約がないため、慣れないうちは週1日・1時間などの短時間勤務にできるなど無理のないペースで柔軟な働き方ができることが大きなメリットです。一方で、雇用契約がないため、地域で定める最低賃金が保障されず、労働時間も短いため、工賃が安い傾向である点がデメリットといえるでしょう。
就労継続支援B型とA型の違い
就労継続支援A型は、一般企業で働くことは難しいものの、雇用契約を結んで働くことが可能な人に対して働く場所を提供する福祉サービスです。
B型との大きな違いは雇用契約を結ぶかどうかです。A型は雇用契約を結んだうえで働きますが、B型は雇用契約を結びません。
雇用契約を結ぶことで労働基準法が適用されるので、A型の制度を利用する場合はその地域の最低賃金以上の給料がもらえます。一方、雇用契約を結ばないB型は工賃を時給換算すると最低賃金を下回るケースもあり、そもそも労働時間が短めの人も多いことから、A型よりB型のほうがもらえる金額は安い傾向にあります。
そのほか、年齢制限があるかどうかもA型とB型の違いです。A型には65歳未満という年齢制限がありますが、B型は年齢制限がないので65歳以上の人も利用できます。
勤務日数や勤務時間はA型・B型ともに、事業所や仕事によって異なりますが、A型はB型よりも勤務日数や時間が多い傾向にあります。A型では勤務時間や日数は雇用契約に定められ、1日4~6時間、週3日以上というようなケースが多いとされています。
一方、B型は雇用契約がないため、体調や能力に応じて、週1日1時間から徐々に勤務時間を増やしていくなどといった柔軟な働き方が可能です。
| 就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 | |
| 対象者 | 1.就労経験があり、年齢や体力面で一般企業での雇用が困難な人2. 50歳以上または障害基礎年金1級受給者3. 1および2に該当せず、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている人 | 1. 移行支援支援サービスを利用して就職活動を行っても企業等の雇用に結びつかなかった人2. 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった人3. 就労経験があり、現在は離職している人 |
| 年齢制限 | 18歳以上~上限なし | 18歳以上65歳未満(※) |
| 雇用契約 | なし | あり |
| 仕事内容 | 事業所によって異なる。就労継続支援A型より軽い作業も多い。 簡単なデータ入力や、工場でのピッキング作業、農作業、清掃作業など。 | 事業所によって異なる。簡単なデータ入力や、工場でのピッキング作業、飲食店のホールスタッフ、Webサイトのデザイン制作など。 |
| 勤務日数・勤務時間 | 雇用契約がないため、週1日、1日当たり1時間からなど、体調や能力に合わせ柔軟な対応が可能。就労継続支援A型よりも勤務時間・日数は少ない傾向。 | 1日当たり4~6時間、週3日以上が多い。雇用契約に定めた日数・時間で勤務する。 |
| 工賃 | 23,053円(2023年度平均月額) | 86,752円(2023年度平均月額) |
| 利用期間 | 制限なし | 制限なし |
| 利用料金 | 所得に応じて変わる。無料~上限3万7,200円。 | 所得に応じて変わる。無料~上限3万7,200円など。 |
※65歳以上でも、65歳に達する前5年以上障害福祉サービスの支給決定を受けており、かつ65歳になる前日時点で就労継続支援A型の支給決定を受けていた人は利用可能。
就労継続支援B型と就労移行支援・就労定着支援の違い
就労系の障害福祉サービスには、就労移行支援・就労定着支援といったサービスもあります。
就労移行支援とは、一般企業などへの就労を希望する障害のある方が、就労に必要な知識やスキルを学べる支援サービスです。就労移行支援では、事業所に通い作業実習や訓練を通じて就職・復職に必要な知識やスキルを習得します。
就労継続支援B型と就労移行支援では、支援サービスの内容が異なります。就労継続支援B型が、実際に働く場を提供するサービスであるのに対し、就労移行支援は、就労に必要なスキルを学ぶ場を提供するサービスです。
一方、就労定着支援は、障害のある人が一般就労で長く働き続けることができるようサポートするサービスです。就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、自立訓練(成果作員連)などを経て一般就労した人を対象に、職場に定着できるよう支援します。
就労継続支援B型と就労定着支援の違いとしてまず挙げられるのは、対象者の違いです。就労継続支援B型は、一般企業での雇用や就労が困難な方を対象としますが、就労定着支援は、一般企業などに就労・復職した方を対象とします。
また、サービス内容も、就労継続支援B型が、働く場を提供するのに対し、就労定着支援では、職場に定着できるように本人や企業をサポートする点で異なります。
就労継続支援B型の利用の流れ
就労継続支援B型を利用する際の流れは、以下のようになります。
- 主治医に相談して許可をもらう
まず主治医から就労継続支援B型の利用に問題がないか確認が必要です。主治医に就労継続支援B型の利用を検討していることを伝え、判断を仰ぎましょう。
- 利用したい事業所を探す
主治医の許可を得たら、利用したい事業所を探します。インターネットで探したり地域の障害福祉窓口で紹介してもらったりして、通いたい事業所を見つけましょう。通っている病院がおすすめの事業所を教えてくれることもあります。
利用前の相談・見学を受け付けている事業所もあるため、気になる事業所があれば問い合わせてみるのがおすすめです。
- お住まいの地域の障害福祉窓口で利用申請をする
利用したい事業所が見つかったら、お住まいの地域の障害福祉窓口で利用申請をしましょう。就労継続支援B型を利用するには、自治体が交付する障害福祉サービス受給者証が必要なので、この受給者証を取得するための手続きも必要です。
- 「サービス等利用計画書」を作成して窓口に提出する
利用申請を行うと、自治体から「サービス等利用計画書」を作成するよう求められます。自治体の担当者が障害福祉サービスについて相談できる指定特定相談支援事業者を紹介してくれるので、サポートを受けながら計画書を作成しましょう。
- 「障害福祉サービス受給者証」が発行される
自治体にサービス等利用計画書を提出して自治体の確認が完了したら、障害福祉サービス受給者証が発行されます。利用申請から支給決定と受給者証の発行までは、約2ヶ月ほどかかると思っておいてください。
- 希望の事業所と手続きをして利用開始
障害福祉サービス受給者証が発行されたら、希望の事業所と契約を結んで利用開始となります。
就労継続支援B型を利用する際の注意点
就労継続支援B型を利用するためには、気をつけたいポイントがいくつかあります。申請を検討している方は、事前に注意点を知っておきましょう。
アルバイトとは併用不可
就労継続支援B型とアルバイトの併用を考えている人もいるかもしれませんが、原則としてアルバイトとの併用はできないと考えてください。そもそも就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい人を対象としている制度です。そのため、アルバイトが可能な人は就労継続支援B型の利用に適さないと判断される可能性が高いでしょう。
ただし、就労継続支援B型の利用可否は各自治体が判断するため、障害特性などによって例外的に許可されるケースもあります。何らかの事情があって就労継続支援B型とアルバイトを併用したい場合は、お住まいの自治体の障害福祉窓口に問い合わせてみてください。
特別支援学校の卒業生が利用する場合
特別支援学校の卒業後に就労継続支援B型を利用したいと考えている人もいるでしょう。しかし、就労継続支援B型は「一般企業での就労経験がある」もしくは「就労アセスメントを受けてB型の利用が適当だと判断される」のいずれかを満たさなければ利用できません。
特別支援学校を卒業したばかりの生徒は、当然ながら一般企業での就労経験はないため、就労アセスメントを受ける必要があります。これに関しては以下のような問題が指摘されていて、これを「直B(ちょくびー)問題」といいます。
- 特別支援学校の卒業後に直接就労継続支援B型を利用できない
- 就労アセスメントが「B型を利用するためのもの」になっている
- 適切な就労アセスメントが行われていないケースがある など
特別支援学校の卒業後に就労継続支援B型の利用を検討している人は、このような直B問題についても把握しておく必要があります。
2025年から開始される就労選択支援とは?
2025年10月以降から、就労継続支援B型を新たに利用する方は、原則として「就労選択支援」の利用が必須になります。
就労選択支援とは、働く意志のある障害のある方に、適切な就労支援サービスを提供するために、専門の支援員とともに意欲や能力などをアセスメントし、利用者に合った選択を行うサービスです。
障害を抱えつつ就労を希望する方は、就労選択支援を利用することで、自身の障害や状況に合ったサービスを正しく選び、必要な支援を受けられるようになります。希望通りに働けない、事業所と合わないなどのミスマッチを防ぐためにも、就労継続支援B型を利用する際には、まず就労選択支援を活用し、希望や適性に合ったサービスを選択しましょう。
なお、新たに就労継続支援B型を利用したいという方でも、50歳に達している方、障害基礎年金1級受給者、就労経験がある方は、就労選択支援の利用は必須でなく任意です。
また、2027年4月以降は、新たに就労継続支援A型を利用したい人、および就労移行支援を標準利用期間の2年を超えて利用する人も、利用が必須となる予定です。
就労継続支援B型の事業所の選び方
就労継続支援B型の事業所は、以下のポイントを考慮して選びましょう。
- 作業内容や働き方
- 事業所までの距離やアクセス
- 事業所との相性
それぞれどのような点を確認すべきなのか、以下で紹介します。
作業内容や働き方
作業内容や働き方は、事業所によってさまざまです。事業所の公式ホームページや求人サイトを確認して、どのような作業ができるのかを事前に確認しておきましょう。「作業内容が自分に合っているか」「無理なく働けそうか」といった視点で事業所を選べば、無理せず長く利用を続けられる可能性が高まるでしょう。
「自分に合っている作業がわからない」という人は、気になる作業を行っている事業所を体験利用してみるのがおすすめです。
事業所までの距離やアクセス
自宅から事業所までの距離やアクセスも重要なポイントです。体力的・金銭的に無理なく通える事業所を選びましょう。自宅から遠くアクセスしづらい場所にある事業所を選んでしまうと、移動によって身体に負担がかかり、交通費も多くかかってしまいます。
事業所によっては通勤交通費を支給してくれることもあるため、希望する事業所の交通費の取り扱いについても事前に確認しておくのがおすすめです。
事業所との相性
継続して通うことになるので、事業所の雰囲気が自分に合っているかどうかも確認しておくと安心です。体験利用や見学の際に、「ここで働けそうか」という視点でほかの利用者やサポートスタッフの様子を見てみましょう。
相性の良い事業所なら、楽しみながら長く利用を続けられますよ。反対に、相性が合わない事業所を選んでしまうと通うのがストレスになってしまうので、事業所の雰囲気も事前に確認しておきましょう。
また、早くからしっかりと就労アセスメントを行い、自分の就労上の強みや弱みなど親身にフィードバックをしてくれる事業所を選ぶのもおすすめです。自分の希望や適性や能力などをしっかりと見極めてくれる事業所だと、自分に合った働き方を見つけやすくなるでしょう。
地域の支援者の評判
地元の支援事業所の事情などをよく知る地域の支援者を見つけ、評判のいい事業所を紹介してもらうのも有効な手段です。
地域には、その地域の支援事情に精通しているキーマンといえる支援者や支援機関があります。そうした支援者・支援機関のもとには情報が集まっているため、豊富な情報から、自分に合った情報を聞きだすことができます。
例えば、公的な支援機関や支援窓口などで、地域の支援者・事業所の評判に詳しい人から話を聞くのもよいでしょう。自分に似た事情の人が多く通う事業所や、評判のよい事業所などを教えてもらえる可能性があります。
就労継続支援B型から一般就労を目指すには
就労継続支援B型は、一般企業での就労が難しい障害のある方に対して、定期的に働ける場を提供し就労を支援するサービスです。しかし、一般企業への就職を目指すには、より専門的な支援が必要になることもあります。その場合、職業訓練や就職活動のサポートが受けられる「就労移行支援」がおすすめです。
厚生労働省の「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ」によると、就労継続支援B型から一般就労へと移行した人の割合は10%前後で横ばいに推移しているのに対し、就労移行支援では50%台で増加傾向にあります。
就労継続支援A型から一般就労に移行した人の割合が20%台で推移していることを考えても、就労移行支援から一般就労に移行する人の割合の高さが際立っています。
就労移行支援は、就職に向けた職業訓練や一般企業で働くためのスキルの習得を支援するプログラムを中心とした福祉サービスです。就労継続支援B型では就労に応じて工賃が発生しますが、就労移行支援では就職のための訓練が主体で就労は伴わないため、工賃は発生しません。
Kaienでは発達障害*の方に特化した就労移行支援を実施しています。一人ひとりの特性に応じた支援計画を作成し、ビジネスマナーや各種スキルの習得、実践的な職業体験を通じて一般就労に向けたサポートを行います。また、障害に理解のある企業と連携しており、あなたの特性や希望に合った求人を紹介することも可能です。
また、就労以前に、生活面における自立に不安がある場合には、自立訓練(生活訓練)の利用もおすすめです。Kaienの自立訓練(生活訓練)では、生活リズムの整え方や感情のコントロール方法、コミュニケーション手法などが学べるプログラムを提供しており、生活の基礎力を高めることもできます。
就労継続支援B型での経験を活かし、一般就労を目指したいと考えている方は、ぜひKaienの就労移行支援や自立訓練(生活訓練)の利用をご検討ください。
就労継続支援B型は自分のペースで働きやすい
就労継続支援B型は、国が定める就労支援サービスのひとつです。就労継続支援B型を利用したいと思ったら、まずは主治医に相談しましょう。主治医の許可が得られたら、希望の事業所を選んで地域の障害福祉窓口で必要な手続きを行います。事業所選びに迷ったら、障害福祉窓口に相談してみてくださいね。
ストレスなく長く利用を続けるには、事業所選びが重要です。作業内容や事業所までのアクセス、事業所との相性を考慮して、通いやすい事業所を選びましょう。
就労継続支援B型は、「雇用契約を結ばない」「年齢制限がない」など、ほかのサービスと比較して働き方を柔軟に選べるのがメリット。自分のペースで働きたい人は、就労継続支援B型がおすすめです。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
【アッシジのフランシスコと働くこと。その1】
就労継続支援(作業所)についての説明は本コラムで十分なされていますので、ぜひご参照ください。私はあえて働くこととはどういうことかを少し掘り下げて考えてみたいと思います。その際の登場人物となるのが、アッシジの聖フランシスコです。
つい先日、お亡くなりになったカトリックのローマ教皇フランシスコは、このアッシジのフランシスコから名前を取ったと言われています。また、ローマを舞台に数々の作品で知られる作家の塩野七生氏は、フランシスコを「ルネサンス運動の第一走者」*1)と呼んでいます。
なぜ一介の聖職者であったフランシスコが、ルネサンスの運動の第一走者だったのでしょうか?それは彼が「見たい、知りたい、分かりたい」*1)と言う人間の根源的な感情を、実直に生き抜いたからに他なりません。むしろ、その信念は、当時のローマ教会の教えを守らないと救われないと言う教えとは相反するものでした。
フランシスコはもともと豊かな家の出身でしたが、十字軍の東方略奪による経済発展に浮かれ堕落するカトリック教会の姿を見て幻滅し、自らは清貧を説いて、らい病患者の体を洗い、彼らに食事を与え続けると言う行動をしました。
まるで当時のカトリック教会は、新自由主義経済で大儲けをしてどんどん堕落していくある国のある偉い人のような姿ですね。いつの時代でも、人間の根本的な心や行動は変わらないのかもしれません。その中でフランシスコは本当に大切なものは何かを自ら考え抜いて、己の信念を貫いた生涯を送ったのです。【つづく】
*1)塩野七生、『ルネサンスとは何であったか』(新潮文庫)

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189