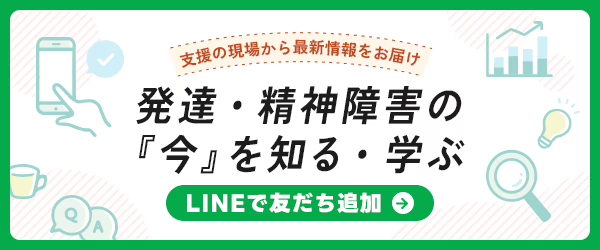就労移行支援を利用したものの、さまざまな不満を感じて途中で利用を止めてしまった人もいるでしょう。また、就労移行支援の利用を検討しているのに「ひどい」という声を耳にすると、不安を感じてしまいますよね。
この記事では、就労移行支援の仕組みと「ひどい」と感じる事業所の特徴、合う人・合わない人の特徴や自分にあった就労移行支援事業所を選ぶためのポイントなどを詳しく紹介します。就労移行支援の利用を考えている人や、自分にあった事業所を探している人は、ぜひ参考にしてくださいね。
目次
そもそも就労移行支援の仕組みとは?

就労移行支援とは、一般企業への就職を目指している障害を持つ方を支援する制度です。利用者は就労移行支援事業所に通所し、就職に必要なスキルを身につけたり就職活動のサポートを受けたりできます。
この制度は障害者総合支援法に基づいた障害福祉サービスのひとつで、事業所は主に「障害福祉サービス等報酬」という補助金によって運営されているのが特徴です。受給できる補助金の額は、利用者の人数や利用時間、就職した利用者の定着率などによって決まります。
利用者が支払う利用料も事業所の収入源のひとつですが、利用料は利用者本人や世帯の所得によって決まるため、無料で通所している利用者も少なくありません。
ひどいと感じる就労移行支援の特徴

「就労移行支援はひどい」と聞いて、利用をためらっている方もいるかもしれません。また、利用中の就労移行支援事業所について、実際に不満を持っている人もいるでしょう。
ここでは、ひどいと感じる就労移行支援の特徴を紹介します。
最低在籍期間がある
就労移行支援事業所の中には、報酬の仕組みの都合から最低在籍期間を設定している場合があります。国から支給される報酬は利用者の人数や利用回数によって決まるため、短期間での就職は事業所の収益がマイナスになることもあるでしょう。
利用者の就職意欲や状況よりも事業所の都合が優先されるような対応が続くと、「ひどい」と感じてしまうのも無理はありません。特に、1日でも早く就職したいと考えている方にとっては、最低在籍期間の存在は大きなストレスになるでしょう。
スタッフの質が低い
就労移行支援事業所のスタッフは、日々の支援を通じて利用者の就職をサポートする重要な存在です。しかし、中には障害に対する理解が不十分だったり、コミュニケーションに問題があったりするスタッフがいる事業所もあります。
特に地方では、事業所の数が限られているため競争が少なく、スタッフやサービスの質が低くても経営が成り立ってしまう「寡占状態」に陥っているケースもあるでしょう。こうした環境ではスタッフの質が改善されにくく、「担当が頻繁に変わる」「対応が一方的で寄り添ってくれない」などの不満が生まれやすくなります。
プログラムの質が低い
就労移行支援のプログラムは、本来であれば就職を目指すための内容であるべきです。しかし、実際には簡単すぎたり、自分が希望する職種と関係のない訓練ばかりだったりと、個々のニーズに合っていないケースも見受けられます。
また、「Webサイトでは魅力的に見えていたのに、いざ通ってみると実際の内容がまったく違っていた」という声も少なくありません。特に都市部では競争が激しく、利用者を集めるために誇張された広告が出回っていることもあり、注意が必要です。
こうしたプログラムの質の低さは通所のモチベーションを下げ、結果的に就職から遠ざかる原因にもなります。そのため、「ひどい」と感じる方が多いでしょう。
事業所の雰囲気が悪い
「なんとなく通いにくい」「居心地が悪い」と感じる場合、それは事業所の雰囲気に原因があるのかもしれません。「利用者が少なすぎて活気がない」「スタッフ同士の関係がぎくしゃくしている」「全体的に暗く、重たい雰囲気がある」といった環境では、安心して訓練に取り組むのは難しいでしょう。
就労移行支援は、事業所に通ってスキルや自信を身につける場です。そのため、リラックスできる空気感や前向きな雰囲気であるかどうかも重要になります。見学の際には、施設の清潔感や利用者同士の関係性、スタッフの対応などもよくチェックしておきましょう。
就職できない・させない
就労移行支援の目的は「就職」ですが、中には利用者の就職をあえて引き延ばす事業所も存在します。その背景には、一定数以上の利用者が就職すると、新たな利用者が増えなければ国からの報酬が減り、事業所の収益が下がってしまうという制度上の仕組みがあります。
そのため、すでに就職の準備が整っていても「まだ早い」などと理由をつけて必要以上に在籍させるケースもゼロではありません。利用者としては本来の目的を果たせず、大きな不満や不信感を抱く原因になります。
就職後の定着率が悪い
就職活動で本当に重視すべきなのは就職そのものではなく、自分に合う職場を見つけて安定して働き続けられるかどうかです。ところが、就労移行支援事業所の中には、本人の希望や適性に合わない企業に就職させ、その後のサポートやフォローをしないケースも存在します。
その結果、早期離職につながってしまい、「せっかく就職できたのに長続きしなかった」という経験をした方も少なくありません。定着支援が不十分な事業所では働き始めてからの悩みや困りごとを相談できる相手がいないため、「ひどい」と感じる利用者が出てしまうのです。
利用前に知っておきたい!就労移行支援のルール

就労移行支援を利用する前に、制度に関する基本的なルールを知っておきましょう。ルールを知らないまま利用を始めてしまうと、想像していた内容とのギャップから「ひどい」と感じてしまうこともあります。
ここでは、就労移行支援について誤解されやすい点や、不満につながりやすいポイントを解説します。
事業所で作業をしても賃金はもらえない
「就労移行支援事業所で軽作業に取り組んだのに、賃金がもらえなかった」という不満の声も聞かれます。苦労して作業したのに賃金がもらえないと、がっかりしてしまう人も多いでしょう。
しかし、就労移行支援は労働ではなく訓練のため、そもそも賃金は発生しない点に注意してください。同じく障害福祉サービスである就労継続支援は賃金や工賃が支払われるため、就労移行支援も賃金がもらえると思っている人もいるかもしれませんが、そうではありません。
就労移行支援を利用する際は、賃金が支払われないことを事前に理解しておく必要があります。
なお、まれに工賃制度を導入している事業所もあり、その場合はわずかながら報酬が支給されます。ただし、これはごく限られた例であり、多くの事業所では賃金はもらえないと考えておいてください。
就労移行支援の利用中にアルバイトはできない
就労移行支援事業所に通所している間は基本的にアルバイトは禁止されており、経済面の不安から、事業所への不満につながる場合もあります。就労移行支援の利用期間中にアルバイトが禁止されているのは、そもそも就労移行支援は就職が困難な人のための制度だからです。
現時点でアルバイトができる人は、就労移行支援制度の対象ではないことを理解しておきましょう。このようなルールを事前に理解していないと、不満を感じる原因になります。
就労移行支援を利用中のアルバイトについては、以下の記事で詳しく解説しています。収入が心配な人のための制度も紹介しているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。
就労移行支援はアルバイト禁止は本当?バレる理由と利用できる制度も紹介
2年間の利用期限がある
就労移行支援制度には、2年間の利用期限があります。これは、制度の利用が長期化するのを防ぎ、早期就職を促進することを目的としているためです。
自分のペースでゆっくりと就職を目指したいと考えている方は、2年間の期限が設けられていることに焦りや不安を感じるかもしれません。例えば「本格的な就職活動に入る前に、まずは生活の基盤を整えたい」といった場合には、就労移行支援だけでなく、自立訓練(生活訓練)など他の支援制度の利用も検討してみましょう。
就労移行支援が合う人・合わない人の特徴
就労移行支援は、利用する人の目的や状況によって「合う」「合わない」が分かれます。
ここでは、就労移行支援が合う人・合わない人の特徴を紹介するので、利用を検討している方はぜひチェックしてみてください。
就労移行支援が合う人の特徴
以下のような方は、就労移行支援の利用が向いています。
- 一人で就職活動を進めるのが難しいと感じている
- 自分の特性やスキルを理解したうえで、無理のない形で働き始めたい
- 仕事に必要なスキルや社会性、コミュニケーション力を身につけたい
- 専門的な支援を受けながら、焦らず就職を目指したい
このように、サポートを受けながら就職に向けての準備を進めたい方にとって、就労移行支援は大きな支えになるでしょう。
就労移行支援が合わない人の特徴
以下のような方は、就労移行支援があまり合わない可能性があります。
- 自力で就職活動を進められる自信がある
- 訓練や就職先の紹介だけ受けたいが、日々の支援は不要だと感じている
- 決まった時間に通所することが負担に感じる
- アルバイトをしながら就職活動をしたい
就労移行支援は「支援を受けながら就職を目指す」ことが前提となっているため、特別な支援が不要な方には、ハローワークや専門学校など他の手段の方が適している可能性があります。
また、安定した日常生活や社会生活が送れておらず、決まった時間に通所することが難しい方も、就労移行支援の利用は難しいかもしれません。そのような場合は、まず生活面の支援を受けられる障害福祉サービスの利用を検討するのがおすすめです。
自分にあった就労移行支援を見つけるための事前準備
就労移行支援を利用するうえで、事業所が自分にあっているかどうかはとても重要です。ここでは、自分にあった就労移行支援を見つけるための事前準備について解説します。
就労移行支援を利用する目的を明確にする
就労移行支援を利用する前に、「どんな働き方を目指したいか」「どのような支援やサポートが必要か」といった目的をあらかじめはっきりさせておくことが大切です。
例えば「デスクワーク中心の職種に就きたい」「対人関係に不安があるため、コミュニケーションスキルを身につけたい」など、自分の状態や希望を整理しておきましょう。目的がはっきりしていれば事業所選びの基準も明確になり、自分にあった場所を見つけやすくなります。
反対に、目指すゴールがあいまいなままでは支援内容とのミスマッチが起きたり、就職活動の方向性が定まらず、最適な支援が受けられなかったりする可能性があるため、注意が必要です。
気になった事業所は見学や体験をする
パンフレットやホームページだけでは、事業所の雰囲気やスタッフとの相性までは分かりません。気になる事業所が見つかったら、見学や体験を通じて実際の様子を確認してみましょう。
見学では、施設の清潔感や利用者の様子、スタッフの対応などをしっかりチェックすることが大切です。可能であれば、複数の事業所を見学・体験して比較してみると、より自分にあった事業所を見つけやすくなりますよ。
事業所選びに失敗しないためのチェックポイント
ここまで紹介してきたように、さまざまな事情から就労移行支援事業所が「合わない」と感じることもあります。なるべくこのような事態に陥らないように、事業所選びは慎重に進めましょう。
ここでは、就労移行支援事業所選びを失敗しないためにチェックしておくべきポイントを4つ紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
サービス内容が自分のニーズにあっているか
サービス内容が自分のニーズにあっていないと、不満の原因になります。事業所によってプログラムの内容が異なるため、自分に必要な訓練や支援が受けられる事業所を選ぶことが大切です。
例えばプログラミングなどITスキルを身につけたい場合は、その分野を得意とする事業所を選ぶのがおすすめです。事前にサービス内容を確認し、自分の目標やニーズにあった事業所を選ぶことで、楽しみながら通所できるでしょう。
スタッフや事務所の雰囲気があっているか
事業所選びでは、スタッフや他の利用者の雰囲気が自分とあっているかも重要なポイントです。例えば、「一人で静かに作業がしたい」という人と「他の人とコミュニケーションを取りながら訓練したい」という人では、あっている事業所の雰囲気が異なります。
また、グループワークのようにコミュニケーションが必要なプログラムもあるため、他の利用者との相性も大切です。利用者同士の関係性や雰囲気もチェックしておくと、安心して通所を始められるでしょう。
見学や体験ができる就労移行支援事業所も多いため、実際の雰囲気を確かめてから通所するかどうかを決めるのがおすすめです。自分にあった環境なら、積極的に訓練に取り組めるでしょう。
経済面も含め無理なく通える場所にあるか
就労移行支援は事業所に通って訓練や支援を受けるため、経済面も含めて無理なく通える場所にあるかどうかも重要です。「通所にかかる交通費が高い」「自宅から遠く、乗り換えも複雑」といった事業所は、通所が負担になってしまう可能性が高いでしょう。
サービス内容や雰囲気に加えて、通いやすさも考慮して事業所を選ぶのがポイントです。最寄り駅からの送迎バスなど、利用者が快適に通所できるよう工夫している事業所もあるので、事業所ごとの通所方法についても調べてみてくださいね。
就職者数や定着率など実績は十分か
最終的な目標は一般企業への就職のため、就職者数や定着率などの実績も確認しておきましょう。十分な実績のある事業所なら、サービス内容が充実している可能性が高いです。
就職率も参考になる実績のひとつではありますが、計算方法が事業所ごとに違う点に注意してください。例えば、「たまたま就職率が高かった期間の実績だけを公表している」「途中で辞めてしまった人は就職率の計算に含めていない」といったケースも見られます。
事業所の実績を確認するときは、1年間の利用者数や就職者数、辞めてしまった人数など、変えられない数字をチェックするのがポイントです。
自分にあった事業所を見つけることが重要
就労移行支援を利用する場合、自分にあった事業所を見つけることが大切です。まずは自分の目標や学びたい内容を決めて、それにあう事業所をいくつかピックアップしてみましょう。その中から、実績や通いやすさなどを考慮して選んでみてください。事業所の雰囲気も大切なので、気になる事業所には見学や体験に行ってみるのがおすすめです。
就労移行支援の利用を検討している人は、ぜひKaienにご相談ください。Kaienの就労移行支援プログラムは専門家が推奨する充実した内容で、100種類以上の職種を体験できます。発達障害*や精神障害に理解のある200社以上の企業と連携しているので、独自の求人を紹介できるのも強みです。
「就職活動を始める前に、まずは自立した生活を送れるようになりたい」という方は、自立訓練(生活訓練)の利用も検討してみましょう。Kaienの自立訓練(生活訓練)では100以上のプログラムを通じて、生活や就職に役立つ見学や体験が可能です。
見学・個別相談会を実施しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
就労移行支援事業所でひどいと感じると、はたして自分は就職できるのかと不安になることがあるでしょう。『就労移行支援の就職率は80%以上!?』の記事にもあったように、障害者雇用のニーズが増えている現在、就労移行支援事業所も高い推移で増えています。特に地方在住などで事業所の選択肢が少ない場合に、「当たり」でない事業所の可能性が高くなるかもしれません。
ただし、「ひどい」という感情は主観的なものですので、まずは一旦冷静になることをお勧めします。できれば、机に向かって紙と鉛筆を用意しましょう。「どういうところがひどいと思ったか」を箇条書きで列挙して、その妥当性(客観的に見てどのくらい当てはまるか)や解決策(職員に相談する、同じ利用者に話してみる)などを書き出して見ると良いでしょう。このように、一時的に自分の主観を棚上げしてできるだけ客観的に考え直してみる作業は認知療法あるいは認知行動療法と呼ばれます。
自分で考えたり、他者に相談してもやはり納得いかないことがある場合は、通院しているクリニックの主治医や自治体のソーシャルワーカーに相談してみると解決の糸口がつかめるかもしれません。
大切なのは、あなたが納得のいく就労を実現することです。就労後も定着支援などで長い付き合いになることもあります。良い就労になるようバックアップしてくれる事業所が見つかると良いですね。

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。