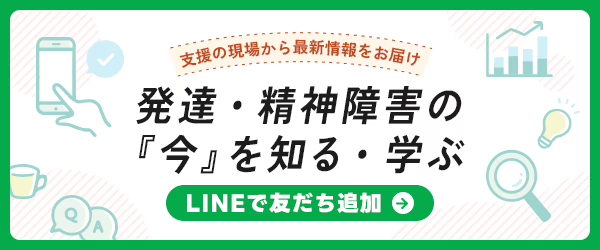就活において、自己PRは合否を左右する重要なポイントです。自己PRの書き方がわからず、悩んでいるADHD(注意欠如多動症)の方も多いのではないでしょうか。自己PRをうまく書けるようになれば、就活の成功率も高まるため、書き方のコツやポイントを押さえておくとよいでしょう。
この記事では、自己PRを作成するときのポイントや、自分の強みの見つけ方について詳しく解説します。自己PRが思うように書けないときに利用できる支援機関も紹介しているので、参考にしてみてください。
目次
就活において自己PRが重要な理由
自己PRとは、就活の履歴書や面接で自分の強みを企業に伝えることです。自己PRを通して、求職者は企業が求めるスキルや能力と自分の強みを結びつけられます。
優れた自己PRを用意することで内定が得やすくなるだけでなく、企業や自分の能力に関する誤解も起こりにくくなります。
適切な自己PRを作るためには、企業の理念や業務形態について調べることが大切です。その過程を通して求職者は応募企業に詳しくなり、企業側は自己PRでどのような人材なのかが把握できます。
その結果、入社後のミスマッチが起こりにくくなり、早期離職などのトラブルを防ぐ効果が得られます。
自己PRと自己アピールの違い
自己アピールと自己PRの違いは訴求する際の観点にあります。自己アピールは自分の観点から自己の魅力を伝えるのに対し、自己PRでは企業側の視点を重視するということです。
自己PRでは、企業にとって自分という人材にどのような価値があるのか、どのような形で貢献できるのかを伝えます。また、長所もよく自己PRと混同されがちですが、自己アピールと同様に、長所は自分が思う自分の強みを伝える項目です。企業側の視点を重視しないという点で、自己PRとは異なるといえます。
ADHDの方が自己PRを作成するときのポイント
ADHDの方は、自身の特性を理解したうえで自己PRの作成に取り組むことが大切です。また、企業研究や経歴の洗い出しなど、基本的なポイントも押さえておきましょう。
ここからは、ADHDの方が自己PRを作成するときのポイントを3つ紹介します。
経歴や実績を洗い出す
自己PRを作成する前に、主張を裏付ける素材を用意する必要があります。これまでの経歴や実績を洗い出し、自分がどのようなことを経験してきたのかを再確認しましょう。
転職においては、今までしてきた仕事を順番に書き出すのが最初のステップです。業種や会社名、業務内容、仕事の中で得た知識やスキルなどを具体的に書き出し、情報を整理してみてください。
この最初のプロセスで確認した経歴や実績を素材として、自己PRを作成する足がかりにすると、作業が進めやすくなります。
自己分析をして障害理解を深める
ADHDの方が説得力のある自己PRを作るためには、自己分析を通じて障害理解を深めることがポイントです。発達障害*の特性がある方は、障害理解を深めることで自分の特性を客観的に把握できるようになります。この作業を通して、企業が求める人物像と自分がマッチするかどうかを判断しやすくなるでしょう。
自己分析をするときは、得意・不得意や過去の成功・失敗体験、キャリアビジョンなどを書き出していきます。紙に書き出した情報から、自分の特性を客観的に分析してみてください。
深く自己分析を行うためには、アルバイトや職業訓練などで経験を積むことも必要です。ただし、挑戦に失敗して傷つき、意欲を失ってしまっては本末転倒となります。焦らないよう、スモールステップから地道に取り組むことが大切です。
企業ごとに研究と分析を行う
自己PRでは、自分がどのような形で企業に貢献できるのかをアピールします。そのため、企業ごとに研究や分析を行い、求職者に求めているポイントを理解することが重要です。
企業研究の際は、基本情報や経営理念、事業内容、企業文化などを企業のホームページなどから徹底的に調べましょう。研究した情報を分析し、自分とマッチしやすいかどうかを確認してください。加えて、ADHDの方は障害者の雇用実績にも注目するとよいでしょう。障害者手帳を取得している場合、障害者雇用の求人にも応募が可能です。障害者を多く雇用している企業なら、内定がもらえる可能性は高くなります。
障害者手帳については、以下の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。
障害者手帳とは?取得のメリットや申請方法、よくある質問を解説
自己PRに書ける強みを見つける方法
自己PRを書く際は、自分の強みを軸とし、人材としての価値をアピールするのが基本です。まずは企業に訴求できる自分の強みを見つけ、担当者の心を動かす自己PRを作成しましょう。
ここでは、自己PRに書ける強みを見つける方法を紹介します。
過去の経験や取り組みを書き出す
自分の強みを見つけたいときは、課題に直面した経験などを思い出すとよいでしょう。
例えば障害特性により、なかなかうまくいかない場面に直面したときを考えてみてください。試行錯誤を繰り返し、工夫を凝らすことで困難を乗り越えた経験があれば、その前向きな姿勢を企業にアピールできます。困難にぶつかってもくじけないタフネスは、どの仕事でも役に立つ能力だといえるでしょう。また、これらの経験は自身の障害理解や対応能力をアピールするのにも役立ちます。
このように、困難を乗り越えたエピソードや過去の成功体験など、自己PRに書けそうな経験をピックアップして書き出しておくことが、強みを見つける第一歩です。
親しい人や専門機関に相談する
自分の強みやアピールポイントは、自分だけでは把握しきれないこともあるでしょう。客観的な自己分析が難しい場合は、親しい人や専門的な知見を持つ医師や心理士、支援機関のスタッフなどに相談するのも手です。
客観的な視点からも洗い出すと、新たな強みを見つけられるかもしれません。なかなか強みを見つけられないときは、身近にいる人や専門家に頼り、積極的に相談することをおすすめします。
なお、発達障害の方が相談できる支援機関の詳細については後述します。
適職診断を受ける
適職診断を受け、診断結果から自分の強みを知ることも一つの方法です。適職診断を利用すると、自分の性格や向いている仕事、ストレス耐性などをデータで客観的に評価してもらえます。
適職診断は転職サイトなどから利用できますが、ハローワークや障害者職業センターなどではGATB(一般職業適性検査)が無料で受けられます。
GATBは、紙筆検査と器具検査で9種の能力を測定し、自分の得意分野や苦手分野を調べる職業適性検査です。適性のある職業グループを把握でき、就活で応募すべき企業を見極めやすくなるため、積極的に活用するとよいでしょう。
発達障害の特性を強みに変えるには?
発達障害の特性を自分の「苦手」や「弱み」ととらえている方も少なくありません。しかし苦手と得意、弱みと強みは表裏一体であり、見方を変えれば短所は長所にもなるものです。
例えば、好きなことしか集中できない、集中するとなかなか切り替えられない弱みがあるとします。これは裏を返せば、好きなことなら長時間でも集中して取り組めるということです。興味のある分野なら、知識量や作業量で誰にも負けない人材になれる可能性があります。
ほかにも、独断で動いてしまう、チームプレーが苦手という弱みは、決断力や行動力が高い強みとして置き換えられます。一人ひとりの裁量が大きく、自由に働ける職場なら、高い成果を上げられるかもしれません。
このように、発達障害の特性は見方次第でいくらでも強みになります。自己PRを作成する際も、発達障害の特性をポジティブな視点から分析する姿勢が大切です。
ADHDの方の自己PRの書き方&例文
自己PRを書くときは、お手本となる例文を参考にすると作業を進めやすいです。まずは自分がアピールしたい強みを決め、例文を自分なりにアレンジして魅力的な自己PRを作成してみましょう。
ここからは、ADHDの方が自己PRを書くときのポイントと例文を、活かしたい特性ごとに紹介します。各特性について、向いている職業例も紹介しているので、参考にしてみてください。
発想力や独創性がある特性を活かした例文
ADHDの特性の一つに、ほかの人には思いつかないようなアイデアが浮かぶなど、発想力や独創性の豊かさが挙げられます。発想力や独創性がある方には、以下のような職業が向いています。
- 料理人
- デザイナー
- アニメーター など
発想力や独創性をアピールする自己PRを書くコツは、思考が散らかりやすい特性を強みに変えることです。企業のニーズに合わせながら、ADHDならではの柔軟な考え方が仕事に活かせることを訴えるとよいでしょう。
発想力や独創性のある特性を生かした自己PRの例文は以下のとおりです。
<例文>
私の強みは独創的なアイデアを生み出す発想力です。発達障害の特性から、私は思考が一貫せず、議題とは無関係な方向にも広がっていく傾向があります。私はこの特性を、既存の常識にとらわれないアイデアを生み出せる長所だと考えています。貴社のデザイナーとして採用していただければ、柔軟な考えから生まれる斬新なアイデアを提案したり、新たな視点から課題にアプローチしたりすることができます。私は創造的な業務や新しい事業の立ち上げを得意としており、アイデアを出す場面で大きく貢献できると考えています。
興味がある分野で高い集中力を発揮する特性を活かした例文
ADHDの方は、自分の興味がある分野なら集中力を発揮して作業に取り組める傾向があります。この高い集中力を軸に、自己PRを作成するのもよいでしょう。特定分野における集中力の高さが活かせる職業例としては、以下などが挙げられます。
- 研究職
- プログラマー
- 教員 など
高い集中力を自己PRでアピールしたい場合は、作業に没頭することで企業の業績向上に貢献できることを訴えるとよいでしょう。大切なのは、自分にとって興味のある分野と応募企業の事業領域が重なっていることです。自分を採用することで、お互いに利益があるということを論理的に伝えてください。
興味がある分野で高い集中力を発揮する方向けの自己PR例文は、以下のとおりです。
<例文>
集中力の高さが私の強みです。発達障害の特性によって、興味がある分野において取り組んでいる作業に没頭しやすい性質があります。集中力が高い特性により、同じ環境で何時間も高いパフォーマンスを発揮し続けることができます。貴社のプログラミング業務でも、持ち前の集中力を活かして業績向上に貢献できると考えております。
好奇心旺盛で行動力がある特性を活かした例文
ADHDの多動性や衝動性といった特性も、見方を変えれば仕事に役立つ能力となります。好奇心旺盛で学習意欲が高い、行動力があるといった訴求ポイントで、魅力的な自己PRを作成するとよいでしょう。好奇心旺盛で行動力がある方には、以下のような職業が向いています。
- 編集者
- ディレクター
- カメラマン など
これらの職業ではフットワークの軽さが重視されます。頭で考えるより先に行動できる点や、新しい業務に物怖じせず挑戦できるところをアピールしましょう。また、高い行動力で困難を乗り越えられる問題解決能力も、アピールポイントの一つです。
好奇心旺盛で行動力がある場合の自己PR例文は、以下のとおりです。
<例文>
私の強みは、新しいことにためらわず挑戦できる行動力です。仕事でわからないことがあれば好奇心を持って自分で調べ、解決方法を見つけ出すことを得意としています。そのため、初めて担当する仕事にも積極的に挑戦でき、長く働くほど対応できる領域を増やしていけます。貴社の編集業務でも、新しいことに積極的に挑戦できる私の強みを活かせると考えております。
ADHDの方の自己PRでの注意点
ADHDの方が自己PRを作成する際は、自分を過小評価したり、反対に能力を誇張したりしないことが大切です。発達障害の特性で多くの失敗を経験した結果、自信をなくしてしまう人も少なくありません。しかし、自己PRでは自分の強みを正確にアピールするのが大前提です。
また、内定が欲しいからといって自分の能力を誇張して伝えるのも、入社後にミスマッチが起こりやすくなるので避けましょう。あくまでも自分を客観的に分析し、事実をもとに自分の強みを伝えるよう心がけてください。
さらに、自己PRに制限時間がある場合を考慮する必要があります。面接では自己PRの時間を1分や3分といった形で指定されることも多いです。実際に話したときの時間を意識しながら、簡潔なパターンとしっかりアピールするパターンを両方を用意しておくことをおすすめします。
面接で自己PRを伝えるうえで大切なこと
自己PRは書類に書いて提出するだけでなく、面接でも言葉にして伝えることが求められます。アピールすべきポイントなどを押さえ、面接官に好印象を与えられるようにしましょう。
ここからは、ADHDの方が面接で自己PRを伝えるときのポイントを紹介します。
要点を押さえて簡潔にまとめる
就活の自己PRでは、限られたスペース、限られた時間でアピールポイントを伝えなければなりません。
しかし、ADHDの方は特性の影響もあり、伝えたいことをうまくまとめられない傾向があります。これにより話が長くなってしまう場合があるため、要点を押さえて簡潔にまとめることを意識しましょう。
簡潔に話すコツは、基本的な構成を利用することです。わかりやすい自己PRは、おおむね次のような要素で構成されています。
- 結論(自分の強み)
- 結論の根拠
- 過去に直面した課題
- 課題を乗り越えた方法
- 経験を通して学んだこと
- 会社に貢献できるポイント
上記の構成に自分の経験や主張を当てはめると、簡潔でわかりやすい形で自己PRを伝えられるでしょう。
興味や学習意欲をアピールする
未経験の業種や職種に挑戦する場合、仕事の経験からアピールできることが少ないかもしれません。そんなときは、業務内容への興味や学習意欲をアピールするとよいでしょう。
例えば、応募企業の事業領域に関する知識を学んでいる、資格取得に励んでいるなどが挙げられます。「以前の会社では積極的に学んでスキルを伸ばした」というように、仕事熱心な面を伝えるのもおすすめです。
その他、ポジティブな考え方ができることや粘り強く業務に取り組めることなど、どの仕事でも役立つ性質を伝えるのも効果的です。
障害のエピソード以外も用意する
障害者雇用の場合、面接の中で障害について聞かれることが多いです。重複を防ぐために、自己PRの内容は障害に関係のないエピソードも用意しておくことをおすすめします。
障害のある方の就活では、どうしても特性による課題を乗り越えたエピソードを用意しがちです。しかし、面接では他の部分でも障害のことを聞かれることがあり、他のエピソードを用意しておかないと同じ内容を繰り返し話してしまうことになりかねません。
自己PRに障害に関するエピソードを入れてはいけないわけではありませんが、かぶらないエピソードもあると安心です。企業に多角的な自分を見てもらい、限られた時間で効率的に自分をアピールするためにも、いくつか異なるエピソードを用意してみましょう。
もし自己PRが上手く書けなかったらどうする?
課題を乗り越えたエピソードなどが思いつかず、自己PRをうまく書けない場合もあるでしょう。自分一人で自己PRの作成が難しい場合は、就活支援をしている専門機関を頼るのも一つの方法です。
代表的な支援機関としては、就労移行支援事業所が挙げられます。就労移行支援事業所では、専門のスタッフが自己PRの作成や面接の練習などをサポートしてくれます。自己分析の助けとなる講座なども実施しているため、行き詰まりを感じたら積極的に助けを求めるとよいでしょう。
Kaienの就活支援
発達障害の方の就労支援に特化しているKaienでは、障害のある方向けに「ガクプロ」「就労移行支援」「自立訓練(生活訓練)」などの福祉サービスを提供しています。自己PRがうまく書けないときは、これらのサービスを活用して専門家の支援を受けるとよいでしょう。
ここでは、先に挙げたKaienの支援サービスを詳しく紹介します。
ガクプロ
Kaienのガクプロは、「国内最大の就活サークル」というテーマを掲げ、障害特性のある学生に向けて就活やライフスキル習得のための支援を行っています。2012年の誕生から1,500人以上が利用している、実績豊富な支援サービスです。
例えば、キャリア・コーチングでは職業選択や面接の準備をサポートします。就活支援は、自己PRなどの書類作成からオンライン面接まで対応する丁寧なフォローが特徴です。障害者雇用を基本として、インターンシップや求人の紹介も行っています。
就労移行支援
Kaienの就労移行支援は、障害のある方の就業をサポートする障害福祉サービスです。就活支援が充実しており、自己PRの作成を手伝うのはもちろん、面接の練習や同行、独自求人の紹介なども行っています。
就活に役立つスキルや知識を身につけられるのも、Kaienの就労移行支援の魅力です。全員に実施される適職アセスメントや、実践的なPCスキルを養うプログラムなどを豊富に用意しています。
Kaienでは約2,000人超の就職実績があり、就職後の定着率も95%と高水準です。就活のサポートを求めている方は、Kaienの就労移行支援をぜひご活用ください。
自立訓練(生活訓練)
Kaienの自立訓練(生活訓練)は、就活の前段階として自分の強みを見つけたい方におすすめのサービスです。自分自身を見つめ直し、視野を広げる訓練を通して将来設計を再構築することができます。
Kaienの自立訓練(生活訓練)で養うことができるのは、感情や睡眠のコントロール、コミュニケーション、スケジューリング、お金の管理といった生活スキルやソーシャルスキルです。地域の職場や施設を見学し、将来的に働くイメージを膨らませることも可能です。
就活の前に自分の強みを見つけたい方は、100以上のプログラムを体験できるKaienの自立訓練(生活訓練)の利用を検討してみてください。
ADHDの特性を活かした自己PRの作成を
ADHDの方が就活に臨む際は、特性を強みとしてアピールする方法が効果的です。集中力や発想力、行動力などの強みを軸に自己PRを作成し、企業に自分の魅力を伝えるとよいでしょう。
なかなか自己PRを作成できずに悩んでいるときは、就労移行支援などの福祉サービスを利用するのがおすすめです。Kaienでは見学・個別相談会を随時開催しているので、興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修者コメント
ADHDをオープンにして自己PRを書く、というタスクはなかなか難しい部分もあろうかと思います。私自身は面接を伴う本格的な就職活動の経験が無いため(私の世代の医師はほとんどがそうです)、いつも就職活動を頑張っている方を尊敬の目で見ています。
PRということに関しては正直苦手な人がほとんどではないでしょうか。何が自分の強みかは案外自分でわかっていなかったり、感覚的にはわかっていても明確に言語化できないことが多いはずです。その意味で、就労移行支援を始めとした支援者に自分の特性、長所/短所を把握してもらうのはとても意味があります。頼ってみてください。主治医も把握していなくてはいけないのですが、やはり明確にはできていないことがあります。良い自己PRが出来上がった折には主治医にも報告してみてください。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。