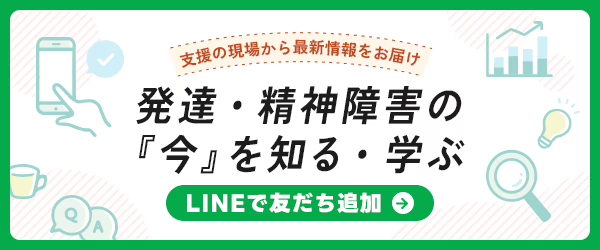就活の際に、「面接で思うように振る舞えない」と感じているADHD(注意欠如多動症)の方も少なくありません。面接は合否に大きな影響を与えるため、自分の特性や症状に応じて対策を講じておくことが大切です。苦手な事柄に対する克服方法や練習方法を知ることで、希望する企業にも就職しやすくなるでしょう。
この記事では、ADHDの方が面接を苦手とする理由や、その対策方法などについて解説します。ADHDの方が面接練習に利用できる支援機関も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
ADHDの方が面接を苦手とする理由
ADHDの方は、発達障害*特性によって面接に困難を抱えるケースがあります。面接が苦手だと感じている場合は、まずADHDの方によく見られる特性を確認してみましょう。自分に当てはまるものがある場合は、把握しておくことで対策を講じやすくなり、苦手の克服に一歩近づけます。
ここからは、ADHDの方が面接を苦手とする理由をケース別に紹介します。
話をうまくまとめられない
ADHDの方は、話をうまくまとめられないことから、面接でうまく受け答えができない傾向があります。話をまとめられない理由の一つとして、ワーキングメモリが低いことが挙げられます。短期記憶が苦手で、自分が直前に話した内容を忘れてしまい、全体として脈絡のない話になってしまうことがあるのです。
また、思考が目まぐるしく変化する脳内多動も一因です。考えが次から次へと思い浮かんでコントロールしづらくなるため、一貫性のない話になる傾向があります。
加えて、物事を俯瞰してみる中枢性統合の弱さも理由に挙げられます。中枢性統合が弱いと、頭の中だけで全体像を把握して情報を整理するのが難しく、まとまりのない話になりやすいのです。
話を最後まで聞けない
相手の話を最後まで聞くのが難しい傾向が、ADHDの方にはよく見られます。これは、ADHDの特性である衝動性や前述の脳内多動の影響によるものです。思いついたことをすぐに口にしたくなり、人の話をさえぎって話し始めてしまうことがあります。
面接官の話を最後まで聞けなければ、相手の質問の意図もくみ取れません。その結果、適切な回答ができず、面接でうまく立ち回れなくなるのです。
とくにグループ面接では、他の応募者の話を遮ってしまうと、協調性に欠ける印象を与えかねません。面接官にマイナスな印象を与えることがないよう、相手の話に耳を傾ける姿勢を意識することが大切です。
落ち着きがなく集中力が持続しない
ADHDの方は、衝動性や不注意といった特性により、周囲の音や人の動きに影響を受けやすく、注意散漫になりやすい傾向があります。このような落ち着きのなさが、面接で悪影響を及ぼすことがあるでしょう。
面接中は礼儀正しい態度が求められますが、ADHDの方はじっとしていられず、つい体が動いてしまう場合があります。また、集中できずに質問の内容を聞き逃し、相手の求める回答ができない、あるいは聞き返すことになるといったケースも考えられます。
緊張しやすい方だと、必要以上に急いで答えようとしてしまい、論理的で説得力のある話し方ができなくなるということもあるでしょう。
言葉が出ずに固まってしまう
面接で質問をされた際、言葉が出ずに固まってしまうこともよくある悩みの一つです。
ADHDの方は処理速度やワーキングメモリが低い傾向にあり、答えるのに時間がかかることも多くあります。なかなか考えがまとまらず、思考が停止してフリーズしてしまうと、面接官の心証を害する恐れもあります。
また、緊張で頭が真っ白になり、質問に答えられなくなるケースもあるでしょう。特に、ADHDの特性による二次障害で社会不安障害などを併発している場合は、人前で緊張しやすくなります。
発達障害の二次障害については以下の記事で紹介していますので、併せてご覧ください。
ADHDの方の採用面接の対策方法
障害の有無にかかわらず、面接をうまく乗り切るためには対策することが重要です。自己分析や台本の用意、模擬面接など、特性を踏まえた対策に取り組めば、自信回復にもつながるでしょう。自分なりの工夫を凝らしながら、面接の準備を進めてみてください。
ここからは、ADHDの方が面接への苦手意識を克服するために有効な対策方法を6つ紹介します。
自己分析をする
ADHDの方が採用面接に臨む際は、第一に自己分析をすることが重要です。
面接では企業側に自分の強みをアピールする必要があります。自己分析を通して障害の特性を理解したり、得意不得意を整理したりしておくと、人材としての自分の魅力を論理的に訴えられるようになります。
また、自分の特性に合った企業を選べるようになり、ミスマッチを防ぐ効果も得られるでしょう。就活前に必ず、自己分析で自分の強みやキャリアビジョン、大切にする価値観などを明確にしたうえで、面接に臨むことをおすすめします。
スケジュールを管理する
ADHDの方は、特性により計画を立てて物事を進めるのが苦手な傾向にあります。例えば、他の作業に集中しすぎて時間を忘れ、予定に遅れてしまうといったこともあるでしょう。
採用面接では、約束の時間に間に合わず、遅刻した時点で内定をもらうのは難しくなります。そのため、遅刻などがないよう、しっかりとスケジュール管理をすることが大切です。
具体的には、スマートフォンのスケジュール管理アプリやリマインド機能を活用する方法が挙げられます。また、時間や目的地をメモや付箋に記し、見えるところに貼っておくのも、やるべきことが可視化されるのでおすすめです。
台本を用意する
話をまとめられなかったり、緊張して何を話せばよいかわからなくなってしまう方は、面接に備えて台本を用意することでスムーズに受け答えがしやすくなります。面接で想定される質問内容と、自分なりの回答をメモに書き出してみましょう。
質問と回答を書き出して視覚化すれば、受け答えのイメージを整理しやすくなります。また、客観的な視点からメモや台本を分析すれば、改善点も見つけられます。
台本を書くときは、本番同様の丁寧な話し言葉で書き出すのがおすすめです。書き言葉で台本を覚えてしまうと、本番で話すときに違和感のある口調になったり、スムーズに言葉が出なかったりする恐れがあります。
結論から話して簡潔にまとめる練習をする
だらだらと長い回答は焦点がぼやけがちで、結局何が言いたいのか相手に伝わらないことが多いです。また、他の求職者もいる中で、自分勝手な印象を与えてしまう恐れもあります。
そこで、回答が長くならないよう、質問に対しては先にYes/Noで答える、結論から伝えるということを意識するとよいでしょう。先に結論を示すことで回答の軸が定まり、筋の通った論理を展開しやすくなります。
適切な回答の長さは、30秒〜1分以内が目安となります。1分間話す場合の文字数は300〜400字程度なので、この文字数を意識して台本を書いてみてください。
話が詰まったときのフレーズを用意する
集中力が切れたり、緊張で頭が真っ白になったりすると、話が詰まってしまいます。対策をしておかないと、面接中にそのままフリーズしてしまう恐れがあるので注意しましょう。
何を言えばいいのかわからなくなったときに備え、事前に以下のようなフレーズを用意しておくとおすすめです。
- 「すみません、少しお時間をください」
- 「うまくまとまらなかったので、もう一度質問していただけますか」
言い慣れた言葉を口にすることで心も落ち着きやすくなるので、ぜひ試してみてください。
模擬面接を行う
面接でスムーズな受け答えができるかどうかは、経験の量に左右されます。まったく面接の経験がない状態だと、回答がまとまらなくてパニックになるなどのリスクも高くなります。そのため、模擬面接を行い、応対の雰囲気に慣れておきましょう。
模擬面接のやり方としては、まず想定問答集を作成し、それをベースに家族などの第三者の協力を仰いで面接練習を行います。面接練習を繰り返し、問答集を改善しながらレベルアップを図るとよいでしょう。
なお、模擬面接は後述する支援機関でも練習できます。第三者の視点から改善のためのアドバイスもしてもらえるため、支援機関も積極的に活用してみましょう。
ADHDであることは面接で言うべき?
「ADHDのことを面接で言うと不利になるのでは」と不安を感じている方も多いでしょう。結論から言うと、障害を開示して応募している場合は、面接でも自分の障害や特性は伝えることをおすすめします。
企業側にとって、求職者が自分の特性をどれくらい理解していて、困りごとが生じた際もサポートを求めるなどの形で柔軟に対応できるかどうかが知りたいポイントです。ADHDであることは隠さずに伝え、困難を乗り越えたエピソードなどを客観的に話すのがよいでしょう。
ただし、困りごとをすべて伝えるのではなく、2〜3個に絞って簡潔に伝えることが重要です。なお、一般雇用の場合でも障害のある方は職場で合理的配慮を受けられるため、後から伝えるよりは隠さないで伝えておいたほうがよいでしょう。
面接で配慮事項を伝える方法
面接で配慮事項を伝えるときは、工夫ポイントとセットで伝えましょう。「特性により音や周囲の動きで注意散漫になりがちなため、集中して業務に取り組めるよう、静かな環境で作業できる部署を希望します」など、理由と希望する処遇を具体的に伝えてみてください。
配慮事項をうまく伝える自信がない場合は、別の書類を用意して提示したり、想定問題集を見ながら回答したりする方法もあります。「特性によりうまく伝えられない」「なるべく正確に伝えたい」などと前置きしたうえで、希望する配慮事項を詳しく伝えるとよいでしょう。
ただし、障害のある方への配慮は企業にとって合理的な範囲で提供されるものです。伝達した希望がすべて実現するとは限らないので、その点には留意しましょう。
ADHDの方が面接対策に利用できる支援機関
ADHDの方が面接対策に悩んでいる場合は、支援機関を利用するのがおすすめです。専門家に協力してもらうことで、効率的に面接のコツがつかめます。
ADHDの方が面接対策に利用できる支援機関としては、主に以下が挙げられます。
- ハローワーク
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援
ハローワークは障害の有無を問わず誰でも利用できる公的機関で、仕事に関する全般的なサポートを提供しています。障害者就業・生活支援センターは、障害のある方の身近な地域において、職業生活における自立を目的として利用できる支援機関です。履歴書の書き方指導や面接練習などの就業面と、生活面の両方から相談支援を行っています。
一方、就労移行支援は、障害のある方の一般企業への就労を支援する福祉サービスです。三者三様でサポート内容に細かな違いがあるため、自分に合った機関を選ぶようにしましょう。
Kaienの面接対策&就労支援
Kaienでは、発達障害などの障害がある方に向けて、就労移行支援をはじめとした福祉サービスを提供しています。専門スタッフのサポートを受けながら面接対策やビジネススキルの習得ができるため、面接が苦手で悩んでいる方や就活にお困りの方はKaienの利用がおすすめです。
ここからは、ADHDの方が利用できるKaienの3つの支援サービスを詳しく紹介します。
ガクプロ
Kaienのガクプロは、「国内最大規模の就活サークル」をテーマに掲げ、障害のある学生を対象に生活スキルや就活スキルの習得をサポートしています。「障害福祉が使えない学生向けの支援が欲しい」という声を受けて2012年に誕生し、これまでに1,500人以上が参加した実績があるのが強みです。
Kaienのガクプロの特徴は、自発的に動くのが苦手な学生に向けてコーチングを導入していることです。面接準備や職業選択の支援を行うキャリア・コーチング、学習方法のアドバイスをするアカデミック・コーチングなど、多角的に学生生活を支えています。
就活支援も充実しているため、面接対策に悩んでいる学生の方はKaienのガクプロの利用を検討してみてください。
就労移行支援
Kaienの就労移行支援は、これまでに2,000人以上の就活や就労を支援してきた実績があります。支援員のうち、専門資格を保有している割合は約87%で、専門的な視点から効果的なサポートを提供しています。
Kaienの就活支援では、面接練習はもちろん、書類作成や面接同行、独自求人の紹介なども行っているのが特徴です。障害者雇用だけでなく一般雇用の実績も豊富なので、希望の会社を見つけやすいでしょう。
その他、PCスキルやビジネススキルの習得支援、医療と連携したカウンセリングなど、充実のサービスが利用できます。面接がうまくいかないと感じているADHDの方は、Kaienの見学・個別相談会にぜひ足を運んでみてください。
自立訓練(生活訓練)
就活の前段階として、まず生活スキルやコミュニケーションスキルを身に付けたいと考えている方には、Kaienの自立訓練(生活訓練)がおすすめです。
Kaienの自立訓練(生活訓練)では、自分を見つめ直して将来を再設計するためのサポートを行っています。プログラム内容は、不安やストレスを緩和する対処法の実践、具体的なコミュニケーション手法の学習などです。また、職場や施設の見学・体験を通して進路を探求するプログラムも実施しています。
Kaienの自立訓練(生活訓練)で就活前に、社会生活を長く送るための準備をしてみてはいかがでしょうか。
事前の準備と対策でADHDの特性に対応を
ADHDの特性で面接が苦手だと感じている方も、適切な対策を講じれば今よりスムーズな受け答えができるようになります。まずは自己分析を通じて自分の特性を見極め、想定問答集などを作成して練習を繰り返すとよいでしょう。
自力での対策が難しいと感じる場合は、支援機関のサポートを利用するのがおすすめです。Kaienでは、ガクプロや就労移行支援、自立訓練(生活訓練)などを実施しています。自分に合った支援サービスを利用し、面接の苦手克服を目指しましょう。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修者コメント
ADHDの方に私がしばしば感じるのは、能力を活かしきれていない、という面です。アメリカのT.E.ブラウンという心理学者はADHDの方の認知能力の特徴は「変動してしまうこと」と表現しています。わたしたちは現実世界の中で様々な環境で能力を発揮しなくてはいけません。静かな環境、騒がしい環境、お腹の空いているとき、いらいらしているとき、人前で緊張してしまうとき、時間に追われているとき…など様々な場面で持っている能力発揮が求められます。ADHDの方はそういった様々な条件で均等に能力を発揮することが苦手と言えるでしょう。もちろん誰しもが苦手な環境を持っていますが、そのような場面と、十分に能力を発揮できるときとの差が激しいのです。苦手な能力を求められるときは尚更です。自分の持っている得意/不得意の把握と同時に、どのような場面が苦手か?という観点からも対策を練ってみてください。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。