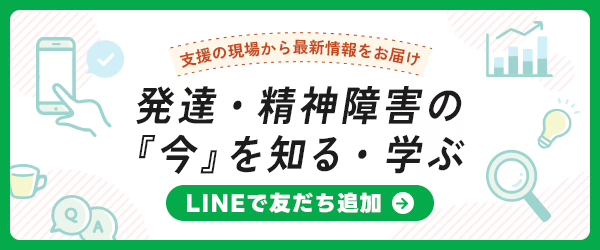新卒で障害者雇用を目指す場合、「新卒での障害者雇用は本当に可能なのか」「どのように企業を選ぶべきか」など、さまざまな疑問を抱える人も多いでしょう。近年、障害者雇用における新卒採用のニーズが高まっていて、障害者の新卒採用に積極的に取り組む企業が増えています。
この記事では、障害者雇用と一般雇用の違いや、新卒で障害者雇用を選ぶメリット・デメリット、障害者雇用の給料、企業が新卒の障害者雇用を重視する理由、就職活動を進める際の注意点、障害者雇用に関する相談先を解説しています。ぜひチェックしてみてください。
目次
障害者雇用と一般雇用の違い
障害者雇用は、障害者手帳を持つ人を対象とした雇用枠です。障害に関する症状や特性、得意なことや苦手なことなどを事前に職場に伝え、合理的配慮を受けながら働くことができます。
一般雇用は、障害の有無に関わらずすべての人を対象とした雇用枠です。求人の募集要項を満たせば、誰でも応募できます。
障害を持つ人は、障害者雇用と一般雇用のどちらを利用するか選ぶことが可能です。例えば、「合理的配慮を受けながら自分のペースで働きたい」という人は、障害者雇用が向いているでしょう。もちろん、希望の条件を満たす一般雇用の求人があれば、それに応募することもできます。
障害者雇用促進法により、従業員が40人以上いる事業主には、少なくとも1人以上の障害者を雇用する義務があります。そのため、多くの企業が障害者雇用枠を設けており、障害者の新卒採用に力を入れている企業も少なくありません。
新卒で障害者雇用で働くメリット
新卒で障害者雇用で働くメリットは、障害の特性に応じた配慮やサポートが受けられることです。障害者雇用では障害について職場にオープンにするため、働くうえでの負担が少なくなるよう勤務時間や業務内容を調整してもらえます。
以下は、合理的配慮の具体例です。
- 定期的な通院のための休暇の付与
- 短時間勤務やフレックス勤務、時差出勤の許可
- 特性により難しいと感じる業務(例:人前でのプレゼンテーションや電話対応など)の免除
- 音や光に敏感な人に対して、周囲の音量や照明など作業環境の調整
さらに、働き始めてからの配慮だけでなく、選考時から配慮を受けられるのも障害者雇用の特徴です。例えば、聴覚に障害を持つ人が選考を受ける際、手話通訳の手配や筆談での対応をしてもらえるケースがあります。
障害によって就職活動や就職後の働き方に不安がある人は、それぞれに合ったサポートを受けられる障害者雇用の利用がおすすめです。
新卒で障害者雇用で働くデメリット
新卒で障害者雇用を利用する際の注意点として、一般雇用と比べて求人数が少ないことが挙げられます。応募先の選択肢が限られるため、希望に合う求人を見つけるまでに時間がかかるかもしれません。
また、障害者手帳を取得しなければ応募できないのもデメリットのひとつです。手帳をまだ取得していない人は、まず手帳の取得手続きから始めなければなりません。障害者手帳の交付には1〜2ヶ月程度かかるため、就職活動をスムーズに始められるように、早めに準備を進めておきましょう。
障害者雇用の給料
厚生労働省の「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」によると、障害別の給与平均は以下のとおりです。
| 区分 | 1ヶ月の平均賃金 | 週あたりの労働時間別の1ヶ月の平均賃金 | |||
| 30時間以上 | 20〜30時間未満 | 10〜20時間未満 | 10時間未満 | ||
| 身体障害者 | 23 万5,000円 | 26万8,000円 | 16万2,000円 | 10万7,000円 | 6万7,000円 |
| 知的障害者 | 13 万7,000円 | 15万7,000円 | 11万1,000円 | 7万9,000円 | 4万3,000円 |
| 精神障害者 | 14万9,000円 | 19万3,000円 | 12万1,000円 | 7万1,000円 | 1万6,000円 |
| 発達障害者 | 13万円 | 15万5,000円 | 10万7,000円 | 6万6,000円 | 2万1,000円 |
新卒の障害者雇用に関する企業の動向
新卒で障害者雇用を利用しようと考えている人は、企業の障害者雇用に関する動向についても理解しておくことが大切です。障害者雇用を推進している企業では、以下のような傾向が見られます。
- 新卒採用のニーズは高まっている
- 身体障害者の採用ニーズが高い
これら2点について、以下で詳しく紹介します。
新卒採用のニーズは高まっている
近年、障害者雇用における新卒採用のニーズが高まっています。その背景のひとつが、法定雇用率の引き上げです。従業員が40人以上の企業には、従業員に占める障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。この法定雇用率は令和6年(2024年)4月に2.5%に引き上げられており、さらに令和8年(2026年)7月には2.7%になる予定です。
これにより、これまで法定雇用率を達成していた企業でも、さらに障害者を雇用する必要が出てきました。その結果、障害者の新卒採用に積極的な企業が増えてきています。
また、新卒採用のニーズが高まっている理由には、中高年層の退職に備えるという目的もあります。新卒採用を通じて若い世代の従業員を確保し、長期的に活躍してくれる人材に育てたいと考えているのです。
参考:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
身体障害者の採用ニーズが高い
障害の種類別に見ると、特に採用ニーズが高いのは身体障害者です。厚生労働省の「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」によると、令和5年(2023年)の障害の種類別の雇用者数は次の通りでした。
- 身体障害者:36万157.5人
- 知的障害者:15万1,722.5人
- 精神障害者:13万298.0人
ちなみに、最も多く雇用されているのは身体障害者ですが、雇用者数の増加率が最も大きいのは精神障害者です。精神障害者の雇用者数は、前年から18.7%増加しました。
企業が新卒を障害者雇用で雇うメリット
ここでは、企業が積極的に新卒を障害者雇用で雇うメリットについて解説します。企業側の採用事情を知っておくと、就職活動に役立つ部分もあるでしょう。
企業や職場に適応できる可能性が高い
企業が新卒雇用を重視するのは、大学を卒業した方は社会人としての適応力が高いと考えているからです。
例えば、大学への通学にはある程度の体力が必要ですし、授業に遅れないように時間を守る力も求められます。大学の授業をこなすには一定の学力が求められ、生活のなかではさまざまな方と関わり、コミュニケーションも学んでいます。これらの経験により、新卒の方は仕事にも順応しやすいとみなされることが一般的です。
また、新卒の方は他の会社で働いた経験がないため、企業のルールや働き方を柔軟に受け入れやすい特徴があります。このように企業文化になじみやすい方は、帰属意識を持ちやすく、長く働いてくれると期待されています。
一般枠とあわせて募集しやすい
新卒の障害者採用には、一般の採用活動と同じスケジュールで進められるメリットがあります。新卒採用のスケジュールに合わせることで、採用選考だけでなく、入社後の研修や教育プログラムまで一貫して進めやすくなるからです。
例えば、新入社員研修を一斉に実施することで、障害のある方も含めて同じ内容の研修を受けられます。これにより、研修担当者の負担が軽減されるだけでなく、新卒全員が同じタイミングで企業文化や業務の基本を学べます。
受け入れの準備期間を設けやすい
企業は、新卒の採用活動において、内定から入社までの期間を長く確保できます。この期間があることで、企業側は受け入れ体制を整える時間を十分にとれます。
例えば、障害のある方を受け入れる部署では、バリアフリー化や職場環境の整備、障害についての理解を深めるための研修などを計画的に進められるでしょう。
新卒の障害者雇用の選考スケジュール
一部の企業では、一般雇用と障害者雇用の新卒採用を同じスケジュールで進めています。この場合、大学3年生の3月ごろから企業説明会が始まり、6月ごろから選考へと進んでいきます。
一方で、障害者雇用を通年採用を実施している大企業も多く、一般雇用の採用と異なるスケジュールで選考を進めているケースも見られます。このように採用スケジュールは企業によって異なるため、希望する企業の対応については個別に確認が必要です。
就職活動の際、障害者雇用枠と一般雇用枠を併用している人も少なくありません。冒頭で紹介したとおり、一般雇用は障害の有無に関わらず誰でも応募できるので、「雇用枠の種類は気にせず、気になった求人に応募してみる」という進め方もあります。
新卒で障害者雇用を目指す場合の企業選びのポイント
新卒で障害者雇用を目指す場合、企業選びが重要です。自分に合った職場を選んで長く働けるように、就職活動の際には次の3つのポイントを押さえておきましょう。
- 雇用実績を確認する
- 環境や配慮・サポートを確認する
- 企業見学で職場を確認する
それぞれどのような点を確認すべきなのか、以下で詳しく解説します。
雇用実績を確認する
雇用実績は、その企業がどれだけ障害者雇用に積極的に取り組んでいるのか、障害者に対するサポート体制がどの程度整っているのかなどを知る手がかりとなります。例えば、自分と同じ障害を持つ人の採用実績がある企業なら、働きやすい環境が整っている可能性が高いと判断できるでしょう。自分と同じ障害でなくとも、障害者雇用の実績が多い企業なら障害への理解があり、障害者を受け入れるノウハウがあると考えられます。
また、定着率を公開しているかどうかもチェックしてみてください。障害者の定着率が高い企業なら、就職後に長く働ける可能性が高いでしょう。
環境や配慮・サポートを確認する
企業によっては、障害を持つ人への具体的な配慮・サポートの内容を公表しているケースがあります。その企業のホームページやパンフレットを確認し、障害者雇用に関する記載がないかチェックしてみましょう。
例えば、視覚障害者のために拡大モニターを設置したり、聴覚障害者のために集音器を提供していたりする企業もあります。また、オフィスのバリアフリー化やユニバーサルトイレの設置など、職場環境の整備に取り組んでいるケースも見られます。
さらに、通院のための休暇やフレックスタイム制など、働き方に関する配慮を行っている企業もあります。環境や配慮で働きやすさは大きく変わってくるため、応募する前に確認しておくことが大切です。
企業見学で職場を確認する
企業見学は、障害者雇用を検討している方にとって、職場の雰囲気や仕事内容を実際に確認できる貴重な機会です。応募前に見学することで、自分に合った職場かどうかを具体的に判断でき、ミスマッチを減らせます。
見学会では、以下のような機会が提供されています。
- 仕事場や休憩室の環境や設備を見学する
- 社員が働いている様子を見て、職場の雰囲気を感じる
- 障害のある社員がどのように仕事をしているかを見る
- 実際に働いている社員に話を聞く
- サポート体制や配慮の内容について、企業の担当者から説明を受ける
企業見学に参加するには、支援機関やハローワーク、自治体などの案内を通じて申し込む方法があります。
障害者雇用を目指し就職活動をすすめる前の注意点
障害者雇用を目指した就職活動をスムーズに進め、自分に合った職場を見つけるために、次の2点に注意しましょう。
- 主治医に事前に相談する
- 障害への理解を深める
- 心身の体調を整える
- 利用できる制度や支援を活用する
これら2つの注意点について、以下で詳しく解説します。
主治医に事前に相談する
定期的に通院している人は、就職活動について事前に主治医に相談するようにしましょう。障害の症状や現在の体調によっては、就職活動を進めること自体が大きな負担になる可能性があります。就職活動を始めても問題ないか、必ず主治医に確認を取るようにしてください。
また、主治医は障害の特性や健康状態について十分に理解しているので、企業選びや働き方について具体的なアドバイスをもらえるでしょう。「どのような仕事なら無理なく取り組めるか」「どのくらいの時間なら働けるか」といったアドバイスは、求人を選ぶ際にとても参考になります。
障害への理解を深める
障害を持つ人の就職活動では、自分の障害についての理解を深めておくことが重要です。例えば、どのような作業が得意で、逆にどのような状況が負担になるのかを明確に把握しておけば、無理なく働ける仕事を選べるでしょう。
また、障害への理解を深めることは、面接の際に自分自身について正確に伝えるためにも役立ちます。自分の強みや必要な配慮を明確に説明できれば、企業とのミスマッチを防ぎ、自分に合った職場を見つけやすくなるでしょう。
障害への理解が不十分では自分に合わない求人に応募してしまうリスクがあり、「なかなか内定が出ない」など就職活動の負担が増えてしまう可能性があるため注意しましょう。
心身の体調を整える
就職活動を成功させ、その後も安定して働き続けるためには、心身の体調を整えることが大切です。企業も心身の安定を採用基準として重視しているため、自己管理がしっかりできる方は評価されやすくなります。
まず、自分の体調や症状の変化に敏感になることがポイントです。例えば、睡眠不足や食生活の乱れが原因で体調を崩してしまう場合には、生活リズムを見直すことで改善できるかもしれません。
さらに、自分の状態を見える化する工夫も大切です。毎日の体調を記録しておくことで、どのタイミングで体調が崩れやすいのかがわかります。これにより、企業に対しても「このような配慮があれば安定して働けます」と具体的に伝えやすくなります。
利用できる制度や支援を活用する
障害者雇用での就職活動では、障害への理解を深めたり、就活の対策を行ったりするなど、自分一人では難しいことも多々あります。一人で悩まず、利用できる支援を積極的に活用するとよいでしょう。
後ほど詳しく紹介しますが、各支援機関では、特性の理解を深めるカウンセリングや適職探しのアドバイス、面接対策、職業訓練、生活面のサポートなど、さまざまなサービスが提供されています。
こうした専門家のフォローを受けることで、自分の負担を軽減しながら、自分に合った企業や職種を見つけやすくなり、採用の可能性も高まります。
障害者雇用についての相談機関
障害者雇用についてわからないことや不安なことがある人は、次のような機関に相談してみましょう。
- ハローワーク
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
- 就労移行支援
それぞれの相談機関について、以下で紹介します。
大学のキャリアセンター
大学のキャリアセンターとは、学生の就職活動や進路選択を支援する専門の部署です。
キャリアセンターで受けられる主なサービスには、自己分析のサポートや面接対策、履歴書の書き方指導などがあります。また、企業の求人情報やインターンシップ情報の提供、合同説明会の案内も行われており、効率的に就職活動を進められるようサポートしています。
障害者雇用を希望する学生に向けて、障害特性に配慮した面談や、障害者雇用を行う企業の求人情報の提供など、特別な支援を実施している大学も少なくありません。
ハローワーク
全国のハローワークには障害者専用の相談窓口が設けられていて、障害者雇用に詳しいスタッフが常駐しています。自分に合った求人探しや応募書類の作成サポート、面接対策など、幅広い支援を受けることが可能です。
ハローワークは中途採用を目指す人が利用するイメージがあるかもしれませんが、新卒採用についても相談できます。全国56か所、各都道府県に1か所以上のハローワークで「新卒応援ハローワーク」という取り組みを実施していて、新卒採用の就職活動について無料で相談を受け付けています。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、障害を持つ人への職業リハビリテーションを提供する機関です。専門スタッフが個々の職業能力などを評価し、就職や職場への適応を目指して必要な支援を行います。また、センター内で作業体験や職業訓練を受けられるので、就職に必要なスキルを身につけたい人にもおすすめです。
地域障害者職業センターでは、職場にジョブコーチを派遣して職場定着を支援する取り組みを行っているのも特徴です。就職後に困ったことがあれば、ジョブコーチに相談して職場に働きかけてもらうことができます。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害を持つ人が就労しながら安定した日常生活を送るための総合的なサポートを提供する機関です。利用者には就業支援担当と生活支援担当がそれぞれ付き、就業面と生活面を一体的にサポートします。
就業面では自分に合った仕事探しのサポートや就職後の定着支援、生活面では生活習慣の改善や健康管理、金銭管理などについてのアドバイスが受けられます。また、ハローワークや障害者を雇用する企業、福祉事務所や医療機関といった関係機関と連携しながら、適切な支援につなげてくれるため安心です。
就職活動だけでなく日常生活に関するサポートも受けたい人は、障害者就業・生活支援センターの利用を検討してみましょう。
就労移行支援
就労移行支援は、障害を持つ人が一般企業への就職を目指す際に利用できる障害福祉サービスです。全国にある就労移行支援事業所に通い、職業訓練や就職活動のサポートを受けることができます。
基本的に失業者を対象としたサービスですが、休職中の人や学生も一部利用可能です。利用条件は自治体によって異なるため、在学中の人は就労移行支援の利用が可能かお住まいの自治体に問い合わせてみてください。
就労移行支援では、それぞれの障害特性や能力に応じて個別支援計画を作成し、職業訓練や就職活動に取り組みます。就職活動についてスタッフと相談しながら計画を立てられるので、初めての就職活動に不安を感じている人でも安心です。
特定の業種やスキルに特化したカリキュラムを提供している就労移行支援事業所もあります。希望する職種が決まっている人は、そのために必要なスキルを習得できる事業所を探してみてください。
新卒は障害者雇用のニーズも高い
法定雇用率の引き上げや中高年層の退職などの背景によって、障害者雇用における新卒へのニーズは高まっています。障害者雇用には合理的配慮が受けやすいという大きなメリットがあるため、障害を持つ人は障害者雇用の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
初めての就職活動で、特に障害者雇用についてはわからないことや不安なことも多いでしょう。ハローワークや就労移行支援など、障害者雇用に関する相談先は複数あるため、積極的に利用してみてください。
就労移行支援の利用を検討している方は、ぜひKaienにご相談ください。Kaienでは、発達障害*の強みを活かした就労移行支援を実施しています。また、発達障害・グレーゾーンの学生向けの支援カリキュラム「ガクプロ」では、職業体験や就職講座が受けられます。見学・個別相談会も実施しているので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
大学に進学してから高校までの生活と異なり、発達障害と初めて診断される方がいらっしゃいます。こういう方々も一度は一般就労を検討しますが、就職活動の経験を通して「とても自分には勤まらない」とうつ状態になることもあります。
こういう方には思い切って障害者雇用を検討してみることを勧めています。そうすると、大きな会社の特例子会社に就職が決まるケースも少なくありません。「大学まで行ったのに最初から障害者雇用かあ…」というため息も聞かれますが、発達障害の方はご自分にあった穏やかな環境でのびのびすることで活躍するチャンスが広がる特性を持っているため、就労環境重視で仕事を考えてみるのも悪い選択肢ではないと思います。
ご家族、友人、主治医、そして就労支援事業所スタッフなどいろいろな方に話を聞いて、ご自分に合った環境を探してみましょう。

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。