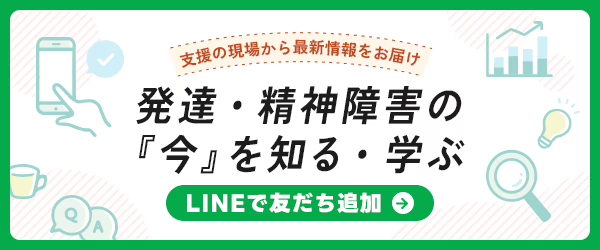リワークとは、うつ病や適応障害などの精神疾患により休職している人が、職場復帰できるように支援するプログラムのことです。復職支援プログラムと呼ばれることもあり、職場復帰、また、復帰後の再発防止のために、さまざまなリハビリを受けられます。
リワークは、医療機関で受けるものや事業所で受けるものなど、さまざまな種類があるため、それぞれの特徴や利用対象者、内容について解説します。リワークを利用するメリットやデメリットも紹介しますので、利用を考えている方は、ぜひ最後まで目を通してみて下さい。
目次
リワークとは?種類や対象者、内容を解説
リワークとは、「retern to work(復職)」のことで、冒頭で触れた通り、うつ病などのメンタルヘルスの不調で休職している人の復職に向けた支援プログラムです。
リワークは、医療機関や障害者職業センターなど、実施主体によってさまざまな種類があります。種類によって、利用対象者、内容が少し異なるため、以下で詳しく解説します。
リワークの種類
リワークは、プログラムを実施する機関によって、4種類に分けられます。
- 医療機関でのリワーク(医療リワーク)
精神科や心療内科などの医療機関が実施するリワーク。病状の安定や回復、再休職の防止などを目的として、医師、看護師、臨床心理士など医療専門家のもとで、医学的リハビリテーションを実施
- 就労移行支援でのリワーク
うつ病などの精神疾患だけでなく、発達障害*や身体障害などの障害を持つ人で、一般企業などに復職・再就職したい人が利用できるリワーク。仕事をするための基礎能力や職場で役立つ実践的なスキルを習得できるプログラムを実施
- 自立訓練(生活訓練)でのリワーク
自立訓練(生活訓練)は、主に生活リズムを整えたり、ストレスの対処法について学んだりなど生活において活かせるスキルを学ぶ場。豊富なプログラムがあり、その中でKaienの自立訓練(生活訓練)では職場見学や体験などリワークとして活用できるプログラムを実施
- 障害者職業センターでのリワーク
公的機関である地域障害者職業センターが実施するリワーク。職リハリワークとも呼ばれ、精神障害のある休職者の職場復帰と復帰後のフォローのための支援を行う。休職中の本人と雇用主、主治医の3者連携で実施
- 職場リワーク
職場リワークとは、各企業が自社の休職中の社員の職場復帰を支援するために行うリワーク。企業が策定した職場復帰支援プログラムに基づいた支援や、外部サービスによる従業員支援プログラム(EAP)を実施
リワークの対象者
リワークの対象者は、基本的にメンタルヘルスの不調で休職していて、職場復帰を目指す人です。ただし、リワークの種類によって、下記のようにサービスを受けられる対象者が多少異なります。
【リワークの対象者】
- 医療機関のリワーク
うつ病や適応障害などの精神疾患により休職・離職中で復職を目指す人
- 就業移行支援や自立訓練(生活訓練)でのリワーク
精神疾患や発達障害、身体障害などの障害があり、もしくは診断がなくとも障害福祉サービス受給者証を保有している人で、休職・離職中で一般企業などへの就労・復職を希望する人。就労未経験者、退職者も利用可能
- 障害者職業センターでのリワーク
うつ病や統合失調症などのメンタルヘルスの不調により休職している民間企業の雇用保険適用事業所の方。公務員は除く
- 職場リワーク
その企業に勤務している、休職・離職中で復職を目指す人
リワークの内容
実際にリワークで受けられるプログラムの内容は、下記のようなものです。
- 生活リズムの再構築・体調管理
生活リズム表や活動記録表を作成し、それを実行することで、生活リズムを整え、体調管理法を身につける
- オフィスワーク・オフィストレーニング
復職後の業務に似た作業内容で作業訓練を行う。集中力、持続力、作業耐性などを高める
- 認知行動療法
物事のとらえ方や考え方といった「認知」に働きかけて、ストレスを軽減し気持ちを楽にする
- ソーシャルスキルトレーニング(SST)
認知行動療法の一つで、自分の意思の伝え方や他人との接し方についてトレーニングを行い、コミュニケーション能力の向上を図る
- グループワーク・レクリエーション
チームメンバーと協力しながらゲームやトレーニングを行い、対人スキルや基礎体力の向上、リフレッシュを図る
- キャリアデザイン
職場復帰に向けて自分を見つめ直し、今後どのようなキャリアを形成していくか考える
リワークにおけるプログラムの詳細については、下記記事も参考にして下さい。
関連記事:リワークプログラムとは?種類や対象者、利用の流れやメリットを解説
リワークを利用するメリット
リワークには、下記のようなメリットがあります。
- 規則正しい生活が送れる
- 専門家によるサポートが受けられる
- 復職のための基礎体力や集中力が身につく
- 自己理解を深められる
- ストレス発散方法が身につく
具体的には次の通りです。
規則正しい生活が送れる
リワークを利用すると、規則正しい生活を送れるようになり、生活リズムを取り戻しやすくなる点がメリットです。
リワークとは基本的に、通所して受けるものです。決まった時間に決まった場所に通うため、自然と規則正しい生活を送れるようになります。
休職中は、定期的に外に出ることもなくなるため、生活リズムが乱れてしまう人も多いでしょう。一度生活リズムが乱れると、自身の努力だけで生活リズムを整えることは簡単ではありません。生活リズムが乱れたままだと、集中力がもたないうえ、体調も崩しやすいなど、職場復帰が難しくなります。
その点、リワークを活用し、規則正しい生活を送ることで、生活リズムを取り戻すことができ、復職しやすくなるでしょう。
専門家によるサポートが受けられる
リワークでは、医師や看護師、心理療法士や公認心理士、職業カウンセラーなどの専門的なスタッフのサポートが受けられる点もメリットです。
職場復帰に当たって、病状などの医療的な側面はもちろん、就業面、生活面についての不安はつきないでしょう。
その点、リワークを利用すると、例えば医療機関でのリワークでは、医師や臨床心理士などの専門スタッフから、病状の安定や回復に向けた専門的なサポートを受けられます。また、障害者職業センターなどでは、障害者職業カウンセラーが適性などを踏まえた専門的なサポートを受けるのも可能です。
リワークでは医療、就労、生活において専門的な知見が豊富なスタッフからサポートを受けることができるため、効果的に復職を目指すことができるでしょう。
復職のための基礎体力や集中力が身につく
リワークでは、施設に通ったり、プログラムを受けたりすることで、基礎体力や集中力を向上できることもメリットです。
休職中は心身を休めることが第一であるものの、その反面、基礎体力が低下してしまう傾向があります。体力が低下すると、集中力の維持も難しくなるでしょう。
その点、リワークをはじめると、定期的に通所したり、トレーニングを受けたりするため、基礎体力や集中力の回復・向上を図れます。
リワークでは、個々の状況に合わせて作成されたプログラムに取り組みながら、無理なく復職に向けた体力づくりやスキルを向上させられます。基礎体力や集中力が高まると、復職への抵抗感も薄れ、復職しやすくなるでしょう。
自己理解を深められる
リワークでは、プログラムを通じて、自分自身の強みや弱点など、自己の理解を深められる点もメリットです。
リワークでは自己分析のプログラムなどを通じて、なぜ自分は体調を崩してしまったのか、どうして休職をせざるを得なかったのかなどについて振り返ります。プログラムを通して、自分がどういったことでストレスを受けやすいのか、また、自分の長所や短所、価値観などを知ることができます。
こうした自身の特性を深く知ると、仕事や日常生活において、自分の強みをどう活かし、弱みとどう向きあうかの対処法を検討できるようになるでしょう。例えば、どういった業種や職種が自分に向いているかといった点も具体的に考えられるようになります。
リワークで自分の特性を知って自己理解を深めると、職場復帰だけではなく、その後の生活もより快適になっていくでしょう。このように自己理解を深められる点は、リワークの大きなメリットといえます。
ストレス発散方法が身につく
リワークでは、ストレス発散方法を学べるのも大きなメリットです。
リワークでは、ストレスの原因を把握し適切に対処するための心理教育や、認知行動療法に基づくトレーニングといったプログラムを受けられます。これらのプログラムを通じて、ストレスをうまく発散したり、回避したりするストレス・マネジメント方法を習得することが可能です。
ストレスに対してうまく対処できないと、復職後もストレスを抱えて再び体調が悪化してしまう可能性もあります。そのため、リワークで、ストレス対処法をしっかりと学び身につけるのが大切です。
リワークでストレス発散方法を身につけると復職への不安を払しょくできるほか、働きやすくなり再休職も予防できるようになるでしょう。
リワークを利用するデメリット
リワークは職場復帰を考える人に役立つ支援サービスですが、利用する際にデメリットもあります。それは次の3点です。
- 施設によって費用が発生する
- リワークを利用する期間が長い
- グループワークでストレスを抱える可能性がある
詳しくは以下の通りです。
施設によって費用が発生する
リワークは、リワークの種類によっては費用がかかる場合がある点がデメリットといえます。
リワークの種類別にかかる費用については、下記の通りです。
- 医療機関でのリワーク:医療費が発生。原則として、保険診療の範囲内で提供されるため3割負担で利用可能
- 就労移行支援でのリワーク:利用料の1割が自己負担となる。また、世帯収入によって上限が定められており、無料で利用できる場合もある
- 障害者職業センターでのリワーク:利用は無料
- 職場でのリワーク:費用は企業負担のため、無料
障害者職業センターや職場でのリワークは基本的には無料ですが、医療機関でのリワークや、就労移行支援のリワークでは費用が発生することがあります。
リワークの費用について詳しくは、下記の記事も参考にして下さい。
関連記事:リワークプログラムとは?施設ごとの費用や特徴、利用するメリットも解説
リワークを利用する期間が長い
リワークについて、利用期間が長いのをデメリットと感じる人もいるでしょう。
リワークに要する期間は、利用するリワークの種類や個人によって差があるものの、2~6ヶ月程度はかかるといわれています。
- 医療機関のリワーク:短いものは数週間、長いものは年単位のプログラムがある。目安は3~7ヶ月程度
- 就労移行支援のリワーク:就労移行支援の利用期間は原則最長2年まで。リワークでの利用の場合は、事業所によって異なり、目安は3~7ヶ月程度
- 障害者職業センターのリワーク:標準支援期間は2~3ヶ月
- 職場のリワーク:数ヶ月程度
参考:京都障害者職業センター「よくあるご質問(リワーク(職場復帰)支援)」
早く職場に復帰したいと考えている場合などには、リワークに数ヶ月かかることに焦りを覚えることもあるでしょう。
しかし、復職後の再発を予防するためにも復帰をあせらず、じっくりと病状の回復や復職準備に取り組むのが大切です。
グループワークでストレスを抱える可能性がある
グループ形式のトレーニングでストレスを抱えてしまう可能性がある点も、リワークのデメリットの一つといえます。
リワークでは、グループでセミナーを受けたり、グループで課題にチャレンジするなど、グループワークが多くあります。グループワークは、コミュニケーション力や人間関係を構築する力を向上させるのに役立つ一方で、人によってはグループワークそのものに大きなストレスを感じる場合もあるでしょう。
グループワークや集団でのプログラムによってストレスを感じる場合は、そのままストレスを抱え込まずに、施設のカウンセラーや担当者に相談しましょう。
リワークを受けるまでの流れ
リワークを受けるまでの流れについて、リワークの代表ともいえる医療リワークのケースで解説します。
1.主治医に相談する
まずは主治医に、リワークの利用について相談します。リワークは復職を目的として利用するため、症状が安定・回復していて復職可能かどうかの判断がまず必要です。
2.利用する医療機関を決める
主治医から復職許可が出れば、主治医と相談しながら、利用するリワーク施設を決めます。医療機関をはじめとしたリワークの実施機関では、見学会や説明会を実施しているケースがほとんどです。見学会などに参加し実際に見て決めるとよいでしょう。
3.リワーク担当医の初診を受け、支援計画書を作成する
利用機関が決まれば、主治医から紹介状を取得して、利用機関の担当医の診察を受けます。初診を受けた後に、支援の実施方法と内容についての支援計画書が作成されます。
支援計画書が作成されれば、それに基づきリワークが開始されます。
他のリワークにおいても、主治医の判断を仰ぎ、利用機関を決め、面接・診断を受け支援計画書を作成するといった流れはほぼ同じです。
リワークとして利用できるKaienのサービス
Kaienでは、就労移行支援と自立訓練(生活訓練)のサービスを提供しています。それぞれについて、リワークとして活用することが可能です。
就労移行支援
就労移行支援とは、うつ病や適応障害のほか、発達障害*や身体障害などの障害を持つ人で、一般企業などへの復職・就職を目指す人が利用できる障害福祉サービスです。リワークとしても活用でき、復職や再就職に向けた基礎能力や職場で役立つ実践的なスキルを習得するのに役立ちます。
Kaienの就労移行支援では、ストレス対処法の習得や生活リズムの再構築、コミュニケーション練習など、復職に向けたトレーニングを提供しています。
Kaienの就労移行支援カリキュラムの例
- カウンセリング:モチベーション・生活リズム管理をメインとしたサポート。医療機関や所属企業と連携した支援が受けられる
- 性格検査などの各種アセスメント:自分の思考パターンだけでなく周囲との関係性での生きづらさも可視化できる
- 障害学・ソーシャルスキル:コミュニケーション、心と体の管理、障害について深く学べる
- キャリア・プランニング:自分の職業人生をデザインできる
- 実践型の職業訓練:軽作業を体験しながら適した職種と環境を探せる
2025年4月からは、YouTuberでもある精神科医の益田裕介先生監修のもと、新しい復職支援「リワークセンター」も開設します。
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある人が自立した生活を送れるように、さまざまな生活上のスキルの維持・向上に向けた訓練を行う障害福祉サービスです。就労移行支援が就職・復職を目指すのに対し、自立訓練(生活訓練)では、生活上の自立を目指します。
Kaienの自立訓練(生活訓練)では、コミュニケーション力を高める方法や、感情をコントロールする方法など生活の基礎力を高めるさまざまな講習・訓練が受けられます。
Kaienの自立訓練(生活訓練)で学べるスキルの例
- 食生活や生活リズム、セルフケア方法など
- 金銭管理、身だしなみの整え方など
- 人間関係の構築、コミュニケーション方法など
- 社会保障制度、障害福祉制度など自分の権利の活かし方
リワークの利用を検討している方はKaienにご相談ください
リワークとは、メンタルヘルスの不調で休職している人が復職するための支援制度です。医療機関、就労移行支援、障害者職業センター、職場など実施主体によって4種類のリワークがあるため、自分にあったものを選ぶようにしましょう。
自分にあったリワーク先がわからない、あるいは復職や再就職に悩んでいる場合には、Kaienにお気軽にご相談ください。
Kaienでは、リワークとして利用できる就労移行支援、自立訓練(生活訓練)を提供しています。2025年4月からは、精神科医の益田裕介先生監修のもと新しい復職支援「リワークセンター」も開設しています。
就労移行支援、自立訓練(生活訓練)について豊富な経験と実績に基づいたサポートが可能です。ご相談やご見学は、オンラインでも事務所でも、ご家族だけでもご参加いただけます。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。

監修 : 鈴木 慶太(株式会社Kaien 代表取締役)
元NHKアナウンサー。自身の長男が発達障害の診断を受けたことをきっかけに、米国留学(MBA取得)を経て株式会社Kaienを設立。 「数的な凸凹があっても、強みを活かして働ける社会」を目指し、大人向けの就労支援から子ども向けの学習支援(TEENS)まで幅広く事業を展開している。 経営者として、また一人の親としての視点を交えた発信は、多くの当事者・家族から支持を得ている。
▼ 代表・鈴木に直接質問できるライブ配信も開催中。毎週開催の「Kaienお悩み解決ルーム」ほか、就職や生活に役立つ情報を配信しています。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189