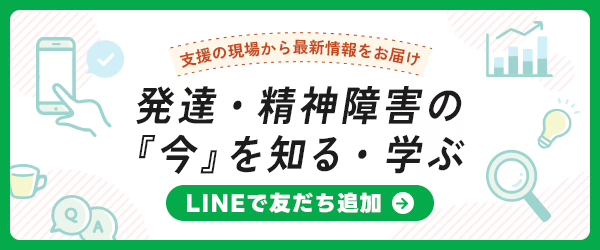突然前触れもなく、激しい不安に襲われるパニック障害。発作が起きてしまうと、「再び発作が起きるのではないか」とさらに不安が強まってしまい、就労が困難になるケースも少なくありません。もしパニック障害により、こうした就労に関する悩みを抱えているならば、おすすめしたいのが支援サービスの活用です。
本記事では、パニック障害の方が働くうえでできる工夫や向いている仕事、仕事を探す時に意識したいポイントなどについて、詳しく解説します。パニック障害の方が活用できる支援サービスも紹介しているので、パニック障害でも仕事を続けたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
パニック障害(パニック症)とは?仕事にどう影響する?

パニック障害とは、前触れもなく動悸やめまい、呼吸困難といったパニック発作が起きてしまう病気で、発作をくり返すことで日常生活を制限されてしまうこともあります。
パニック障害は、100人に1人がなると言われている不安障害の1つです。パニック障害になる原因は明らかになってはいませんが、ストレスや脳内の伝達物質が関係していると考えられています。早期の対処が重要で、早めに適切な治療が行えれば回復に向かうケースが多いのも特徴です。
パニック障害はその性質上、仕事にも大きな影響をおよぼします。仕事中に症状が出ると、落ち着くまで業務を中断しなければなりません。作業効率が悪くなるほか、周囲に迷惑をかけてしまうことへの心理的負担や、また症状があらわれることへの不安など、あらゆる面で仕事に支障が出てしまいます。
パニック障害の主な症状と特徴
パニック障害の代表的な症状の1つが「パニック発作」です。パニック発作は、突然めまいや動悸などの症状が現れ、電車に乗ったときや会議に参加したときなどに何度もくり返されます。時には発作により、「このまま死んでしまうのではないか」と大きな恐怖を覚えることも少なくありません。これらの症状は多くの場合、発作が起きてから10分以内にピークに達し、20分以内におさまる傾向にあります。
こうした発作をくり返すと、「また発作が起きるかもしれない」という不安にかられ、パニック発作が起こらなくても「予期不安」が付きまといます。この予期不安が強くなると、発作を起こした場所や、その状況を極度に避けるようになり、外出自体が困難になったり、仕事や日常生活にも影響が強く出てしまいます。また、そのような不安が、発作に関係の無い場所にまで拡大し、「広場恐怖」を発症し、多様な状況に不安が強くなることもあります。こうなると外出自体が難しくなってしまい、仕事や日常生活に影響が出てしまうようになるでしょう。
パニック発作が仕事に及ぼす影響
パニック障害はパニック発作がつらいのはもちろんですが、予期不安の進展や、広場恐怖の発症により仕事が困難になるケースが少なくありません。パニック発作による恐怖や、密閉空間による不安などから、発作が起きた場所(通勤電車やエレベーターなど)に行くことができず、通勤が困難になる可能性があります。
また会議の参加など、強い緊張を感じる場面でもパニック発作は起こりやすくなります。特にプレゼンなどでミスをした経験がある方は、失敗したときのことがフラッシュバックして強い不安や恐怖に支配されてしまうケースが多いです。仕事中にパニック発作が起きてしまうと業務を続けるのは困難になるため、仕事を一時中断して発作が落ち着くまで休まなければなりません。
パニック障害と発達障害との関連性
治療をしてもパニック障害の症状がどうしても改善しないときに、根底に発達障害特性のある方が抱える不安が関係してることもあります。発達障害*は先天的に脳機能の発達に偏りが生じる障害で、自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如多動症(ADHD)などが挙げられます。
発達障害の特性により多様な不安を抱えて生活することで、パニック障害などの後天的な精神障害が引き起こされるケースがあります。これを二次障害と呼び、症状の改善にはパニック障害のほかに大元となっている発達障害へのアプローチも必要です。
ただし覚えておきたいのは、発達障害はうまれつきの特性であるのに対し、パニック障害は後天的に発症したものであり、適切な治療により改善が見込まれるということです。そのため、正確な診断と治療が早期改善のカギとなります。
パニック障害があっても仕事は続けられる?
パニック障害があると、「仕事を続けられるか」不安に思う方も多いと思います。しかし無理をして仕事を続けるのは、パニック発作などの症状が悪化したり、再発をくり返したりする恐れがあるためおすすめできません。まずは医療機関を受診し、適切な治療や休養をとることが大切です
パニック障害の改善を目指すなら、休職や転職も選択肢の1つです。しっかりと休んで仕事のことを考えられるようになったら、通勤時間や通勤場所を検討する、自分に合った仕事を探すといったアクションをとるようにしましょう。
パニック発作が起きた時の対処法と予防策
パニック発作は、適切な対処法を押さえておけば症状を軽減できる可能性があります。また、発作を未然に防ぐための予防法を実践することで、予期不安も和らげられるでしょう。
ここからは、パニック発作が起きたときの対処法と、発作を未然に防ぐための工夫について解説します。
発作時にできる対処法
パニック発作は突然起こるため対処が難しいのですが、事前に対処法を身につけておくとスムーズに対応できることもあります。まずは、自分なりのリラックス方法を見つけてみてください。
例えば、意識的に深呼吸をする・その場から離れる・「発作では死なない」と頭で考える・あらかじめ落ち着ける場所を見つけておく、といった方法があります。
不安や緊張を感じたら、これらの方法を思い出して試してみましょう。事前に対策を準備しておくことで、発作が起きたとき、起こりそうなときでも冷静に対処できるようになります。
発作を未然に防ぐ工夫
パニック発作は緊張や不安を感じているときに起こりやすいため、心身をリラックスさせることが予防につながります。手軽にできるリラックス方法は以下のとおりです。
- 休憩時間に音楽を聴く
- 深呼吸をする
- ストレス要因を紙に書き出す
- 好きなアロマの香りをかぐ
その他、以下のようなストレス対処法も効果的です。
- 休日にキャンプなど自然に触れる
- ランニングなどの適度な運動をする
- お風呂にゆっくり浸かる
- 寝る前はスマホに触らず、本を読んで過ごす
パニック障害と向き合いながら働く工夫

パニック障害の影響をなるべく抑えて仕事を続けるためには、まずパニック障害を受け入れることが大切です。症状から目をそらさず、真摯に向き合うことで効果的な対策方法も見えてくるでしょう。
ここでは、パニック障害と向き合いながら働くうえで役立つポイントを5つ紹介します。
通勤ラッシュを避ける
パニック障害を抱えていると、電車やエレベーターなどの閉鎖空間や人混みに不安を感じやすくなります。このような状況を避けるため、人が少ない時間に通勤時間帯をずらしてみるのがおすすめです。
出勤・退勤の時間を調整できないか、職場に相談してみてください。現在仕事探しをしている方は、時差出勤や時短勤務ができる職場を選ぶとよいでしょう。
出勤や退勤の時間を調整するのが難しい職場の場合は、「通勤経路を変えたり各駅停車の電車に乗ったりして人混みを避けている」「ラッシュの時間帯を避けて1時間早い電車に乗り、職場の近くで朝食を食べている」という人もいます。
生活リズムを安定させる
パニック障害を抱えながら働くには、生活リズムを安定させることが大切です。生活リズムが乱れるとストレスや不安を感じやすくなるため、睡眠時間や食生活が乱れていると感じる人は注意してください。
毎日の起きる時間と寝る時間を決めたり、3食しっかり食べたりして、生活リズムを整えるよう意識しましょう。適度な運動や、朝起きて太陽の光を浴びるのもおすすめです。眠りにつきやすくするために、寝る前のカフェインやアルコールは控えるようにしましょう。
最初からすべてを完璧にこなす必要はないので、取り組みやすいところから始めて、少しずつ自分のペースで生活リズムを整えていってください。
職場環境を調整する
少しでも安心して働けるように、パニック障害について職場に可能な範囲で伝えておきましょう。
例えば、どんなときにパニック発作が起こりやすいのか事前に伝えておくと、仕事上で発作が起きやすい状況を回避できます。また、発作が起きたときにどのように対応してほしいかを伝えておけば、発作が起きても周囲の人に冷静に対応してもらえるでしょう。
自分一人で職場と対話するのが難しい場合は、医師やカウンセラー、障害者支援の窓口などに相談するのもおすすめです。専門家のサポートを受けながら職場環境を調整することで、より安心して働くことができます。
在宅ワークや柔軟な勤務形態を活用する
パニック障害のある方は、仕事でストレスをため込まないようにすることが重要です。特に、責任感が強くまじめな人が発症しやすいため、柔軟な考え方や働き方を身につける必要があります。
在宅ワークが可能な職場なら、無理をせず在宅ワークに切り替えてストレスや疲労を軽減させるのがおすすめです。体調が悪化したり、不安が強まったりしているときは、上司などに相談して柔軟な働き方を許可してもらうのがよいでしょう。
合理的配慮を求める
合理的配慮とは、障害のある方が働きやすくなるように、事業者が提供する配慮事項のことです。合理的配慮を提供することは、すべての事業者に義務付けられています。
パニック障害で仕事に支障をきたしている方は、職場で合理的配慮を求めるとよいでしょう。上司や人事担当者に相談すれば、可能な範囲で適切な対処をしてくれるはずです。
合理的配慮の具体例としては以下が挙げられます。
- 本人の状況に応じて業務の量を調整する
- 通勤ラッシュを避けるために時間差での通勤を認める
- 不安を感じたときに休めるよう、適宜休憩をとる
- 強いストレスを感じる会議への参加を強制しない
パニック障害の方に向いている仕事とは?

パニック発作がある方は、発作が起きづらい環境に身をおくことが大切です。例えば電車通勤の必要ない在宅ワークが可能な仕事や、対人的なストレスや業務への重圧が少ない事務職などの定型職が、おすすめの仕事として挙げられます。ほかにも、人前に出ることで緊張や不安が強くなる方は、エンジニアやIT関連など自分のペースで行える仕事が適しています。
ただし、パニック障害の程度や状態などは人によりさまざまです。あくまでこれらは目安にすぎないため、自分に合った働き方や職種を見極めるようにしましょう。今の仕事を続けたい場合は通勤時間帯を変える、上司に相談して配置換えをお願いするなど、職場環境を整えることが先決です。
パニック障害の方の仕事探し・就職活動のポイント

パニック障害の方が仕事を探すときは、不安や緊張を感じにくい職場選びがポイントです。また、障害者雇用なども検討することで、働きやすい環境が見つかる可能性が高まるでしょう。
以下で、パニック障害の方が就職活動をする際のポイントを3つ紹介します。
不安や緊張を感じにくい職場を選ぶ
パニック障害の方は、不安や緊張を感じにくい職場を選ぶことが大切です。まず、自分がどんな職場なら長く続けられそうかを考えてみましょう。
例えば、電車や飛行機で発作が起こりやすい人は、電車を使わずに通勤できる職場や出張のない職種が向いているでしょう。通勤時間を調整しやすいフレックスタイム制や、短時間勤務が認められている企業もおすすめです。
このように自分に合った職場を見つけることが、パニック障害を抱えながら働く方にとっては非常に重要になります。
パニック障害への理解がある職場を選ぶ
パニック障害の方の仕事探しでは、障害に対して理解のある職場を選ぶことも大切です。こうした職場では、本人の特性や困りごとに合わせて通勤時間や業務内容を配慮してもらえる可能性があります。パニック障害であることを伝えやすく、困ったことがあっても相談しやすいのもメリットです。
働きやすい環境づくりには、自分でできる対処法だけでなく職場の協力も必要です。障害に理解がある職場なら、さまざまな協力が得られるでしょう。また、職場の同僚や上司に自分の状況を理解してもらうことでストレスが軽減され、安定して長く働ける可能性が高いです。
障害者雇用も検討する
パニック障害を抱えている方は、障害者雇用の利用も検討してみてください。障害者雇用とは、企業に対して一定割合以上の障害者を雇用するよう定めた制度です。障害を持つ方の採用を前提としているため、理解や配慮を受けやすい環境が整っています。事前にパニック障害の症状について伝えておけるので、働きやすい職場環境を整えてもらえるでしょう。
障害者雇用を利用するには、障害者手帳が必要です。障害者手帳をまだ取得していない方は、自治体の窓口で申請を行いましょう。
自分に合う仕事探しは就労移行支援などの活用がおすすめ

パニック障害がある方が仕事を続けるためには、発作が起こりづらい職場環境で働けるかどうかが重要になります。しかし、症状が出ている間に1人で仕事を探すのは難しいかもしれません。さらに転職や再就職などで就活をするとなると、採用面接など緊張する場面に何度も直面することになり、不安も強くなってしまうことでしょう。
パニック障害がある方が仕事を探す際は、支援サービスの活用がおすすめです。例えば就労移行支援は、事業所により特色が異なりますが、働くうえでの困りごとに対するスキルを学べたり、自分に合った仕事を探すための職業訓練が受けられたりと、障害に理解があるため相談しやすい環境が魅力です。サービス利用は通所型で、利用期間は原則2年間と定められています。個々の状況に合わせて、通所期間内に個別に立てられた支援計画のもと、一人ひとりにあった手厚いサポートが受けられるのも特徴です。
また、就職の前段階として自分を見つめ直したり、生活の基盤を整えたりしたい方は、自立訓練(生活訓練)の利用がおすすめです。自立訓練(生活訓練)では、障害のある方が自立した生活を送れるように、日常生活や社会生活に関するプログラムを提供しています。働き始める前に自分自身を見つめ直したいと感じている方は、自立訓練(生活訓練)の利用も検討してみてください。
パニック障害があっても「自分らしく働く」方法を見つけよう
パニック障害の方は、発作と上手く付き合いながら無理なく働ける環境に身をおくことが大切です。人により向き不向きは異なりますが、在宅ワークや対人ストレスが少ない職種など、ストレスの少ない仕事を選びましょう。
症状が落ち着いて復職や転職を希望する際には、就労移行支援サービスの利用がおすすめです。Kaienではパニック障害の方のために、職業訓練や障害に理解のある企業の独自求人を紹介するなど、手厚い就労サポートを行っています。興味がある方は、無料で説明会や見学会も随時開催していますので、ぜひお気軽にお越しください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修者コメント
パニック症は、症状が突然始まることで、それまでそんなことが無かった方にとって非常に衝撃的な疾患だと感じられます。一番の問題は、その症状の強烈さによって、行動範囲が狭まってしまうことです。それによって本来ならできることができなくなってしまう、自分の能力を発揮できる場所に移動できなくなってしまうことが非常に辛いところです。とはいえ、治療が非常に効果的な疾患でもあります。パニック症の克服は認知行動療法が最も得意としていますし、薬物療法も上手く利用することで生活上の不安を大きく下げることが可能です。悲観せず、まずは治療により症状を軽減していくことを目指してみてください。そしてそのための環境作りとしては、周囲の理解を得て一定の配慮を受けたり、状況によっては治療のための休養を選択してください。本記事にあるような生活上の工夫も効果的です。パニック症は確かに辛い症状を呈しますが、多くの著名人が自分もそうだと声を上げてくれたこともあり、周囲の方を理解しやすい疾患でもあります。治療への取り組みや周囲の理解を得ることを、是非勇気を持って始めてみてください。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189