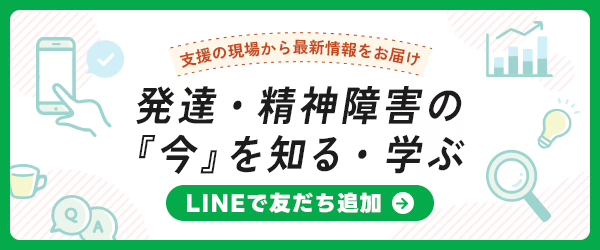本人の意識と関係なく咳払いやまばたきをくり返してしまうチック症の多くは、小児期から青年期にかけて発現する一時的な症状ですが、中には大人になってからも症状が続いたり、悪化したりする場合もあります。また、チック症の原因はまだはっきりと解明されていませんが、脳機能の障害が関与していると考えられており、日本では神経発達症(発達障害*)に分類されています。
この記事ではチック症の主な症状と対処法、トゥレット症との違いや活用できる支援機関について解説します。
目次
大人のチック症とは
チック症とは、多くの場合は自分の意志とは関係なく体の一部分がいきなり動いたり、無意識に声やせき払いが出たりすることを繰り返してしまう状態です。小児期(4歳位から)に発症することが多いですが、一般的にチック症は一過性であり、大人になるにつれて自然に治まると言われています。
ただし、大人になってからもチック症の症状に悩む方がいるのも事実です。大人のチック症には、子ども時代に発症した症状が軽くはなっているものの継続しているケースや、一度は治まっていた症状が再発するケースがあります。
チック症が1年以上続くとトゥレット症に
チック症は、まばたきや首振りといった運動チックや、せき払いや奇声などの音声チックが一時的に現れます。一方で、トゥレット症は、複数の運動チックと1つ以上の音声チックが1年以上続いている場合に診断されます。またトゥレット症は18歳未満で発症し、10代半ばでピークを迎えるケースが多いです。
チック症からトゥレット症に至る流れは、以下のとおりです。
- 暫定的(一過性)チック症: チックの発症から1年未満
- 持続性(慢性)運動チック症: 運動チックのみを発症し、運動チックが1年以上持続
- 持続性(慢性)音声チック症: 音声チックのみを発症し、音声チックが1年以上持続
- トゥレット症: 運動チックと音声チックの両方を発症し、1年以上持続(チックが出ていない時期も含む)
このように、チックの種類と持続期間によって診断名が異なります。
チック症の主な症状
チック症の主な症状は、大きく分けると次の2つです。
- 音声チック
- 運動チック
また、音声チックと運動チックは、症状が続く長さなどによって、さらに単純チックと複雑チックに分類されます。単純チックは突然の発声・動作など持続時間が短く無意味なもの、複雑チックはややゆっくりとした発声や発語・動作など持続時間が長めで意味があるように見えるものを指します。それぞれの症状について以下で詳しく見ていきましょう。
音声チック
音声チックは、無意識に単純な音声や言葉をくり返し発してしまうのが特徴です。単純音声チックには主に次の症状が見られます。
- せき払い
- 「アッ」「エッ」「ンッ」などの声を出す
- うなる
- 鼻をすする、鳴らす
- 鼻歌のような声を出す
一方、複雑音声チックに見られる主な症状は次の通りです。
- 状況にふさわしくない声を出す
- 不適切な言葉や不謹慎な言葉、暴言などを発する(汚言症・コプロラリア)
- 人の言葉を繰り返す(反響言語・エコラリア)
- 特定の単語を繰り返す(反復言語)
運動チック
運動チックとは、自分の意志とは無関係に顔や手足など体の一部をくり返し動かしてしまう状態です。単純運動チックには主に次の症状が見られます。
- まばたきする
- 顔をしかめる
- 首を振る
- 肩をすくめる
- 口を曲げる
- 鼻を動かす
- 手足を伸ばす
それに対し、複雑運動チックに見られる主な症状は次の通りです。
- 白目をむくなど表情を変える
- 床や地面を激しく踏み鳴らす
- 自分の体をたたく
- 飛び跳ねる
- 他人を触る
- 匂いをかぐ
- 他人の運動を真似る(同響動作)
- 不適切な動作をする(汚行症・コプロプラキシア)
チック症の原因
チック症は以前は保護者の育て方や本人の性格、心の問題などが原因だと言われていました。しかし現在では、脳内の神経伝達物質の働きのかたよりや神経回路の異常などによって、運動を制御する脳機能がうまく働かないことがチック症の原因とする考え方が一般的です。
また、チック症はさまざまな要因によって悪化するとされています。主なチックトリガー(要因)は生活環境やストレス、心理的要因、その他の疾患などです。
チック症と併存しやすい病気や発達特性
チック症は、精神疾患や発達特性が併存しやすい傾向があります。ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)といった発達特性は、チック症よりも前から出現している場合が多く、チックの悪化に影響を与える可能性もあります。
またチック症は強迫性障害や不安症、うつ病なども併存しやすいです。これらの症状はチックの出現と前後して現れたり、チックの慢性化にともなって悪化したりするケースが見られます。
強迫症
チック症は、強迫症を併発するケースが少なくありません。強迫症は、特定の考え(強迫観念)が繰り返し頭に浮かんだり、特定の行動(強迫行為)を繰り返さずにはいられなくなったりする精神疾患です。例えば、「手が汚れている」という強迫観念から何度も手洗いを繰り返すといった症状が見られるでしょう。
チック症と強迫症が併発すると、「チックをせずにはいられない」といった衝動に駆られ、「まさにぴったり」と感じるまでチックを続ける傾向にあります。特にトゥレット症は約30%の患者さまが強迫症を併発しており、診断基準を満たさない強迫症状を含めると、併発率は50%以上と報告されています。
強迫症は、強迫観念と強迫行為のどちらか一方、あるいは両方が出現する可能性があり、症状は人によってさまざまです。もしチック症と同時に強迫症のような症状に悩まされているのであれば、専門医に相談し、適切な診断と治療を受けるのをおすすめします。
注意欠如多動症
チック症は、注意欠如多動症を併発するケースもあります。実際に、持続性チック症のある児童の約半数に注意欠如多動症が併存しているという報告もされています。
注意欠如多動症とは、不注意、多動性、衝動性を主な特徴とする発達障害の一つです。不注意は、集中力の持続が難しく、忘れ物やなくし物が多いといった症状が特徴です。多動性は、落ち着きがなくつねに動き回る傾向があります。衝動性は、ルールや約束を守れず、つい口を挟んでしまうなどの行動が見られる場合があります。
チック症と注意欠如多動症が併存する場合、それぞれの症状が互いに影響し合う可能性もあるでしょう。例えば、注意欠如多動症による不注意や多動性がチックを悪化させたり、逆にチックが注意欠如多動症の症状をさらに目立たせる場合もあるでしょう。
チック症と注意欠如多動症の併発は、どちらかの特性のみをとらえるのではなく、包括的な視点から理解し、適切な支援へとつなげる必要があります。
自閉スペクトラム症(ASD)
チック症は、自閉スペクトラム症(ASD)と併存する可能性も指摘されています。自閉スペクトラム症(ASD)は、対人関係・社会的コミュニケーションの難しさや、限定された興味・行動、感覚過敏などを特徴とする発達障害の一つです。
自閉スペクトラム症(ASD)の感覚過敏やこだわりといった特性が、チック症状の発現や悪化に影響を与える可能性もあるでしょう。例えば、特定の感覚刺激(音・光・触覚・味覚・匂いなど)に敏感な場合、その刺激がチック症状を誘発したり、チックの回数を増やしたりするケースがあります。特定の行動パターンを反復するなかで、チック症状が現れる場合もあります。
自閉スペクトラム症(ASD)とチック症が併存する場合、それぞれの特性が複雑に絡み合い、日常生活での困りごとが増えるかもしれません。両方の特性を理解し、それぞれに合った適切な支援や対処法を検討しましょう。医療機関では、自閉スペクトラム症(ASD)とチック症の診断を行い、各症状に合わせた治療や支援が受けられます。
限局性学習症/学習障害(SLD/LD)
チック症の方のなかには、限局性学習症/学習障害(SLD/LD)を併存している方もいます。限局性学習症/学習障害(SLD/LD)は、全般的な知的発達に遅れはないものの、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった特定の能力の習得・使用に著しい困難を抱える発達障害の一つです。
チック症と併存していると、チック症状と学習面での困難が同時に現れる場合があります。また、先述した注意欠如多動症は、限局性学習症を併発しているケースも多いとされています。チック症状に加えて、注意欠如多動症の集中力の低下や多動性が学習に影響を与える可能性も考えられるでしょう。
チック症と限局性学習症はそれぞれ異なる特性を持つ障害ですが、互いに影響し合う場合もあるため、両方の視点からサポートが必要です。早い段階で特性を理解し、一人ひとりに合わせた学習支援や環境調整を行えば、学業面での影響を抑え、社会生活への適応につながるでしょう。
併存・併発する可能性があるその他の病気や特性
チック症は、以下のような病気や特性が併存・併発する可能性があります。
- うつ病: チック症による自己肯定感の低下が影響し、気分の落ち込みや興味の喪失、食欲不振、倦怠感などのうつ症状が見られる場合もある
- 怒り発作: チック症の不快感やストレスから、突発的な強い怒りやイライラが制御できないケースもある
- 不安症: チック症状が出る不安や恐怖心から、不安症を併発する場合がある
- パニック症(パニック障害): チック症による精神的な負担が、動悸や息苦しさ、めまいなどのパニック発作の引き金となる可能性がある
これらの併存症は、チック症の治療と並行して、症状に合わせた適切な治療を受けましょう。
大人のチック症で抱えやすい困りごと
大人のチック症は、日常生活のさまざまな場面で困難を引き起こす場合があります。公共の場での視線、職場での誤解など、周囲の理解が得られない状況では社会生活を送るうえで精神的な負担を感じるかもしれません。しかし症状を無理に抑え込もうとすると、かえってストレスが増えて、症状が悪化する可能性もあります。
この章では、大人のチック症の方が直面しやすい困りごとや、具体的な対処法ついて、詳しく解説します。
音声チックによって周りの視線が気になる
音声チックは日常生活において大きな悩みの種となりがちです。突然大きな声を出してしまったり咳払いや舌打ちが止まらなくなったりすると、周囲の視線が気になり不安を感じる方も少なくありません。
例えば、通勤中の電車内や静まり返ったオフィス、図書館のような場所では「周囲に迷惑をかけていないか」「変に思われていないか」といった不安を抱えるかもしれません。また、会議中に突然声が出てしまったり、面接や商談などの大事な場面で乱暴な言葉が出てしまったりして、相手に誤解を与えるおそれもあります。
このような状況が頻繁に起こると、外出自体に抵抗を感じるようになったり、人との交流を避けるようになったりする方もいます。周囲の反応を過度に気にしてしまい、社会生活にも影響を及ぼす可能性も考えられるでしょう。
運動チックにより誤解を招きやすい
運動チックは、本人の意図しない体の動きとして現れるため、周囲から誤解を招きやすい症状といえます。頻繁なまばたきや顔のしかめ、首振り、身体の揺れなどは、周囲からは「落ち着きがない」「緊張しているのではないか」といった印象を与えてしまうかもしれません。
特に職場のようなフォーマルな場では、運動チックが不適切に受け取られがちです。例えば、会議中に何度もまばたきをしたり、プレゼンテーション中に首を振ってしまったりすると、「話に集中していない」「真剣に取り組んでいない」と誤解されかねません。仕事の評価に悪影響が及んだり、周囲からの信頼を損ねたりするケースもあります。
当事者にとっては、努力しているにもかかわらず正しく評価されないといった状況は、大きなストレス要因となり心身ともに負担が増えるでしょう。
無理にチックを抑えようとしてストレスが悪化する
音声チックや運動チックの症状に対して、「周りに変に思われたくない」「怒られたくない」といった思いから、必死に症状を抑えようとすると、かえって逆効果になる場合があります。無理にチックを我慢しようとすると、緊張や不安が高まり、反動でチックがより強く出てしまうといった悪循環に陥るケースも少なくありません。
また、どうしてもチックを抑えなければならない状況で我慢し続けた結果、解放された瞬間に症状が激しくなるといったケースも報告されています。このような状況が続くと、心身への負担が増えて疲労感が蓄積したり、不眠などの身体症状を引き起こしたりする場合もあります。
さらに、強いストレスはうつ病や不安障害など、ほかの精神疾患を併発する原因となる可能性もあります。チックを無理に抑えようとするのは避けましょう。
大人のチック症の対処法
大人のチック症に関する主な対処法としては、次のようなものが挙げられます。
- 職場などに相談して理解と配慮を求める
- 落ち着ける時間や環境を確保する
- 支援機関を活用する
それぞれの対処法について、以下で詳しく見ていきましょう。
職場などに相談して理解と配慮を求める
チック症について知識のない人も多いため、まずは職場の上司などに相談し、チック症について理解してもらうことから始めてみましょう。また、一緒に働く同僚に対しても、本人の意志と無関係に声や言葉、動作が出てしまうことや、どのような症状が出るのかなどについて事前に説明しておくことが大切です。そうすれば、職場でチック症の症状が出てしまう場合でも理解してもらいやすく、必要な配慮や支援もお願いしやすくなるでしょう。
落ち着ける時間や環境を確保する
仕事中はさまざまなストレスや不安にさらされることもあるかもしれません。そのような精神的に余裕のない状態が、チック症の症状を悪化させる可能性もあります。症状が進行して苦痛を感じる場合は、1人になって落ち着ける時間や環境を社内や職場の近くなど、仕事中に行ける範囲であらかじめ確保しておくようにしましょう。仕事中にうまく一息つくことによって、チック症の症状を緩和できる場合があります。
医療機関の受診・支援サービスを活用する
チック症が日常生活に支障をきたしている場合、医療機関を受診してみましょう。チック症の治療法として、チックの予兆となる感覚を認識し、別の行動に置き換える「ハビットリハーサル」や、チックを軽減するために統合失調症の薬が用いられる場合があります。
また、支援サービスや自助会・当事者会を活用するのもおすすめです。自助会・当事者会に参加し、同じ悩みを抱える人たちで集まって情報や経験を共有すると、精神的な支えを得られるでしょう。
Kaienでは、一般企業への就職を目指す発達障害の方に特化した就労移行支援を行っています。職場訓練では、100職種以上の実践的なカリキュラムを受講可能です。さらに、特性理解を深めるためのライフスキル講座やスキルアップ講座、就活講座も50講座以上実施しています。
発達障害に理解のある200社以上の企業との連携による独自求人の紹介や、担当カウンセラーによる手厚い就活サポートもKaienの強みです。
大人のチック症は症状や環境に合わせた対応を
大人のチック症は、自分の意思とは関係なく生じる声や動作の症状により、日常生活や社会生活に支障をきたす場合があります。ストレスや環境によって悪化するケースもあるため、ご自身の症状や特性を理解し、適切な治療や対処法を見つけましょう。例えば、自分の特性に合う環境を求めて転職する方法もあります。
Kaienでは、精神的な不調で仕事を離れた方をサポートするリワーク(復職・再就職支援)プログラムを提供しています。リワークプログラムでは、症状との向き合い方やストレス対処法を学びながら、ご自身に合った働き方をじっくりと見つけられます。専門機関の支援を活用しながら、チック症とうまく付き合っていきましょう。
*1 発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
チック症は男の子に多く見られるもので、小学校高学年で症状のピークを迎えますが、大半はその後自然に改善します。しかし、経過の中で成人になっても継続する方がいらっしゃいます。仕事などの心理的なストレスが重なって、症状が続いたり悪化したりする場合もあります。
このため、チック症の治療では心理的ストレスを低減することが肝心ですが、十分な改善が見られない場合は保険適用外ではあるものの、患者さんから同意を得て抗精神病薬を用いることがあります。また、チックが出そうな時に敢えて反対の行動を取る(右手がぐっと上がりそうなときに全身の力を抜く)というハビットリバーサルが有効な場合もあります(国立精神・神経医療研究センターHPより*1)。
トゥレット症候群は、医療関係者でないとご存知ない用語かもしれません。しかし、アメリカのインディーズ映画 ”(500) Days of Summer” で主人公の女の子(サマー)がロサンゼルスの公園でのデートでわざと卑猥な言葉を叫んで、ボーイフレンドの男の子(トム)が周りに「すみません!彼女はトゥレットなんです」と言っていたので*2、アメリカでは知名度があるかもしれません。何も医学的な解説になっていませんが、トリビアとしてお伝えしました。
*1https://www.ncnp.go.jp/hospital/patient/disease16.html
2*https://jp.pinterest.com/pin/500-days-of-summer-movie-poster–858709853941631510/

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189