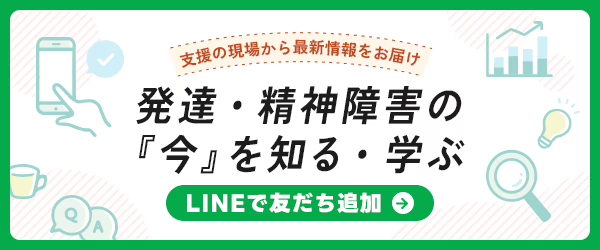境界知能の方は、日常生活や就労の場で困難を感じやすい傾向があります。しかし、医学的な診断名がないことから、必要な支援を受けられないケースも珍しくありません。自分が境界知能ではないかと感じている方は、検査方法や支援先などの情報を知り、活用することをおすすめします。
本記事では、境界知能の概要や知的障害との違い、よくある困りごとなどについて解説します。境界知能の方が利用できる相談・支援先も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
境界知能とは
境界知能とは、一般的におおむねIQ70〜84の方で、知的障害の診断が出ていない場合に用いられる言葉です。知的障害者として認められるのは通常IQ70未満であり、境界知能はそのレベルよりは高いものの、平均的なIQレベルは下回る層を指します。
境界知能に該当するIQ70〜84の方は、日本全国で約14%、人数にして約1700万人いるといわれています。この数字からも、境界知能で悩んでいる方が決して少なくないことがわかるでしょう。
境界知能があると、日常生活や就労現場でさまざまな困難を感じやすい傾向があります。しかし、境界知能という正式な診断名はなく、公的支援の対象外であるため、必要な支援や配慮を受けることが難しいケースも少なくありません。
IQ(知能指数)を測る知能検査の種類
そもそも知的指数(IQ)とは、知能水準あるいは発達の程度を測定した検査数値の1つです。知能検査などの検査で示される指標であり、IQレベルは「生活年齢(何歳相当の発達か) ÷ 暦年齢 × 100」で計算されます。
知能検査は、個人の理解や知識、課題解決などの認知能力を測定するための心理検査です。IQの数値は、知能検査の基本的な指標とされることが多いです。
知能検査にはいくつかの種類がありますが、日本ではウェクスラー式知能検査がよく使われています。ウェクスラー式知能検査には80年以上の歴史があり、専門家と受検者が1対1となる状況で実施されます。受検者の年齢に応じて、幼児用のWPPSI、児童版のWISC、青年・成人用のWAISの3種類に分けられます。
大人の知能検査の中でもよく用いられるのが、「WAIS(ウェイス)」の第4版である「WAIS-Ⅳ」です。
WAIS-Ⅳでは、「言語理解」「知覚推理」「ワーキングメモリー」「処理速度」という主な4つの指標と、それらを合わせた総合的な指標(全検査IQ)を通して、個人の全般的なIQや能力のばらつきを評価します。
関連記事:知能検査とは? 大人の知能検査 WAIS-Ⅳ を読み解く
境界知能と知的障害の違い
知的障害とは、実用的な場面における知的機能と適応機能の両面での欠陥を含む障害のことです。厚生労働省やアメリカ精神医学会の定義では、知的障害は「軽度」「中度」「重度」「最重度」の4グループに分けられます。軽度知的障害は4つのうち、症状や程度が最も軽いグループを指します。
軽度知的障害と境界知能は、IQの基準が異なります。境界知能はIQ70〜84に該当するのに対し、軽度知的障害はIQ51〜70相当という位置付けです。
IQを指標とした知的障害の診断は、以下の通りです。
- IQ70〜84:境界知能
- IQ50〜70:軽度知的障害
- IQ35〜50:中等度知的障害
- IQ35以下:重度知的障害
上記に加えて、おおよそIQ20以下を最重度知的障害とする分類もあります。
IQは、おおまかな知能の判断基準に加え、知的障害などの診断や支援にも利用されますが、「IQが高いから困りごとが少ない」などとは一概に言えません。実際に、知的障害は知能指数だけでなく、社会的な領域と実用的な領域も踏まえて判断されます。
境界知能であっても困難が少ないこともあれば、正常域以上でも困難が目立つケースもあります。そのため、単にIQの数値から診断するのではなく、本人が抱える悩みや困りごとの程度などを総合的に踏まえた上で、フレキシブルに判断することが求められます。
関連記事:軽度知的障害とは?働き方や仕事での困りごと、就労の相談先を解説
境界知能と発達障害のグレーゾーンとの違い
グレーゾーンとは、発達障害*¹の特性や症状があるものの、度合いが薄いために診断基準をすべて満たしていないケースを指します。また、医師によって診断が変わるために、確定診断が出ていない場合もグレーゾーンとして捉えられる場合があります。
グレーゾーンは、境界知能と同様に正式な診断名ではありません。ただし、「ASD(自閉スペクトラム症)」「ADHD(注意欠如多動症)」「LD(学習障害*²)」という3つの障害の診断基準を一部満たしている場合や、すべては満たしていないケースを指します。一方で、境界知能はIQなどの知能検査の指標をベースに診断されるものです。
関連記事:発達障害グレーゾーンとは?特徴や困りごと、対策についても解説
境界知能と発達障害は併存する?
精神科医の臨床経験に基づくデータによれば、境界知能の方は、一般的なIQレベルの層よりも発達障害の割合が多い傾向にあることがわかっています。境界知能と発達障害が合併しているケースでは、自己肯定感が低い、劣等感を持っているといった特性が見られる場合もあります。
また、顕在化しにくい発達障害の場合、就労などで困難に直面するケースも少なくありません。そのため、発達障害への支援に加えて、さらに一歩踏み込んだ支援が必要になります。
自己肯定感が低い、劣等感があるといった状態が長く続くと、うつ病や双極性障害などの二次障害を発症する恐れがあります。境界知能や発達障害によって生きづらさを感じている場合は、ほかの精神疾患が現れる前に、専門機関などで適切な支援を求めることが重要です。
境界知能の方の特徴と困りごと
境界知能の方は、就職活動や仕事、社会生活など、さまざまな場面で困難に直面することがあります。「自分は境界知能ではないか」と感じている方は、境界知能の方によくある困りごとの例を参考にするとよいでしょう。
ここからは、境界知能の方の特徴や、よくある困りごとを具体的に紹介します。
就職活動が上手くいかない
境界知能の方は、就職活動に際して困りごとに直面する場合があります。
例えば、学生時代は通常クラスに在籍、勉強は苦手なものの無事大学にも進学し、問題なく進級できたとします。しかし、就活の段階でエントリーシートが書けない、面接でうまく答えられないといった困難が生じ、なかなか就職先が決まらない事態に追い込まれる場合があります。
ここで初めて医療機関を受診し、境界知能が判明する方も少なくありません。境界知能は問題が表面化しにくく、学校生活の終盤まで発覚しにくいケースも見られます。
仕事が続かない
境界知能の方は、物事の理解に時間がかかりやすい傾向があります。具体的には、漢字の読み書きや計算など数的な処理に苦手を感じる、物事の理解が表面的になりやすいために正確な意味を捉えにくい、といったものです。
そのため、就労の場面では、業務内容を覚えるのに時間がかかる可能性があります。また、口頭指示を理解することが難しい、複数の人から指示を受けると混乱して手が止まってしまう、漢字が多いマニュアルは意味を理解しづらい、といった傾向が見られる場合もあります。
また、境界知能の方はコミュニケーション面においても困難を感じやすいです。例えば、相手の言葉の意味を掴むことが難しく会話についていけない、自分が伝えたいことをうまく表現できない、といった困りごとを抱えやすくなります。
コミュニケーションの大変さからも、境界知能の方は人とのやり取りが苦手になってしまうことが考えられます。また、集団生活でのルールの理解が難しく感じられ、対人関係に影響が生じることもあるでしょう。
これらの傾向から、仕事でトラブルや悩みを抱えやすく、なかなか仕事を続けられない場合があります。
社会生活で困難を抱えやすい
境界知能にある人は、身の回りのことや社会生活で困りごとを抱えやすい傾向にあります。例としては、整理整頓や身だしなみを整えることなどに苦手を感じる、金銭管理や電車の乗り換えなどが難しい、といったものです。
また、生活の中で不適応や困難が重なると、うつ病などの二次障害につながる可能性もあります。
適切な支援が受けられない
知的障害や発達障害などの診断があれば、学生なら特別支援学級、社会人なら障害者雇用などのサポートが受けられます。しかし、境界知能などの診断がつかない方への支援制度は整っていないのが現状です。発達障害のグレーゾーンなども同じように、周囲の理解を得にくく、適切な支援が受けられないことは大きな問題といえます。
ただし、境界知能の方も職場で合理的配慮を求めたり、支援機関に相談したりすることは可能です。悩みを抱えている場合は、後述する相談・支援先を参考に、専門家にサポートを求めるとよいでしょう。
支援を必要とする境界知能の方
境界知能の中でも、特に手厚い支援が必要と考えられるのは以下に挙げる方々です。
- 発達障害の合併がある方(ASD、ADHD、DCDなど)
- 反応性愛着障害のある方
- 抑うつ状態にある方
顕在化しにくい発達障害の合併がある場合、就職活動などで困難に直面する可能性が高いでしょう。
反応性愛着障害とは、幼少期に養育者との愛着関係が適切に形成されなかった結果、対人関係における過度な警戒や無関心が引き起こされる状態です。
上記の条件に当てはまる場合は、医師に支援対象の診断名で書類を作成してもらったうえで、「より手厚い支援を要する」などと記載してもらう必要があります。なお、医師によって診断の基準や方針が異なる場合があるため、診断内容に納得がいかなければ、他の病院で再評価を受けるのも方法の一つです。
境界知能の方の相談・支援先
境界知能の特性による困りごとで悩んでいるときや、境界知能が疑われる場合に必要な支援やアドバイスを受けるためには、専門機関や相談場所の利用を検討しましょう。ここでは、相談先として主に4つの機関を紹介します。
発達障害者支援センター
発達障害支援センターは、発達障害のある人に対して総合的な支援を提供するための専門機関です。発達障害のある人が抱える日常生活や社会生活の困りごとに加えて、境界知能についての相談ができる場合もあります。
発達障害のある本人とその家族が豊かな地域生活を送ることを目的とし、医療・福祉・教育・労働など関係機関と連携して必要なアドバイスの提供や他の機関の紹介も可能です。
精神保健福祉センター
精神保健福祉センターは、障害や疾患のある人やその家族に対して、必要な支援や治療についての助言の提供を行う公的機関です。各都道府県および政令指定都市に設置することが定められており、地域の医療機関とも連携しながら相談窓口として機能しています。
センターでは、専門家によるカウンセリングやリハビリプログラム、心理検査などを提供しています。
就労移行支援
就労移行支援とは、就労を希望する障害のある人を支援するための障害福祉サービスです。全国にある就労移行支援事業所に通いながら、職業訓練や日常生活に関する指導を受けて、一般企業への就職を目指します。
仕事をするために必要な知識や能力の習得から就職活動の準備、面接対策、就職後の定着支援まで幅広いサポートが受けられます。また、就職や体調に関して就労支援員に相談することも可能です。
Kaienでも就労移行支援を行っており、約87%が専門資格を保有している相談員のカウンセリングを利用できます。適職が見つかるアセスメントや職業訓練も実施しており、サポート内容も豊富です。
就活支援においては、Kaienならではの独自求人を多数用意しており、就職後の定着率が95%と高いことも魅力の一つです。就労移行支援を利用する際は、2,000人超の就職者を輩出しているKaienをぜひご検討ください。
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある人が自立した生活を送るために、必要なスキルや習慣を身に付けることを目的とした支援を提供するものです。支援機関によって支援内容は異なりますが、食事や生活リズムなどの自立したライフスキルや、人との付き合い方などに関するトレーニング、助言を受けられます。
親や周囲の人の助けを得ずとも、健やかに毎日を送るために生活基礎力を付けたい人や、就労や自立に向けて自己理解を深めたいといった人などに適しています。
Kaienの自立訓練(生活訓練)では、学びのための「ギャップイヤー」を提供しています。就職や新生活のために役立つ知識やスキルを、年単位の時間をかけて習得することで、新たな一歩を踏み出せるよう準備するのです。
Kaienでは100以上のプログラムから自己理解を深め、自分なりの進路を探すことが可能です。自立に向けて将来を再設計したい方は、Kaienの自立訓練(生活訓練)をぜひご活用ください。
境界知能の方にも適切な支援や配慮が重要
境界知能はIQレベルが70〜84の層とされており、就活や仕事で困りごとを抱えるケースも少なくありません。
また、境界知能は発達障害と合併するケースもあり、実際に発達障害のある層に境界知能のある方の割合が高いというデータも出ています。学習面やコミュニケーション、社会生活において困りごとを抱えやすい傾向があるため、必要な配慮や支援を受けることが重要です。
Kaienでは、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)といった福祉サービスを提供しています。見学・個別相談会を随時実施しているので、サポートが必要だと感じている方はぜひお気軽にご相談ください。
*1発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
*2学習障害は現在、DSM-5では限局性学習症/Specific Learning Disability、ICD-11では発達性学習症/Developmental Learning Disorderと言われます。
監修者コメント
知能、とは人の様々な認知能力を捉える言葉であり、固定された1つの定義というのはありません。その意味で、知能指数で表現されるIQと知能という言葉が同義でないことは明らかです。例えばいわゆる知能テストと言われるWAISやWISCですが、ギフテッドとも言われる130以上であっても、社会的な技能が不足し、学習することも困難なことはあります。私の経験したある認知症の方はIQ116と非常に高い数値でありながら、前頭側頭型認知症と診断できる症状を呈していました。つまり高くても何もかもが優れているということは無いぞ、という限界を前提にした上で、低い場合に心配が多いのは確かです。知能テストが境界知能の結果であるときに、何らかの社会的支援が必要なことは多く、でも「境界」数値だけで判断されると必要な支援が公的に保障されないことが問題になりえます。最近私の外来では、これまでは特に問題を指摘されることもなかった、という30-40代の方が実は境界知能のIQであったということを経験します。特にコミュニケーション能力に長けていると、本来支援の必要があった部分に気づかれないで成人し、何か上手くいかないと困惑することもあるのです。診断書には、実際の生活や学習レベルに応じて、IQ数値以外の要素も丁寧に記載がされるべきと改めて考えるようになりました。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。