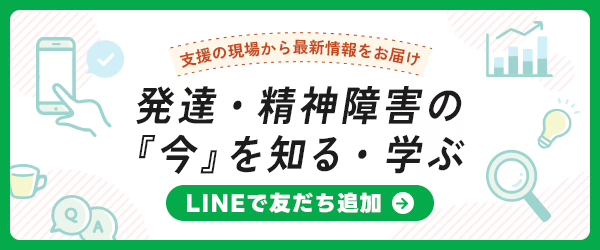発達障害*について「グレーゾーン」という言葉を耳にすることもあるのではないでしょうか。発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の症状や特性が見られるものの、診断基準をすべて満たさないために、発達障害だと正式な診断が出せない状態を意味します。
正式な診断が出されないため、グレーゾーンは症状が軽いととらえられる傾向があるものの、決してそうとは限りません。グレーゾーンの方は、発達障害の方に見られるいくつかの特性を持っているために、さまざまな困りごとを抱えているケースがよくあります。
この記事では、発達障害グレーゾーンの方の特徴や抱えがちな困りごと、また、その対処法について詳しく解説します。グレーゾーンで仕事や生活に困難を抱えている場合に相談できる相談先も紹介しますので、ぜひ最後まで目を通してみてください。
目次
発達障害の「グレーゾーン」とは
発達障害「グレーゾーン」とは、冒頭で触れた通り、発達障害の特性が見られるものの、発達障害と断定されない状態を指します。以下では、グレーゾーンとは一体どういうものなのか、発達障害の特性や、診断基準などから詳しく解説します。
発達障害の種類
発達障害グレーゾーンの特性を知るには、まず、発達障害について知るのが大切です。
発達障害とは、脳機能の発達に偏りがあるために生じる障害です。脳の働きの違いから日常や社会生活においてさまざまな支障を抱えやすい特性があります。
発達障害にはさまざまな種類があり、代表例としてよく挙げられるのは下記の3つです。
- 注意欠如多動症:不注意や多動性、衝動性という3つの特性により、日常生活に困難をきたしやすい発達障害
- 自閉スペクトラム症(ASD):対人関係やコミュニケーションに困難があり、独特のこだわりを持つなどの特性が見られる発達障害
- 限局性学習症:理解力に問題はないものの、読む・書く・計算するなど特定の学習能力において困難さを抱える発達障害
上記のような発達障害は、単独で単独で現れるわけではなく、併発することが少なくありません。例えば、注意欠如多動症と自閉スペクトラム症(ASD)の特性を同時に持つ発達障害の人は多いと言われています。
グレーゾーンの場合でも、異なる3つの発達障害それぞれの診断基準を完全に満たさないまでも、3つの発達障害のいくつかの特性が同時に見られるケースはよくあります。
発達障害の診断基準を満たさない「グレーゾーン」
発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の症状や特性が見られるものの、診断基準をすべて満たしていないために発達障害だと正式な診断ができない状態を指します。「グレーゾーン」は医学的な診断名ではなく、通称です。
発達障害の診断基準を満たさないからといって、グレーゾーンの方は症状が軽いかというと、そうとは限らない点に注意が必要です。
グレーゾーンの方も発達障害のいくつかの特性を持っており、その症状の濃淡も個人によってさまざまで、症状が強く出る人もいます。また、「空気が読めない」「約束を忘れる」といった特性も、障害のためでなく、単に怠惰や甘えととらえられるなど、周囲の理解が得られないために、困難を抱えるケースもあります。
そもそも発達障害は、タイミングや環境で表れる症状の強さが変わるため、受診当日にたまたま症状が強く出なかったために、グレーゾーンと判断されるケースも少なくありません。そのため、グレーゾーンだからといって、周囲の支援の必要がないかというとそうではないといえるでしょう。
グレーゾーンでも、仕事や日常生活で困難や生きづらさを抱えやすいため、なんらかの対策や支援が必要です。
発達障害の「重さ」、「軽さ」を測る医学的基準はない
まず発達障害の診断には、腫瘍マーカーやγ-GTPのような絶対的な数値基準が存在しているわけではありません。
診断は日常生活や社会生活上の困難・生きづらさがある点を確認することで行われます。
例えば現在診断基準とされるDSM-5※でもご本人や周囲の理解を数値化・リスト化しているだけとも言えます。
このため医師は断定を避け「グレーゾーン」や「傾向がある」という表現をすることが多いようです。
そもそも精神科や心療内科の医師にも得意・不得意があります。
「うつ」のアセスメントや治療が得意な医師や子どもの精神領域が得意な医師などがたくさんいる中で、発達障害の診断に積極的な精神科医師はまだ少数派のようです。このため発達障害の診断を自信をもって行える医師が少ないこともあるでしょう。
発達障害の特性の出方は「スペクトラム = 連続体」と言われるように個々人により濃淡が様々です。
同じ人であっても環境(つまりいる組織や置かれる状況)や年齢などにより変化します。
すべての人がグレーという考え方も出来るほどですのではっきりと言わない医師が多いのも頷けます。
※DSM-5 = 「精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版」アメリカ精神医学会作成
発達障害グレーゾーンの場合障害者手帳は取得できる?
障害者手帳の発行には医師による確定診断が必要なため、発達障害グレーゾーンの人は取得することができません。
「障害者手帳」とは、障害によって日常生活や仕事における困難や支援を必要とする人に対して発行される手帳です。障害者手帳を取得することで、税金の減免や公共料金の割引などが受けられるというメリットがあります。
障害者手帳の3種類のうち、発達障害の場合は「精神障害者保健福祉手帳」、発達障害と知的障害が見られる場合は「療育手帳」の申請対象となる可能性がありますが、確定診断が出ていないグレーゾーンの場合は取得対象外とされています。
ただし、障害者手帳や周囲からの配慮を必要としていることを医師に伝えれば、意見書や診断書を発行してくれるケースがほとんどです。障害者手帳が必要な場合は、まず医師に相談してみましょう。
グレーゾーンの方の特徴や抱えやすい困りごと
発達障害と正式に診断されないグレーゾーンの人は、個人差があるものの、日常生活においてさまざまな困りごとに直面する場合があります。以下では、よくある困りごとについて、具体的に解説します。
人間関係でトラブルを抱えやすい
グレーゾーンの方は、人との関わりの中で、コミュニケーションがうまくいかないなど、トラブルを抱える場面があります。
仕事や日常生活において良好な人間関係を築くには、相手の表情から感情を察したり、周囲に合わせて行動したりするといった表情や空気を読む力が必要です。
下記のような特性が見られるグレーゾーンの方は、そうした人間関係を築く上で困難を感じやすいといえるでしょう。
- その場の空気を読んだ対応ができない
- 相手の行動や表情から感情を読み取れない
- 相手の話をさえぎって一方的に話す
- 思ったことを口に出す
- 過剰に気配りをするもポイントがずれる
上記のような特性で人とのコミュニケーションに問題を抱えやすいため、人と関わるのに自信を失ったり、苦手だと感じたりする人も少なくありません。
スケジュール管理が苦手
グレーゾーンの方の中には、スケジュール管理が苦手な方もいます。予定を忘れてしまったり約束に間に合わなかったりといった、困りごとを抱える方も少なくありません。
スケジュールを管理するには、期限やタスクを把握し優先順位をつけて時間を見積もり、計画性を持って、柔軟に対応する必要があります。
そのため、下記のような発達障害の特性を持ったグレーゾーンの方は、スケジュール管理を苦手とする傾向があるといえるでしょう。
- 頼まれた用事や約束を忘れやすい
- 物事の優先順位をつけられない
- マルチタスクができない
- 先を見通した行動が取れない
- 目前のことに没頭し、やるべきことを忘れてしまう
- 臨機応変な対応ができない
- 曖昧な指示が理解できない
上記のような特性があると、スケジュール通りに業務を遂行できないといった状態に陥り、トラブルを抱えやすくなります。
仕事が長く続けられない
仕事が長く続けられないといったのも、グレーゾーンの方の抱えやすい問題の一つといえます。
特に下記のような特性を持つグレーゾーンの方は、職種や業務内容によってはトラブルを抱えやすく、仕事を長く続けにくい傾向があるといえるでしょう。
- 臨機応変な対応が苦手
- 曖昧な指示が理解できない
- 興味のない業務には集中できない
- 同じミスを何度も繰り返してしまう
- マルチタスクができない
- 業務の優先順位がつけられない
- 納期や頼まれた業務を忘れてしまう
- 悪気はないのにクライアントや上司を怒らせてしまう
- 音やにおいが気になって仕事に集中できない
上記のような特性で、業務に大きな支障が出るような場合は、仕事内容や職場環境が自分に合っていない可能性があります。結果として、精神的な不調を抱えたり、転職を繰り返したりするケースも少なくありません。
周囲の理解を得られにくい
グレーゾーンの方は、正式に障害があると診断されないことにより、周囲の理解を得られにくいといった困りごとを抱えるケースもよくあります。
先述の通り、グレーゾーンだからといって、症状の程度が軽いわけではありません。しかし、強い症状があっても、本人の甘えや性格の問題と見なされてしまうことがよくあります。
例えば、「同じミスを繰り返してしまう」といった特性も、障害と正式に判断されていれば、周囲の支援を受けやすいかもしれません。しかし、グレーゾーンの場合は、本人の気持ちや性格の問題と判断され、理解や支援を得にくいのが現実といえるでしょう。
グレーゾーンの方は、発達障害のいくつかの特性により困難を抱えていても、適切なサポートを受けられないだけではなく、批判や非難の対象となってしまう場合も少なくありません。このように、周囲の理解が得られないために、本人の苦しみが増しているケースがあります。
グレーゾーンの方の困りごとの対処法
グレーゾーンの方が、仕事や日常生活で抱える困りごとを解消するための対処法を5つ紹介します。
発達障害の二次障害の症状はないか受診する
発達障害の二次障害の症状が出ていないか受診することも、対処法として有効です。
発達障害の二次障害とは、発達障害の特性のため仕事や周囲との人間関係がうまくいかず、うつ病や適応障害などの精神疾患を発症することです。グレーゾーンの方でも、発達障害の二次障害を発症するケースがよくあります。
二次障害が原因で生きづらさが生じている場合、二次障害の治療として認知行動療法や薬物療法を受けることで、苦しみが緩和されたり解消したりします。
また、発達障害では「重ね着症候群」という症状があります。これは、さまざまな精神障害の困難が重ね着のように見られる人の、その着物をはいでいくと、発達障害が根幹にあるといった症状です。
二次障害の診断をきっかけに、その根底に発達障害があると判断され、発達障害から生じる困難に対処できるケースもあります。
自己理解を深める
自己分析をするなどして自己理解を深めるのも対処法の1つです。
自分の強みや弱みといった特性を把握することで、トラブルを避けたり、解消したりする方法を考えやすくなります。自分はどのような場面が苦手でどのような困りごとを抱える傾向があるのか、反対にどういったシチュエーションであれば問題なくすごせるのかなど、自分を深掘りしてみましょう。
例えば、自分の特性や困難をノートに記録して振り返ってみたり、家族や友人からフィードバックを受けたりするのもよいでしょう。発達障害かどうかの診断を受ける際の心理検査でも、得意・不得意などの特性を把握できます。
何が得意で何が苦手かを明確にしておくと、自分にあった仕事や働き方を考える上で役立ちます。
苦手なことを頑張るより得意なことを活かす
自己理解を深めて自分の特性が把握できたら、苦手なことを克服しようとするのでなく、得意なことを活かすのも一つの手です。
グレーゾーンの方は、障害と判断されないため、ただ「変わった人」と周囲からとらえられ、理解やフォローが得られないケースが少なくありません。理解が得られない中で、無理に苦手な作業を頑張ろうとしても大きなストレスを抱えてしまいます。
そうした場合、短所の改善に強くこだわるよりも、長所を活かす方向に目を向けてみるのもよいでしょう。
グレーゾーンの方の中には、興味分野において高い集中力や記憶力を発揮する、ルールや規則を守るのが得意、論理的思考が強い、反復作業が得意といった特性を持つ方もいます。
弱みの克服に注力するより、そうした強みを仕事や日常生活に活かした方が、生きづらさが軽減しやすくなるかもしれません。
周囲の人の協力を得る
あらかじめ自分の特性を話すなどして、周囲の人の理解や協力を得ることも、生きづらさや困難を解消するために必要です。
グレーゾーンの方は、診断名がないとはいえ症状が軽いとは限りません。症状のせいで、仕事や日常生活において実際に影響が出ている場合は、特性を共有しながら周囲の理解や協力を得るのがトラブルを起こさないためにも必要といえるでしょう。
例えば、曖昧な指示が理解できない特性や空気を読みにくい特性から、抽象的ではなく明確な指示を出してもらいたい旨を相談すると、具体的な指示を出してもらえるようになります。
明確に何をいつ、どのようにやれば良いのか理解することで、納期に間に合わないなどのトラブルや細かなミスを防ぎやすくなるでしょう。また、予定や約束を忘れやすい点を相談すると、リマインドの方法やTodoリストの作成など対策を一緒に考えてもらえるかもしれません。
前述のように、グレーゾーンについて周囲の理解を得るのは簡単ではないかもしれません。それでもまずは、信頼できる身近な人に話してみて協力を得ることから始めてみましょう。
グレーゾーンの方が利用できる専門機関を活用する
発達障害という診断のないグレーゾーンの方でも利用できる専門機関があるため、そうした専門機関を活用するのも対処法の一つです。
グレーゾーンの方でも活用できる専門機関には、ハローワークや発達障害者支援センター
就労移行支援、自立訓練(生活訓練)などさまざまな機関があります。
専門機関では、グレーゾーンの特性による困りごとについての相談ができ、さまざまな支援を受けられます。困りごとや生きづらさの軽減・解消に役立つため、ぜひ活用してみてください。グレーゾーンの方が利用できる専門機関は次章で詳しく解説します。
グレーゾーンの方が利用できる支援サービスや相談先を紹介
発達障害グレーゾーンの方が、仕事や日常生活における困りごとに関して相談できる機関があります。以下では、5つの相談先について詳しく紹介します。
ハローワーク
ハローワークは、厚生労働省が運営する職業紹介所です。各都道府県に設置されており、無料で職業紹介や就労支援サービスを行っています。
一般の相談窓口とは別に、発達障害がある方に対する就業サポートのために、障害への専門知識を持つ担当者によるサポートが受けられる「障害者相談窓口」を設置しています。
障害者手帳を持っていない場合でも、自身の特性による困りごとを相談し、求人情報の提供や就職活動のアドバイス、就職後の継続的な支援などを受けることが可能です。
また、個人に合った求人情報の提供あっせんや採用面接への同行、障害のある方を対象とした就職面接会も随時行っています。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターは、発達障害のある方への総合的な支援を目的とした専門的機関です。各都道府県や政令指定都市に設けられており、都道府県知事等が指定する社会福祉法人や特定非営利活動法人などにより運営されています。
発達障害者支援センターでは、発達障害のある人やその家族の日常生活や就労におけるサポートや相談を行っています。診断を受けている人はもちろん、診断を受けていないものの発達障害の可能性がある人に対する支援も提供しています。
センターでは基本的に無料で相談することが可能です。ただし、サービス内容は各自治体によって異なるため、詳細について直接問い合わせてみましょう。
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害がある方の雇用の促進および安定を図ることを目的とし、全国に設置されている機関です。発達障害を持つ就業者、あるいは就業を希望している人に対し、日常生活の自己管理に関する支援と、衣食住を安定させるための支援や制度の紹介を行っています。
具体的には、就労支援機関と連携した仕事探しや入社前後のサポート、日常生活のアドバイスなどです。2023年4月時点で全国に337ものセンターが設置されており、立ち寄りやすい施設を見つけやすいでしょう。
就労移行支援
就労移行支援とは、一般企業などでの就労を希望している障害のある方をサポートする障害福祉サービスです。障害者手帳がなくとも、医師の意見書や診断書があれば利用が認められるケースがあります。
就労移行支援を利用すると、就労前や就労後に必要となる知識やスキル向上のためのプログラムが受けられます。例えば、グレーゾーンの方が苦手とするビジネスマナーを学んだり、職種体験を通じて自己理解を深めたりすることも可能です。適性にあった就職先探しや、応募書類・面接対策、就労後のフォローアップといったサポートも受けられます。
なお、Kaienの就労移行支援は、発達障害の方のサポートに豊富な実績があり、グレーゾーンの方でも、働きたいという意思があればご利用いただけます。
就労移行支援について詳しくは下記の記事も参考にしてください。
関連記事:就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)とは、障害のある人が自立した生活を送れるように、さまざまな生活上のスキルの維持・向上に向けた訓練を行う障害福祉サービスです。発達障害グレーゾーンの方も、医師の診断書や意見書があれば利用できる可能性があります。
Kaienでは、グレーゾーンの方も利用できる自立訓練(生活訓練)を提供しています。自立訓練(生活訓練)では、コミュニケーション力を高める方法や、優先順位をつける方法、感情をコントロールする方法など生活基礎力を高めるプログラムの受講が可能です。
自立訓練(生活訓練)を活用して、生活基礎力を向上させると、日常生活はもちろん、働く上でも生きづらさや困難さを軽減できるでしょう。
就労移行支援や自立訓練(生活訓練)など、グレーゾーンの方でも利用できる障害福祉サービスについて詳しくは、下記の記事も参考にしてください。
関連記事:障害福祉サービスとは?種類や対象者、利用の流れを解説 – 株式会社Kaien – 強みを活かした就労移行支援・自立訓練(生活訓練)
グレーゾーンの方で困りごとを抱える方はKaienにご相談ください
発達障害グレーゾーンの方は、発達障害の診断基準をすべて満たさないからといって、症状が軽いわけではありません。生きづらさや困難を抱えている場合には、周囲の理解や協力を得るようにしたり、専門機関に相談したりするといった対処法を取ることが大切です。
グレーゾーンで、困りごとを抱えている場合には、発達障害の支援に豊富な実績と経験のあるKaienに、ご相談ください。
Kaienの就労移行支援や自立訓練(生活訓練)は、発達障害のグレーゾーンの方でも医師の意見書や診断書があれば、ご利用いただけます。グレーゾーンの方が自分の特性や強みを活かして就労を目指せるプログラムや、生活基礎力を高めるプログラムを提供しています。
ご相談やご見学は、オンラインでも事務所でも、ご家族だけでもご参加いただけるため、お気軽にお問い合わせください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます
監修者コメント
「グレーゾーン」は悩ましい言葉です。発達障害特性があるのに診断しない/できないと言っているわけですから。また、発達障害に限りませんが、精神科診断は検査値によって自動的につけられるものではないので、診察する医師によるバラツキが避けられない面もあります。当事者にとって「診断によって今後の生活が良い方向に変わる」のであれば、最初の診察や検査をしてもらうときに、むしろ診断を望んでいることを伝えても良いかもしれません。私個人の意見ではありますが、「診断する勇気がないから」診断せず、グレーゾーンという耳あたりが良い言葉で済ましてしまっている医師が多いようには感じています。私自身は支援が必要な場合には積極的に診断することが殆どで、「グレーゾーン」という言葉は基本的に使わないようにしています。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。
あなたのタイプは?Kaienの支援プログラム
お電話の方はこちらから
予約専用ダイヤル 平日10~17時
東京: 03-5823-4960 神奈川: 045-594-7079 埼玉: 050-2018-2725 千葉: 050-2018-7832 大阪: 06-6147-6189