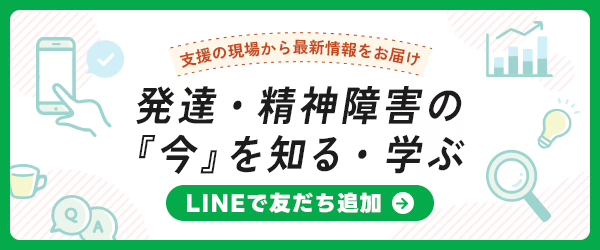ストレスや心の不調によって、休職を経験する人は年々増えています。そんな中、リワーク(再び働く)のための支援として注目されているのが「リワークプログラム」です。
リワークプログラムとは、休職中の方が無理なく職場に戻れるよう、医療機関や福祉施設、行政機関、職場などが連携して行う職場復帰支援です。広い意味では、就職や社会復帰をめざす支援全般を含めて使われる場合もあります。
この記事では、リワークプログラムの概要や種類、対象者、利用の流れや費用、具体的な内容例や得られるメリットを紹介します。さらに、リワークを検討中の方が利用できるサービスについても解説するので、関心のある方はぜひご覧ください。
目次
リワークプログラムとは
リワークプログラムとは、うつ病・パニック障害・気分障害・統合失調症など、精神疾患が原因で休職している労働者の職場復帰をサポートするためのプログラムです。「職場復帰支援プログラム」や「復職支援プログラム」とも呼ばれていますが、すべて同義語になります。
プログラムの内容は実施機関によって異なりますが、下記のような職場復帰に向けたリハビリテーションやトレーニングが中心です。
- 実務に近いデスクワークや軽作業を体験し、基礎体力や業務遂行能力の向上を図る
- 集団レクリエーションに参加し、対人スキルの向上を図る
- 心理療法を受けて、精神疾患の再発を防ぐ
また、決まった日時に決まった施設へ通うことで、規則正しい生活リズムの確立を目指します。
それでは、次項よりリワークプログラムの種類と対象者について解説します。
参考:厚生労働省「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」
リワークプログラムの種類
リワークプログラムと一口にいっても多種多様ですが、実施機関によって大きく4種類に分類されます。
- 医療機関でのリワーク(医療リワーク)
主に精神科や心療内科が実施しています。精神疾患に伴う症状の安定や回復、再休職の予防を目的とする医学的リハビリテーションを受けられることが特徴です。
- 就労移行支援・自立訓練(生活訓練)のリワーク
福祉施設や民間機関に通所し、スキル習得や職場復帰後の定着に向けたサポートを受けます。休職者だけではなく、就職未経験者や離職者も利用することが可能です。また、障害のある方の自立をサポートする「自立訓練(生活訓練)」も利用できます。
- 障害者職業センターでのリワーク
各都道府県にある地域障害者職業センターが実施しています。休職者・雇用主・主治医の3者で調整した職場復帰プランをもとに、トレーニングやカウンセリングを行うことが特徴です。
- 職場でのリワーク
休職者が所属する企業内で行われるものです。企業が策定した「職場復帰支援プログラム」をもとに、独自の職場復帰訓練制度や外部サービスによる従業員支援プログラム(EAP)を実施しています。
自分に合ったプログラムを見つけるためにも、それぞれの特徴を押さえておきましょう。
リワークプログラムの対象者
リワークプログラムの対象者は、リワークプログラムを提供する機関によって以下のように異なります。
- 医療機関でのリワーク(医療リワーク)の対象者
休職者
- 就労移行支援・自立訓練(生活訓練)の対象者
休職者、離職者、就職未経験者
※原則として、精神疾患や発達障害*などの障害のある方
- 障害者職業センターでのリワークの対象者
民間企業などの雇用保険適用事業所に雇用されている休職者(公務員を除く)
- 職場でのリワークの対象者
休職者
不明な点がある場合は、各機関の窓口や主治医などに相談しておきましょう。
リワークプログラムの内容例
「リワークって何をするんだろう?」「むずかしい訓練ばかりだったら続けられるか不安…」と感じている方もいるかもしれません。しかし、実際のリワークプログラムは、少しずつ働く準備ができるように進められます。
代表的なプログラムは以下の5つです。
- ソーシャルスキルトレーニング(SST):人とのかかわり方や伝え方を練習します
- 認知行動療法(CBT):考え方のくせに気づき、気持ちを整える方法を学びます
- グループワーク・レクリエーション:仲間と協力しながら働く力を育てます
- キャリアデザイン:自分の強みや将来の働き方を見つめ直します
- オフィスワーク・オフィストレーニング:実践的な職業スキルを身につけます
各プログラムについて詳しく解説します。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)
ソーシャルスキルトレーニング(SST)とは、自分の意思の伝え方や他人との接し方など、社会生活に欠かせないスキルを習得するための訓練です。「社会生活技能訓練」とも呼ばれています。
一般的にソーシャルスキルトレーニングは、少人数(5~8人程度)のグループを作って実施します。社会生活において人とかかわるシーンを想定しつつ、ロールプレイやゲームの形式でコミュニケーションの実践練習をしたり、グループ内のメンバーと協力して作業に取り組んだりするといった内容です。
また、精神疾患の再発を防ぐため、症状への対処方法や薬の知識を学ぶ心理教育プログラムを実施するケースもあります。
参考:国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 地域精神保健・法制度研究部 こころとくらし「社会生活技能訓練 (SST)」
参考:厚生労働省 こころの耳「ソーシャル・スキル・トレーニング」
認知行動療法
認知行動療法とは、人間の物事に対するとらえ方(認知)に働きかけることで、メンタルヘルスを整える心理療法(精神療法)の一種です。「認知療法」や「CBT(Cognitive Behavioral Therapy)」とも呼ばれています。
日頃から強いストレスを受けている人や精神疾患を抱えている人は、悲観的な思考や感情を持ってしまいやすいです。すると物事を極端なとらえ方(歪んだ認知)で見るようになり、状況に即さない判断や行動が増えてしまう可能性もあります。
このような歪んだ認知を患者とともに確認し、改善へと導くことが認知行動療法の目的です。医師は患者が現実的かつ柔軟なとらえ方を選択し、患者自身が持つ本来の力を発揮できるよう、カウンセリングやグループセッションによって不安や動揺の解消を図ります。
認知行動療法は多くの精神疾患に対する治療効果が認められており、医学研究でも有効性が立証されてきています。
参考:NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター「心理検査・各種心理療法(認知行動療法)」
参考:国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 認知行動療法センター「認知行動療法(CBT)とは」
グループワーク・レクリエーション
グループワーク・レクリエーションでは、グループ内のメンバーと協力しながらゲームやトレーニングを実践し、職場復帰に必要なスキルを養っていきます。
一見、ソーシャルスキルトレーニングと似ていますが、グループワーク・レクリエーションは対人関係のスキル向上だけではなく、基礎体力の向上やリフレッシュなども目的に活動できます。
キャリアデザイン
キャリアデザインとは、自分らしいライフスタイルを実現するため、仕事を通じて将来の目標やビジョンを設計したうえで、その過程で必要なプロセスを明確化することです。
リワークプログラムを利用する場合、第一の目標は職場復帰なので、職場復帰に向けて自分を見つめ直す必要があります。
- 自分の強み・弱みは何なのか?
- どのような仕事ができるのか?
- いつまでに職場復帰を果たしたいのか?
- 1年後に自分はどうなりたいのか?
このように近い未来の生き方や働き方も見据えて考えると、自分のやりたいこと・やるべきことが見えてくるため、これらをリワークのスタッフと一緒に考えていきます。
オフィスワーク・オフィストレーニング
オフィスワーク・オフィストレーニングとは、職場復帰後の実務と同じような作業内容・環境で行う訓練のことです。主に下記のようなデスクワークや軽作業がメインとなっています。
- パソコンのワープロソフトを使った文書作成・修正
- パソコンの表計算ソフトを使ったデータ入力・集計
- 帳簿の作成
- 書類のコピー・ファイリング
- 郵便物の仕分け・発送
これらの作業を通じて、業務遂行に必要な集中力や忍耐力を養うことが目的です。スキルアップはもちろん、資格取得に必要な知識も学べます。
また、決まった日時に決まった施設への通所を継続することは、通勤のトレーニングにもなります。作業に取り組む過程で他人とかかわる機会も多いため、コミュニケーション能力の向上を図ることも可能です。
リワークプログラムを受けるメリット
リワークプログラムは、スムーズな復職につなげるだけでなく、再休職のリスクを下げながら無理なく働き続けるうえでも有効です。
ここからは、ストレスがやわらいだり、物事の受けとめ方が変わったり、日常生活を見直すきっかけになったりするなど、プログラム受講者のメリットに注目して解説します。
再休職のリスクが抑えられる
復職後の職場環境が大きく変わらないことは珍しくありません。こうした場合、自分の感情や人間関係の課題に適切に対処できるソーシャルスキルの向上が重要です。
リワークプログラムでは、感情コントロールの練習を行います。また、グループワークを通じて、「どう話せば気持ちが伝わるか」「どのような振る舞いが協力を得やすいか」などを体験的に学ぶプログラムも用意されています。
こうしたプログラムは、同じ原因や症状の悪化による再休職や退職のリスクを抑えるうえで効果的です。実際にリワークプログラムの利用者は、利用しなかった人と比べて、復職後に長く働き続けるという調査結果が示されています。
参考:NIVR「精神障害者職場再適応支援プログラム リワーク機能を有する医療機関と連携した復職支援」
生活リズムの改善が期待できる
休職中は、不眠や体調不良などの影響で、生活リズムが乱れる方がいます。決まった時間に起きて出勤する必要がなくなるため、昼夜の区別があいまいになっている方もいるでしょう。
通所型のリワークに通うと、規則正しい生活を自然と送りやすくなる点がメリットです。毎日決まった時間に通う習慣がつくことで、起床時間や食事のタイミングも安定してきます。週に何日かの参加でも、体を動かすリズムや睡眠の時間が整ってきたと感じる方もいるでしょう。このようにリワークを利用するのは、休職中の乱れがちな生活習慣を整えるきっかけになります。
また、規則正しい生活は、精神の健康にも良い効果をもたらすと考えられています。不安や抑うつ感、イライラといった不調が軽くなる可能性も期待できるでしょう。
ストレスへの対処法を身につけられる
職場でのストレスが重なり、休職に至る方は少なくありません。こうしたストレスは、自分の考え方や受けとめ方を少し変えるだけで、やわらぐ場合もあります。
リワークプログラムでは、ストレスへの対処法を身につけられるのがメリットです。たとえば、思考や行動を記録して自分の考え方や行動のくせに気づき、それに合った対処の方法を探るプログラムがあります。また、カウンセリングを通じて自己理解を深めることで、仕事へのモチベーションを保ちやすくなるケースもあるでしょう。
ストレスへの対応が上手になると、無理なく働き続けやすくなります。日々の生活も安定し、仕事への活力も少しずつ戻ってきやすくなるのではないでしょうか。
仕事に必要な体力や持続力、集中力が身につく
精神的な不調を経験し休職した後は、疲れやすくなったり、少しの作業でも集中が続かなかったりする場合があります。復職後に短時間労働や隔日出勤などを認めてくれる職場もありますが、体力や気力が大きく落ちていると、それすらも負担に感じる場合があるでしょう。
こうした不安がある際に、リワークプログラムで軽作業や職業訓練に取り組みながら、自分がどのくらいの時間で疲れるのかを確認できます。あらかじめ適切な体力の使い方を身につけておけば、復職後に再び体調を崩すリスクを抑えられます。
またリワークプログラムでは、休み方や仕事の進め方といった、体力や集中力を保つ工夫を実践的に学べる点もメリットです。たとえば、段階的に仕事の量を増やしていくためのセルフモニタリング方法を知っておくと、復職後にオーバーワークになってしまう事態を避けやすくなります。
リワークプログラムの利用までの流れ
リワークプログラムを利用する際は、おおまかに以下の流れで進みます。
- 主治医にリワーク通所の可否を相談する
精神科や心療内科の医師に、プログラムに通える状態かを確認します。
- 実施機関へ問い合わせる
利用対象者の条件を満たしているか確認します。診断名や状況によっては利用できない場合もあります。
- 説明会に参加する
プログラムの目的や内容、通所ルールを聞きます。
- 個別相談・申し込みを行う
説明会後に個別相談を受け、その上で申し込みに進みます。診断書や紹介状が求められることもあります。
- 主治医や支援担当者と支援計画を立てる
通所の頻度や目標などを話し合い、生活リズムや病状に応じて支援内容を調整します。
- リワークプログラムに参加する
通所を始め、軽作業やグループワークなどに取り組みながら復職準備を進めます。
- 職場復帰の調整を行う
一定期間の通所後、主治医に相談して職場復帰可能の診断書をもらい、職場と復帰時期や働き方を調整します。
- 復職後のフォローを受ける
復職後も支援機関のフォローを受けながら、無理なく働き続けます。
利用する機関によって手続きは多少異なるため、事前に確認しておくようにしましょう。
リワークプログラムの費用
リワークプログラムを利用する際にかかる費用は、実施主体によって変動します。
| 医療機関 | 就労移行支援事業所・自立訓練(生活訓練) | 障害者職業センター | 職場 | |
| 費用の有無 | 有料 | 有料 | 無料 | 無料 |
| 費用の目安 | 3割負担:1日2,000~3,000円1割負担:1日700~1,000円 | 生活保護受給世帯:0円市町村民税非課税世帯:0円市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):9,300円上記以外:3万7,200円 | 0円 | 0円 |
医療機関でのリワークは医療費がかかりますが、保険診療の一種に含まれるため、健康保険で3割負担に抑えられます。自立支援医療制度を適用すれば、1割負担になります。
就労移行支援事業所でのリワークも有料ですが、9割は行政側が負担してくれるため、利用者は1割負担です。ただし、世帯収入によって負担上限月額が決まっており、無料で利用できるケースもあります。
障害者職業センターでのリワークは無料です。ただし、交通費や昼食費は自己負担となります。
職場でのリワークは企業側が費用を負担してくれるため、基本的に無料で利用可能です。
参考:NCNP病院 国立精神・神経医療研究センター「リワークデイケアについて」
参考:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「リワーク支援の利用に関するQ&A」
リワークを検討している方が利用できるサービス
病気や障害を抱えながら復職の活動を一人で行うと、無理が重なってしまいます。ここでは、復職を検討している方が利用できるサービスとして、医療のデイケア、就労移行支援、自立訓練(生活訓練)の3つを紹介します。
医療のデイケア
医療のデイケアリワークは、主にうつ病や適応障害などで休職中の方が、職場復帰や再発予防を目指して参加します。主治医を変えずに利用できることが多く、治療とリハビリテーションを一体的に進めやすい点が特徴です。
医療のデイケアでは、生活のリズムを整え、働く力を段階的に回復するプログラムを行います。導入期では、通所の習慣をつけながら、軽作業や運動などで生活リズムと体力を整えます。中期は、認知行動療法やストレス対処など、心の偏りに気づき対処するプログラムが中心です。後期になると、職場とのやりとりや勤務形態の調整など、具体的な復職準備を進めます。
医療のデイケアは医療機関によって内容が異なるため、主治医や実施機関に相談してみましょう。
就労移行支援
就労移行支援は、一般企業への就職をめざす障害のある方をサポートするサービスですが、休職者も利用可能です。自己分析から職業訓練、職場定着支援まで、一貫したサポートを受けられます。
パソコン操作やビジネスマナーなど、実際の仕事に近い訓練が多い点も特徴です。これらは、休職中の方のオフィストレーニングとして活用できるでしょう。
また、発達障害や精神障害の方に特化したKaienの就労移行支援では、専門知識を持つスタッフが在籍しています。たとえば、障害の特性に合わせたカウンセリングを受けたり、自分に合った働き方を見つけるためのトレーニングを受けたりすることが可能です。結果的に、新たな職種、職場への転職に至る場合もあります。
さらに、職場への定着支援が受けられるのもメリットです。たとえば「聴覚過敏のため静かな席で働きたい」といった合理的配慮の要請を、本人の代わりに会社へ相談してもらえます。
自立訓練(生活訓練)とは?就労移行支援との違いや併用についても解説
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)は、障害のある方が、将来の就労や社会参加を見据えて、生活リズムや感情の安定、対人関係の練習など、自立的な生活に必要な力を身につけるためのサービスです。一例を挙げると、感情コントロールの練習や、スケジュール調整のスキルを学ぶ講座などがあります。
このため、自立訓練(生活訓練)は、就労準備に進む前の第一歩として利用しやすいサービスです。復職や就職をしたいものの、精神的・肉体的な状況が整っていない際に、自立訓練(生活訓練)を活用するとよいでしょう。
自立訓練(生活訓練)によって復職、就職のための活動ができるようになってから、就労移行支援や医療のデイケアを利用する方法もあります。
就労移行支援や自立訓練(生活訓練)でのリワークをご検討中の方はKaienにご相談ください
リワークプログラムは、心や体を整えながら、少しずつ働く力を取り戻すための支援です。ただし、一口にリワークプログラムといっても、現在の職場に復帰したい方に適したサービスや、就労前に生活基盤を整えたい方に適したサービスなど、複数の種類があります。ご自身に合ったプログラムを受けられるサービスを選んでいきましょう。
Kaienの就労移行支援は、復職や就職をめざす方に向けたサービスが中心で、実践的な職業訓練や自己理解のためのカウンセリングなどが利用できます。また、職場定着のための支援も利用可能です。
一方、Kaienの自立訓練(生活訓練)は生活スキルや感情の安定など、働く前の土台を整えたい方に向いているサービスです。いきなりリワークの活動を始めるのがむずかしい場合に向いています。
Kaienでは、発達障害や精神障害のある方に特化したプログラムを実施しておりますので、お気軽にご相談ください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修者コメント
リワーク(Re-work)は、実は和製英語です。英語圏では”Return to Work Program”や”Occupational Rehabilitation”といった表現が用いられます。日本では「職場復帰支援プログラム」を意味する造語として定着し、主にうつ病などの精神疾患で休職した方が、安全かつ確実に職場復帰するための専門的な支援プログラムを指します。
ヨーロッパでは、より早期の段階での職場復帰支援が重視されています。特にワークシェアリングの進んだオランダでは、産業医や職場との密接な連携のもと、部分的な就労から段階的に労働時間を延ばす「段階的復職制度」が確立されています。長期間完全に休職するのではなく、早期から職場との接点を保ちながら回復を図るアプローチが主流です。これに対し日本では、完全休職後に十分回復してから復職するという文化が根強く、その間のリハビリテーションとしてリワークプログラムが発展したのが実情です。
両者のアプローチには違いがありますが、いずれも「働く人の回復と再発予防」という共通の目標を持ちます。

監修:中川 潤(医師)
東京医科歯科大学医学部卒。同大学院修了。博士(医学)。
東京・杉並区に「こころテラス・公園前クリニック」を開設し、中学生から成人まで診療している。
発達障害(ASD、ADHD)の診断・治療・支援に力を入れ、外国出身者の発達障害の診療にも英語で対応している。
社会システムにより精神障害の概念が変わることに興味を持ち、社会学・経済学・宗教史を研究し、診療に実践している。