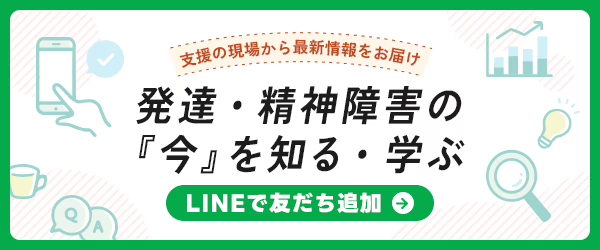就職はできるものの、なかなか仕事が続かずに悩んでいる方も多いでしょう。特に、発達障害*の方は職場の環境に適応するのが難しいケースも見られます。まずは仕事が続かない方に共通する特徴を押さえ、長く続けるための対処法を実践していくとよいでしょう。
この記事では、仕事が続かない人の特徴やデメリット、働き続けるための対処法などについて解説します。発達障害の方が利用できる支援サービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
目次
仕事が続かない人の特徴とは?
仕事が続かないケースでは、もともとの性格が原因の場合もあれば、発達障害の特性が影響している場合もあります。なかなか仕事が続かずに悩んでいる方は、よくあるケースから自分に当てはまる特徴を探してみるとよいでしょう。
ここからは、仕事が続かない人の特徴をいくつか紹介します。それぞれの項目で、発達障害の特性が影響するケースも併せて解説するので参考にしてみてください。
人間関係に関するストレスを感じやすい
人とのコミュニケーションが苦手で、同僚と協力して働けない、孤独を感じるといった問題を抱える方も少なくありません。
原因の一つは、職場の人間関係にストレスを感じやすい性格であるため、同じ仕事を長く続けられないケースです。どの職場でも大なり小なり人との関わりはあるため、人間関係でストレスを抱えやすい方は転職を繰り返しがちになります。
一方、発達障害の方は、特性により相手の意図や感情を正確に読み取ったり、社会的なルール・場面に適応したりするのが難しい場合があります。これらの特性から人間関係でストレスを感じやすく、早期離職につながるケースも珍しくありません。
さらにASD(自閉スペクトラム症)のグレーゾーン傾向の方は、発達障害の診断基準を満たしていないものの、社会生活での違和感やストレスを感じやすいのが特徴です。必要以上に気を遣い、他者に合わせようとする過剰適応を起こす場合があり、長期的な心身の疲労や不安の蓄積につながる場合があります。
参照:障害者職業総合センター「発達障害者のコミュニケーション・スキルの特性評価に関する研究」
ミスをして叱られるのが怖い
誰もが失敗をして叱責されるのは怖いものです。「また叱られたらどうしよう」という不安や「ミスをしないように仕事をしなくては」という緊張が重なるとストレスが溜まり、働き続けることが困難になるケースも少なくありません。
発達障害の方、特にADHD(注意欠如多動症)の方の場合、不注意や計画性の欠如といった特性から仕事でミスをしやすい傾向にあります。また、処理速度の遅さから作業が他人よりも長引き、結果的に叱責を受ける場面が増え、精神的な負担を感じる場面が多いです。これらに適応するには、認知行動療法やタスクの分割方法を学ぶなどが効果的と考えられており、適切な支援があれば職場でのストレス軽減に繋げるのも可能となるでしょう。
物事に飽きやすい
飽きやすい性格の方は、新しい仕事には強い興味を持ちますが、同じ仕事を長期間続けるのが得意ではありません。隣の芝生は青く見えると言うように、自分の仕事よりも他の仕事が望ましいように感じ、すぐに転職してしまう傾向があります。
物事に飽きやすい特性は、ADHDとの関連も指摘されています。ADHDの方は衝動的に行動しやすく、新しい刺激を求める傾向にあるため、同じ作業を繰り返す場面で集中力が途切れがちです。
さらに、一度興味を失うと注意力が急激に低下し、締め切りの遅れや手順の抜け漏れが発生する場合もあります。
参照:帝京短期大学「発達障害に対する職場における合理的配慮についての一考察
参考:広島大学学術情報リポジトリ「広汎性発達障害をベースに持つ大学生の診断や援助のあり方について : 自閉症スペクトラム指数日本語版(AQ-J)の使用経験からの提言」
仕事の楽しさ・やりがいを感じられない
職場環境のストレスや過度なプレッシャー、適性に合わない業務内容などの要因から、仕事に楽しさややりがいを見いだせないことは、障害の有無を問わず起こり得ることです。この場合は仕事で成長や成果を実感できず、モチベーションが低下して仕事への興味を失い、早期離職につながるケースもあるでしょう。
発達障害の方は、さらに複雑な理由で仕事の楽しさを感じにくいことがあります。集中力を保てない、コミュニケーションがうまくできないといった特性から、周囲の期待にうまく応えられないことで自己肯定感が低下しがちです。また、飽きやすさが影響し、業務を継続することが難しくなると、達成感も得られにくくなるでしょう。
参考:NIVR障害者職業総合センター「発達障害者の職業生活への満足度と職場の実態に関する調査研究」
参考:NIVR障害者職業総合センター「調査研究報告書 No.125発達障害者の職業生活への満足度と職場の実態に関する調査研究]
病気やストレスの可能性も
もともとの性格や発達障害の特性以外に、うつ病などの病気や過労、過度なストレスが原因で仕事を辞めやすくなるケースも少なくありません。特に発達障害の方の場合は、特性による生きづらさから二次障害としてうつ病など精神疾患を発症しやすい傾向にあります。
このようなケースでは、まず身体や精神の状態を回復することが先決です。専門の医療機関を受診して医師のアドバイスを聞き、いったん職場から離れるなどの対応をとる必要があります。
精神疾患などを発症しているにもかかわらず、無理に働き続けると状態が悪化する恐れもあるため、自身の健康を最優先に考えて行動しましょう。
仕事が続かないことによるデメリット5選
仕事を続けられないことには、さまざまなデメリットがあります。まず、スキルが蓄積されにくいため、キャリアアップが難しくなります。収入も安定せず、経済的な不安が増大する可能性も高いです。また、短期間での離職が重なると社会的な信用を得るのが難しくなり、「辞め癖」がつく人もいます。
それぞれの要因を詳しく解説します。
スキルアップが難しい
仕事が続かないと、専門的なスキルを身につける機会が減少し、キャリアの形成が妨げられます。仕事を通じて得られるスキルは、継続的な経験と学習によって深まるものです。しかし、短期間で転職すると、専門性の高い業務に十分に関わる前に職場を離れることになり、スキルが定着しません。
たとえば、ITエンジニアの場合、プログラミング言語の習熟には一定期間の実務経験が必要です。プロジェクトを途中で辞めると、エラー解決や最適化のスキルが磨けず、次の仕事で苦労する可能性が高まります。
一方、仕事を長く続けることで得られる専門性は、キャリアアップの大きな武器となるでしょう。職場を変え続けてスキルアップの機会を逃してしまわないように、働き方をよく検討し計画的なキャリアプランを立てるようにしましょう。
経済的に不安定になる
仕事が続かないと給与が安定せず、経済的に不安定な状態に陥りやすいです。収入が不安定だと生活費の確保が難しくなり、貯金ができない状況を招く原因にもなるでしょう。特に発達障害の方は、自分に合った職場を見つけるまでの期間が長くなる場合が多く、経済的に不安定になるリスクがより高まる可能性があります。
また、頻繁な転職は社会的信用を損ない、ローンの審査が通りにくくなるといった影響も考えられます。経済的安定を得るためには、早期に自身の特性に合った仕事に就き安定した収入を確保するのが重要です。
社会的な信用が得られにくくなる
一つの仕事が続かず、何度も転職することは、社会的信用を得る上で大きなデメリットです。安定した職場に留まるのが難しいと見なされ、雇用主や社会からの信頼が低下する可能性があります。
たとえば、履歴書に短期間の職歴が多数ある場合、採用担当者は「すぐに辞める人」として評価しがちです。こうした評価の積み重ねが、その後のキャリア形成に悪影響を及ぼす場合があります。また、転職のたびに新たな人間関係を築く必要が生じるため、コミュニケーションによるストレスを感じる場面も多くなるでしょう。
安定した職場で人間関係が築けずまた転職し、より社会的信用を低下させてしまうという悪循環に陥っている人もみられます。
対処法として、自分に合った職場環境を見つけるために支援制度を利用するのも良いでしょう。支援制度については後述しています。
「辞め癖」がつくようになる
仕事が続かないと、仕事を辞めることに対する抵抗感が薄れ、「辞め癖」がついてしまう可能性があります。これは、短期間で何度も仕事を辞めるうちに、困難に直面しても努力する前に退職するという選択肢を優先する習慣が身についてしまうためです。
具体的には、職場で嫌なことがあったり、自分の期待と実際の業務がかけ離れていたりした場合に「どうせまた次がある」と考え、安易に辞めるケースがみられます。このような辞め癖がつくと、転職を繰り返すうちに、次第に採用されにくくなるというリスクも生じます。
この状況から抜け出すには、辞める前に自分の現状や仕事への不満を冷静に分析し、解決策を模索するのが大切です。また、周囲の家族や知人など誰かに相談して客観的な意見を得るのもよいでしょう。
自己肯定感が下がる
仕事を続けられない場合、自己肯定感が低下する可能性があります。継続的に続けられる仕事を失うことで自信を失ってしまい、自分を否定する感情が強まっていきます。特に発達障害の人は、社会的な期待に応えられない自分を責めやすく、自分の能力を過小評価しやすいため、さらに自己肯定感が低下する恐れもあるでしょう。
たとえば、職場での人間関係や業務のプレッシャーによって、頻繁に仕事を辞めてしまうと、その度に「自分にはできない」という思いが強まります。この繰り返しは、自己肯定感のさらなる低下を招き、次の就職への不安を強める要因にもなるでしょう。
一方、自己肯定感を取り戻す方法もあります。まずは、自分の特性を受け入れ、過去の経験を見つめ直すのが重要です。自分を責めすぎないように第三者の意見も交えながら、過去の経験を振り返ると、今後転職を繰り返さないためにできることが見つかります。
仕事が続かない人が仕事を続けるための4つの対処法
仕事が続かないと悩んでいる方やそのご家族は、仕事を続けていくためにどのように対処すればよいのか悩んでいるのではないでしょうか。まずは自己分析を行い、自身の特性を理解するのが大切です。次に、ストレスを適切に発散する方法を身につけることで、心身の負担を軽減できます。
また、小さな目標を設定し、少しずつ達成感を感じられるようにするのも、仕事を続けるための効果的な手段の1つです。対処法を実践してもうまく行かない場合は、専門医の受診が必要になるケースもあるでしょう。仕事を続けるための対処法について、それぞれ詳しく解説していきます。
自己分析をしてみる
仕事が続かない人が仕事を続けるためには、まず自己分析が必要です。自己分析をすると、自身の特性や働き方の傾向、強み・弱みなどが把握でき、障害となっている原因を明らかにできます。そして原因がわかると、現状を正しく認識した上で、適切な対策を取れるようになります。
たとえば、業務に対する苦手意識やコミュニケーションの難しさが原因であれば、それに合わせて業務環境を調整してもらえるか相談するのも良いでしょう。また、得意・不得意を分析すると、強みを活かせる場面も知ることができます。
さらに自身の過去の経験を振り返り、どのような状況でうまく仕事をこなせているか、またはうまく行かなかったのかを分析すると、どのような職場なら仕事を長く続けられるか見えてくるかもしれません。
ストレス発散方法を身につける
ストレスは、集中力の低下や対人関係の悪化を引き起こし、職場でのパフォーマンスにも影響を与えます。適切なストレス発散方法を取り入れることで、心身の健康を保ち、仕事を続ける意欲を維持できるでしょう。
たとえば、運動や趣味を通じてリフレッシュするのがおすすめです。ウォーキングやストレッチは、身体を動かすことで気分をリフレッシュし、ストレスを軽減させる効果が期待できます。また、アートセラピーや音楽療法などのクリエイティブな活動も、心を落ち着ける手助けになるでしょう。
自分にとって良いストレス発散方法を身につけると、仕事に対する不安感も軽減され、心身の健康を保ちながら仕事を続けやすくなります。
小さな目標を立てて仕事を続ける
無理なく仕事を続けるための方法として、小さな目標を立てて仕事をこなすのも効果的です。達成しやすい小さな目標を設定すると達成感を得やすくなり、自己肯定感を高めやすくなります。心理学的にも、短期的な目標を達成することで、脳内にドーパミンが放出され、モチベーションを向上させる効果があるとされています。
たとえば、1日30分だけ業務に集中する、平日は7時までに起床するなどが良いでしょう。小さなものでも目標を達成し続けると、少しずつ自信をつけることができ、仕事への取り組み方や考え方も変わっていきます。自分のペースで小さな成功体験を積み重ねることで、将来的に大きな目標を達成する力を養えるでしょう。
病院を受診してみる
仕事に行きたくない、仕事を頑張れないと感じる時が長期間続く場合、うつ病などの精神疾患が隠れている可能性があります。発達障害などの特性自体がストレス源になる人もいますが、その症状が続くことで心身に負担がかかり、気づかぬうちにうつ病に進行する場合もあります。
例えば、集中力の欠如やコミュニケーションの困難さが原因で、業務の負荷が重く感じるようになり、次第に出社自体が苦痛になるケースがあります。こうした状況では、早めに専門医を受診し、適切な支援を受ける必要があるでしょう。
詳しくは下記の記事も参考にしてみてください。
仕事に行きたくないのはうつ病だから?原因や対処法、支援サービスなど解説
自分に向いている仕事を探すポイント
仕事を長く続けるためには、業務内容や職場環境が自分に合っていることが何よりも重要です。自分にとって働きやすい職場を見つけるためのポイントを押さえ、無理をせず働けるように工夫を凝らすとよいでしょう。
ここからは、発達障害の方が自分に向いている仕事を探すときの5つのポイントを紹介します。
特性を理解する
自分の特性への理解を深めれば、自分に合った仕事も見つけやすくなります。自己分析などによって自分の苦手な環境やストレスを感じやすい状況を把握し、苦手やストレスに直面する業務や職種はなるべく避けるとよいでしょう。
反対に、自分の得意分野や強みとなる特性を活かせる仕事を探すことが、仕事を長続きさせるポイントになります。例えば、特定の分野で高い集中力を発揮でき、プログラミングに関心がある方はプログラマーを目指すなど、自分と相性が良さそうな仕事を見つけるのがおすすめです。
働き方を工夫する
仕事でストレスを感じやすい方は、働き方を工夫することも仕事を長く続けるうえで重要です。オフィスで他人の目にさらされながら働くのが苦手な場合は、リモートワークに切り替えるのも一つの方法です。また、所属している部署に苦手な業務が多い場合は、異動を申し出る手もあります。
労働時間が長いと感じている場合は、時短勤務を希望して無理なく働けるようにするのも有効です。根本的に今の仕事が向いていないと感じるときは、無理に働き続けるのではなく、転職を検討することで状況が好転する場合もあるでしょう。
適職診断を受ける
自分と相性のよい仕事を見つけたいときは、適職診断を受けるのも一つの選択肢です。よく知られている適職診断に「GATB(一般職業適性検査)」があります。
GATBは、紙筆検査と器具検査を通して9種の能力を測定し、受検者の適職領域を見極めるテストです。GATBの検査結果から、自分が予想もしていなかった職種に適性があると判明する場合もあります。
GATBは障害者職業センターやハローワークなどで無料で受けられるため、興味がある方は問い合わせてみるとよいでしょう。
障害者雇用を検討する
一般雇用で働き続けるのが難しいと感じる場合は、障害者雇用を検討する方法もあります。病院を受診して発達障害やうつ病などの診断を受ければ、障害者手帳を取得できます。障害者手帳があれば障害者雇用への応募も可能になるため、検討してみるとよいでしょう。
障害者雇用の場合、求職者に障害があることを前提としているため、理解や配慮を得やすいメリットがあります。特性などの影響で仕事上のストレスを感じやすい方は、障害者雇用を利用することで長く働けるようになる可能性が高まるでしょう。
支援機関を活用する
自分一人の力では適職を見つけるのが難しいと感じている場合、支援機関に頼るのが賢明です。転職サイトや転職エージェントを利用すると、自分の希望条件に合致する求人情報を紹介してもらえます。仕事探しの選択肢が増え、向いている仕事を探しやすくなるでしょう。
また、障害がある場合はハローワークや就労移行支援事業所などの支援機関を活用するのがおすすめです。就活やスキルアップのためのサポートが受けられ、仕事を長く続けるための土台作りにも役立つため、ぜひ検討してみてください。
仕事を続けていくために利用できる支援制度・サービスを解説
仕事が続かないと悩む場合、さまざまな支援制度やサービスを利用するのも良いでしょう。ハローワークや地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などは、仕事を続けるために活用できるさまざまなサポートを提供しています。これらの機関を活用することで、職場環境に適応しやすくなり、継続的な就労が可能になるかもしれません。以下では、それぞれの支援制度やサービスの特徴について詳しく解説していきます。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、求職者や求人主に対し、無償でさまざまなサービスを提供する公的機関です。特に障害のある求職者向けには、専門の職業相談窓口が設置されており、専門知識を持つスタッフが担当者制で個別支援を行っています。
個別の支援により、それぞれの特性や疾患にあった適切な職場選びはもちろん、安定した就労ができるようなサポートも行っています。
地域障害者職業センター
地域障害者職業センターは、独立行政法人高齢・障害者・求職者雇用支援機構(JEED)が運営している施設で、全国に最低1か所ずつ設置されています。障害者に対する職業リハビリテーションや事業主向けの雇用管理支援を行っており、発達障害者向けの専門的支援も実施しています。
仕事を続けるための個別サポートも受けられるため、仕事が続かないと悩む方にもおすすめの施設です。
参照:高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「地域障害者職業センター」
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害者が働き続けるためのサポートをする公的な支援機関であり、就労や生活に関する幅広い相談を受け付けています。
職場適応訓練や就労移行支援、生活支援など、個々のニーズに応じたサービスを提供しており、就業面と生活面の一体的な支援を行うことで、より充実したサポートが可能となっています。仕事と生活の両方を充実させたい方に、おすすめの公的サービスです。
詳しくは下記の記事も参考にしてください。
障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)とは?対象者や支援内容、利用の流れを解説
就労移行支援
就労移行支援は、就労を希望する障害のある方を支援するサービスです。利用者は職業訓練や日常生活に関する支援を受けながら、一般企業への就職を目指します。
具体的には、コミュニケーション能力の向上や、ビジネスマナー、時間管理などのスキルを学びます。
Kaienの就労移行支援の特徴は、専門的なカウンセリングや豊富な独自求人です。適職が見つかるアセスメントも実施しており、ビジネススキルが身につく実践型のプログラムも好評を得ています。自分に合った仕事を見つけたい方は、就職実績も豊富なKaienの就労移行支援をぜひご利用ください。
就労移行支援については下記の記事でも紹介していますので、参考にしてください。
就労移行支援とは?受けられる支援や利用方法をわかりやすく解説
自立訓練(生活訓練)
自立訓練(生活訓練)とは、自立した生活に必要な知識やスキルを習得できるよう、障害のある方をサポートする福祉サービスです。カリキュラムを通して障害特性への理解を深めたり、コミュニケーション能力を伸ばしたり、将来を再設計することができます。
Kaienでは就労移行支援だけではなく自立訓練(生活訓練)も提供しており、利用者は仕事だけでなく日常生活に必要なスキルを習得することも可能です。
訓練を通して健康的な生活習慣を身につけ、生活の質の向上を目指します。
就労移行支援事業所との違いは、就労ではなく「自立」を目指す点です。就労に対して具体的なイメージを持てない方や、年単位で自己理解を深めたい方、生活の基盤を築いていきたい方には自立訓練(生活訓練)の利用がおすすめです。
自立訓練(生活訓練)については下記の記事でも紹介していますので、参考にしてください。
自立訓練(生活訓練)とは?就労移行支援との違いや併用についても解説
仕事が続かない人は自分にあった制度やサービスの利用を検討してみよう
仕事が続かない状態が長引くと辞め癖がつき、スキルアップが難しくなります。また、経済的な不安定さや社会的信用の低下を招く恐れもあるため、早めに対策を講じることが重要です。
自分に向いている仕事を見つけるためには、特性への理解を深めたり、働き方を工夫したりするのがおすすめです。ハローワークや地域障害者職業センター、就労移行支援事業所などの支援を活用し、仕事を続けるために必要なスキルを習得するのもよいでしょう。
Kaienでは、専門家が推奨する充実した就労移行支援プログラムを提供しています。興味がある方は、お気軽にKaienの見学・個別相談会に参加してみてください。
*発達障害は現在、DSM-5では神経発達症、ICD-11では神経発達症群と言われます。
監修者コメント
「仕事が長く続かない」というと、自分の弱さや欠点に思えてしまう方も少なくありません。しかし、外来に来る方々と接していると根気がないという単純な問題ではなく、記事にある通り、様々な要因が絡んでいます。精神科医としては仕事を続けられない理由に医学的理由がないかを探ります。気分の問題やADHDやASD特性のような特性の課題がある場合にはそこに焦点をあてて治療をすることが解決の一歩となり得ますね。
そして、これまでに何度も転職を繰り返していた方も、自分の適性に合った職場に変わった途端に長く続く方も多いのです。その意味では、「どんな条件なら自分が力を発揮しやすいか」を見極められるといいですね。仕事を変える経験は、その探求の一部とも言えるでしょう。また、支援者を頼る大きな意味は、その見極めを手伝ってもらえることにあると考えます。自分の得意や安心できる環境を探し、試行錯誤していくことが、結果として長く安定して働ける道につながります。

監修 : 松澤 大輔 (医師)
2000年千葉大学医学部卒業。2015年より新津田沼メンタルクリニックにて発達特性外来設立。
2018年より発達障害の方へのカウンセリング、地域支援者と医療者をつなぐ役割を担う目的にて株式会社ライデック設立。
2023年より千葉大子どものこころの発達教育研究センター客員教授。
現在主に発達障害の診断と治療、地域連携に力を入れている。
精神保健指定医、日本精神神経学会専門医、医学博士。